子どもの未来を育てる習い事選び|第5回
はじめに ― 習い事の選択肢を広げたいとお考えの保護者の皆さまへ
この連載では、AI社会を見据えた子どもの習い事について考えてきました。
前回は「プログラミング力を家庭でどう補うか?」をテーマにお伝えしましたが、今回はプログラミング以外にも未来社会を生き抜くうえで役立つ習い事を取り上げます。
私は普段、小中学生にプログラミングやICT教育を指導しています。その中で感じるのは、学びの土台となる力はプログラミングだけでなく、他の分野でも育まれるということです。
プログラミング以外の未来型スキル習い事TOP5
ここでは、最新の調査結果や教育現場での実感をもとに、プログラミング以外で「これからの時代に役立つ」とされる習い事を紹介します。
1位 英会話
グローバル化が進む中で、英語は「世界とつながるパスポート」です。
文部科学省の調査によれば、小中学生の保護者が子どもに習わせたい習い事の上位には必ず「英語・英会話」が入っています(ベネッセ教育情報サイト「【最新版】子どもに人気の習い事ランキング」2024より)。
英語を学ぶことは単なる言語習得ではなく、異文化理解力やコミュニケーション力を養うことにつながります。
私の教室でも、留学生と一緒にプロジェクトを行うと、日本人の子どもたちは「どう伝えればいいかな?」と頭をひねり、言葉を選び、伝える工夫をするようになります。この体験が、グローバル社会で求められる力につながると感じています。
2位 ロボット・サイエンス系
レゴ®やロボット教材を使った習い事は、プログラミングに直結するだけでなく、**「ものづくりの楽しさ」や「試行錯誤の大切さ」**を学べる点が魅力です。
日本能率協会の調査でも、理科実験やロボット系の習い事に関心を持つ保護者は年々増えていることが示されています。
実際に、私の教室に通う小学生が「ロボットに目をつけたい」と言って、センサーを追加する工夫をしたことがあります。単にプログラムを書くのではなく、アイデアを形にする創造力を育てる場として大きな価値があると感じます。
3位 英語×プレゼン・ディベート教室
英会話に加えて、自分の考えを論理的に発表する力を養う教室も注目を集めています。AIが自動翻訳をしてくれる時代になっても、伝える力・議論する力は人間ならでは。
特に中学生の授業では、「自分の作ったアプリを英語で紹介する」練習を取り入れることがあります。初めは恥ずかしそうにしていた生徒が、回を重ねるごとに自信を持ち、英語で堂々と説明する姿に保護者の方も感動されていました。
4位 芸術・デザイン系の習い事
デザインやアートは「正解が一つではない」世界。これはAI社会における創造性や独創性を養う絶好の場になります。
たとえばデジタルイラストや動画編集などは、単なる表現活動にとどまらず、ICTリテラシーの向上にもつながります。
現場で感じるのは、絵や工作が得意な子がプログラミングを学び始めると、デザインとコードを組み合わせて、驚くほどユニークな作品を作るということです。芸術的な感性と論理的思考の両立は、AI時代に強い個性を発揮する武器になります。
5位 スポーツ・体験型活動
AIが進化する社会では、人にしかできない「体を使った表現」や「チームワーク」も大切です。
サッカーやバスケットボールといったスポーツは、協調性・リーダーシップ・体力を育みます。
ある保護者の方から、「普段は口数の少ない息子が、サッカー仲間と戦術を話すときだけ本当に楽しそうに説明する」と伺ったことがあります。これもまた、言語化力を自然に伸ばす瞬間です。スポーツを通じて学んだ「チームでの役割意識」や「伝える力」は、将来の仕事でも必ず役立ちます。
6位〜10位の注目習い事(簡易紹介)
- ダンス(表現力・リズム感を育てる)
- サッカー(体力づくりと協調性)
- 習字・書道(集中力・丁寧さ・日本文化理解)
- そろばん(計算力・集中力の基礎)
- 音楽・楽器(感性・持続力を伸ばす)
おわりに
プログラミングは「未来の必須スキル」としてお勧めの習い事ですが、家庭でできる工夫もたくさんあります。
大切なのは、保護者の方が子どもの学びに寄り添い、一緒に考える姿勢を見せること。習い事に通えなくても、家庭での小さな体験が子どもの思考力を育み、将来への大きな力となります。
関連リンク
「子どもの未来を育てる習い事選び」シリーズまとめ
- 第1回|最新のお勧め習い事ランキングとプログラミングが1位の理由
- 第2回|お勧めランキングと実際の人気ランキングの「ズレ」とは?
- 第3回|保護者が知っておきたいプログラミングの選び方 ― リアルとオンラインの違い
- 第4回|プログラミング力を家庭ではどう補うか?
- 第5回|プログラミング以外の未来型習い事
このシリーズでは、子どもに合った学び方・習い事の選び方をわかりやすく解説しています。
保護者の方が後悔しないための判断材料として、ぜひ全記事をご覧ください。

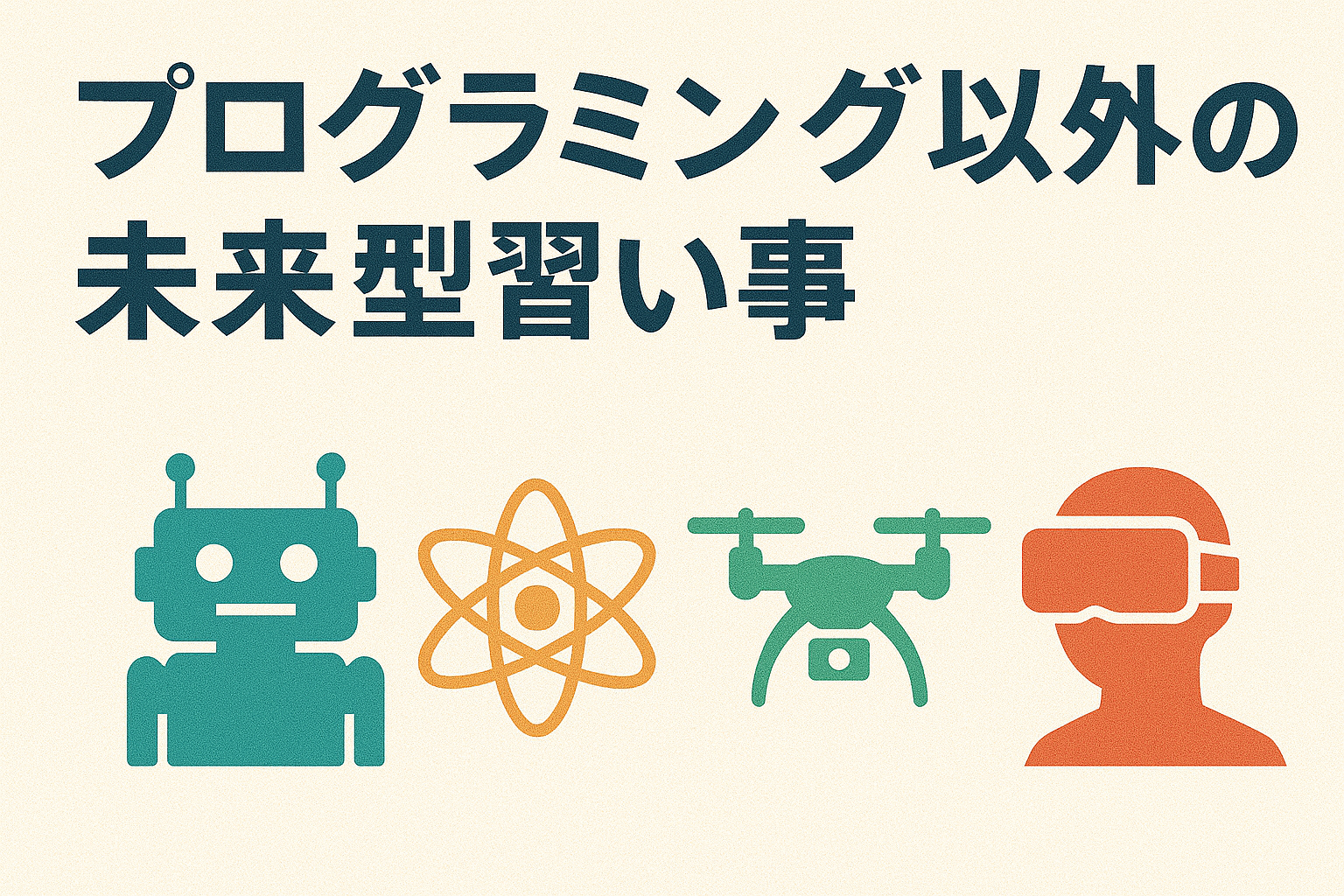
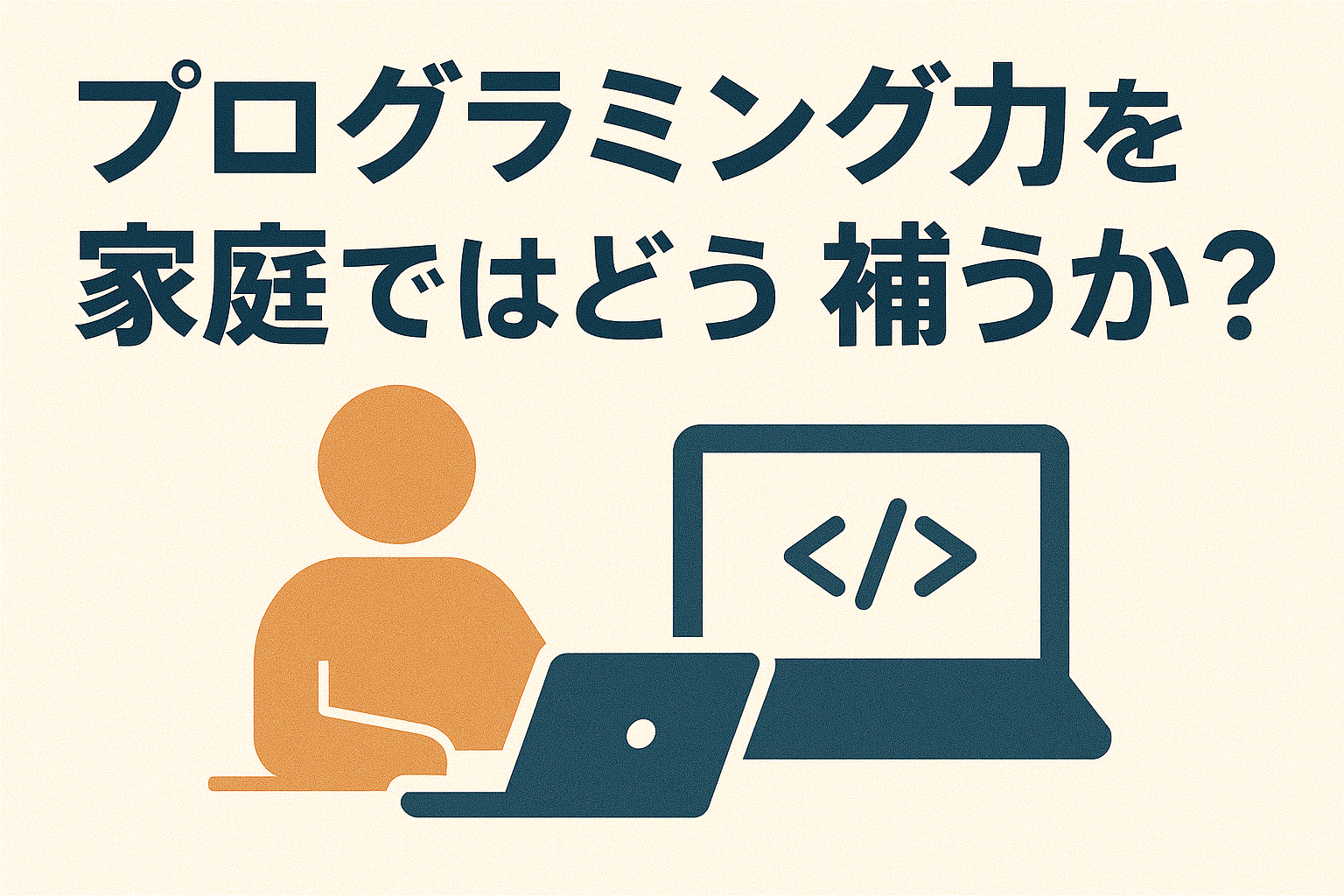
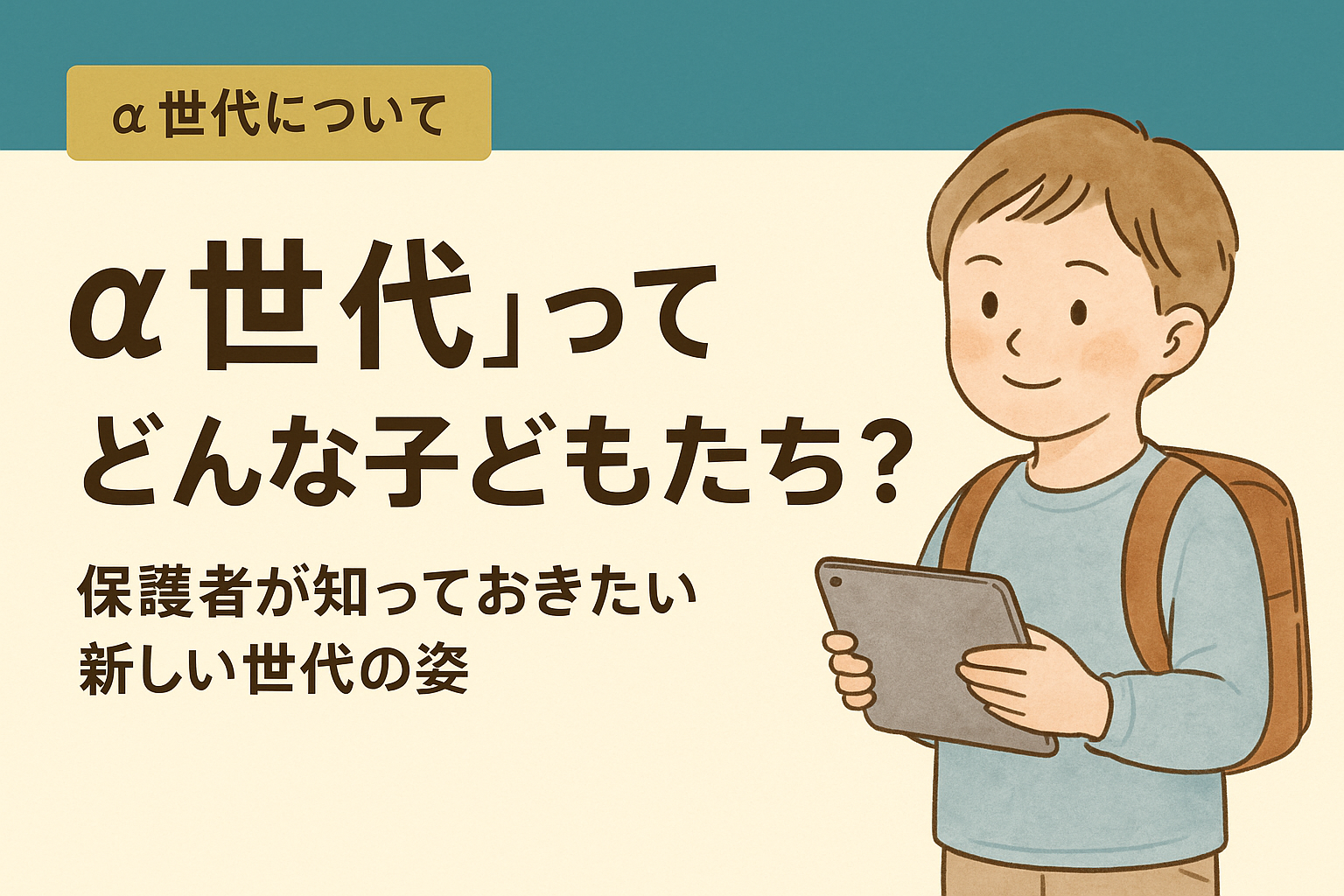
コメント