子どもの未来を育てる習い事選び|第1回
はじめに ― 習い事選びで悩まれる保護者の方々へ
「水泳は体力に良いって聞くし、ピアノをやらせたい気もする。でもAIやデジタルの時代に、本当に必要な習い事って何なんだろう?」
小中学生の保護者の方とお話ししていると、こうした声をよく耳にします。
私は専門学校や子ども向けのプログラミング教室で指導をしていますが、保護者の方から「自分はプログラミングを習ったことがないから、何が身につくのかよく分からない」という相談をよく受けます。
一方で、実際に教室で子どもたちが初めて自分の作ったキャラクターを動かした瞬間の、あの目の輝きや「できた!」という歓声を聞くと、まさに“未来を生き抜く力”が芽生える瞬間を感じます。
今回は、そんな教育者としての現場からの視点も交えながら、**「未来社会で役立つ習い事ランキング」**を整理し、なぜプログラミングが第1位に選ばれるのかを深掘りしていきます。
📊 未来社会に向けたお勧め習い事ランキング(TOP5)
| 順位 | 習い事 | どこが良いか/伸びる力 |
|---|---|---|
| 1位 | プログラミング | 論理的思考・問題分解力・創造力・情報リテラシーを育成。AIを「使う側」になるための基盤を築ける。OECD「Learning Compass 2030」や文科省の「情報I」必修化でも重視されている。 |
| 2位 | 英会話・ディベート | 国際社会での必須スキル。AI翻訳が発展しても、自分の考えを相手に納得感を持って伝える力は人間固有の強。 |
| 3位 | 読書・文章・スピーチ | 情報を整理し、言葉にして相手へ伝える訓練。OECDが提唱する「批判的思考力」や「表現力」を養う。 |
| 4位 | ロボット・STEAM教育 | 実物を動かす体験を通じて、設計思考や試行錯誤の精神が育つ。AI活用を支える“ものづくりマインド”を形成する。 |
| 5位 | 思考系ボードゲーム | 将棋・チェスなどで論理的思考と先を読む力が鍛えられる。楽しみながら学びの習慣づけが可能。 |
💡 プログラミングが「お勧め1位」の理由とは?
国際機関・行政も強調する「計算論的思考」
OECDの Learning Compass 2030 では、未来に必要な力として「知識 × スキル × 態度・価値観」の組み合わせが示され、その中核にあるのが**Computational Thinking(計算論的思考)**です。これは「問題を分解し、筋道を立てて考え、解決策を試す」力。まさにプログラミング学習で身につく能力です。
さらに日本でも、文部科学省が2020年度から小学校でプログラミング教育を必修化し、2025年度からは大学入学共通テストに『情報』科目が加わることが決定しています。これは社会全体がプログラミング的思考を持つ人材を求めている証拠です。
“つくる力”と“考える力”が同時に育つ
プログラミングは、算数や国語のように与えられた問題を解くのではなく、自分で問題をつくり、それをどう解決するかを設計する活動です。
授業の中で、ある小学生が「雪玉を画面の真ん中に表示する」課題に取り組んでいました。最初は「なんでうまく出てこないの?」と戸惑っていたのですが、座標の意味を一緒に確認して、少し数値を変えて実行した瞬間、画面の真ん中に雪玉が現れました。
その子の顔がパッと明るくなり、「できた!」と叫んだ場面を今でも鮮明に覚えています。
このように、失敗と成功を行き来しながら学ぶ過程で、子どもたちは自分で考える力や表現力を育てていくのです。
AIを使いこなすための“共通言語”
AIは人間の指示を「言葉」として受け取ります。
生成AIをうまく活用できるかどうかは、自分の考えを論理的に言語化できるかどうかに大きく依存します。
プログラミングの学びはまさにこの「言語化」のトレーニング。
どんな手順で動かすのか、どんな結果を期待しているのかをコードで表す過程は、将来AIと共創する力に直結します。
👨🏫 現場での実感 ― プログラミングが開く子どもの表現
プログラミング教室で、ある小学生が「ロボットにダンスをさせたい」と言いました。最初は動かすだけで手いっぱいで、「なんで動かないの?」と困っていました。そこで一緒に条件分岐の考え方をかみ砕いて説明すると、数分後には自分でコードを直し、見事にロボットを音楽に合わせて動かすことができました。
その子が「先生、ぼくが考えた通りに動いた!」と嬉しそうに話してくれた時、私は改めて思いました。プログラミングは単に“技術を覚える”以上に、子どもが自分のアイデアを言葉にして実現する体験を与えてくれる学びなのだと。
保護者の方にこの話をすると、よく「なるほど、勉強の点数だけじゃなくて、考える力や表現力が伸びるんですね」と安心されます。
🗂️ 6位〜10位の人気習い事(簡易紹介)
実際の調査(ベネッセ教育総合研究所、学研 2024 など)によると、以下の習い事が人気上位に並びます。
- 6位:ダンス(体力づくりやリズム感、表現力が身につく)
- 7位:サッカー(仲間との協力・体力向上)
- 8位:習字・書道(集中力、美しい文字、礼儀作法)
- 9位:プログラミング(関心は高まるが、まだ選択は限定的)
- 10位:ピアノ以外の楽器(バイオリン・ギターなど)(情操教育、継続力)
おわりに
データが示す「お勧め」と「実際の人気」の違いは、単なるトレンドの差ではありません。
保護者が「自分の経験のある習い事」を選びがちな一方で、AI社会で必要なスキルとの間にはまだギャップがあります。
教育現場で子どもたちがプログラミングを通して自信をつけ、目を輝かせる瞬間を数多く見てきました。親が知らないという理由だけで、子どもの未来の可能性を狭めてしまうのは本当にもったいない。
次回予告
次回は、「お勧めランキングと実際の人気ランキングの「ズレ」とは?」 このギャップに焦点をあてて「なぜプログラミングはまだ“選ばれにくい”のか?」をデータや実体験から掘り下げます。ぜひ続けてご覧ください。

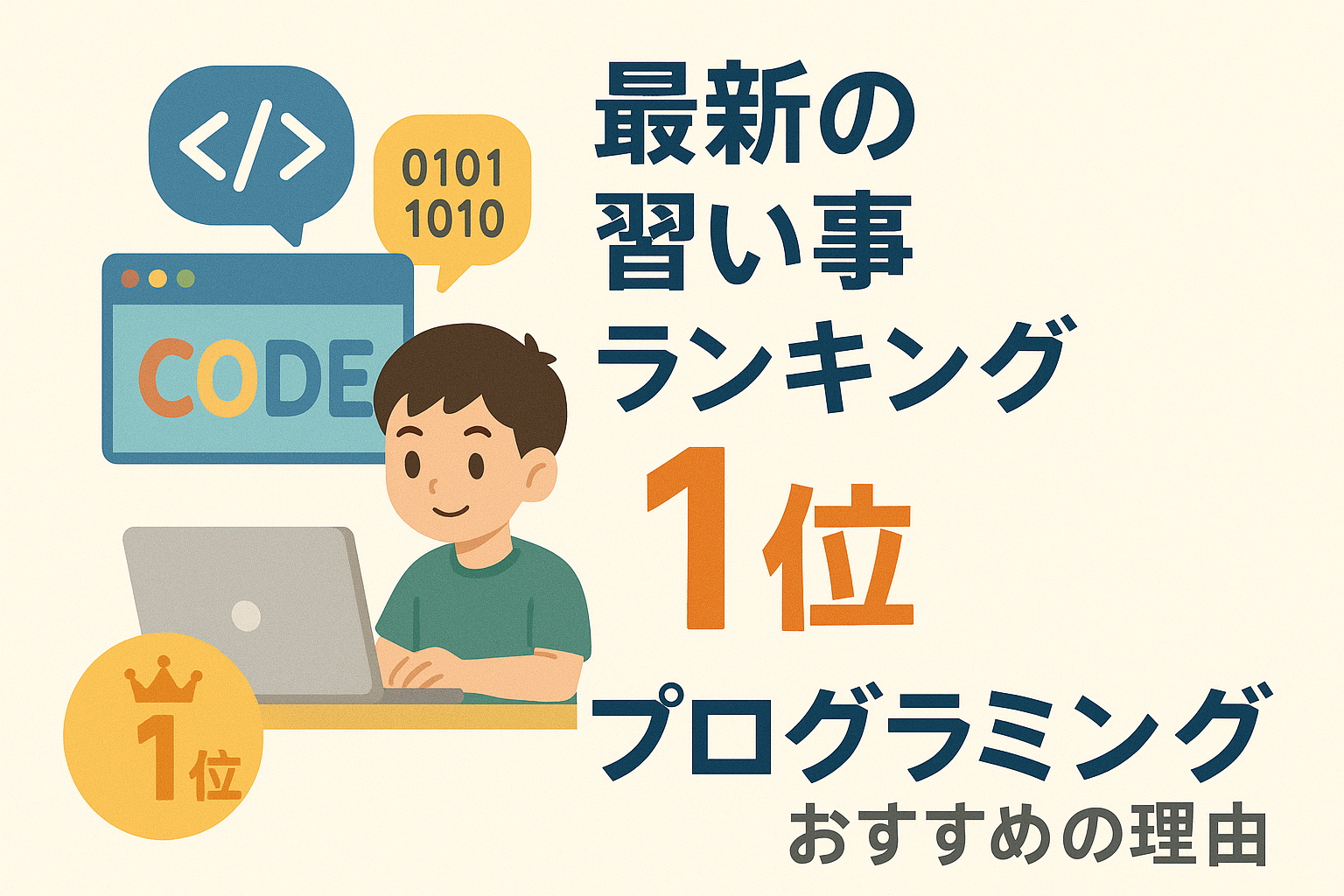

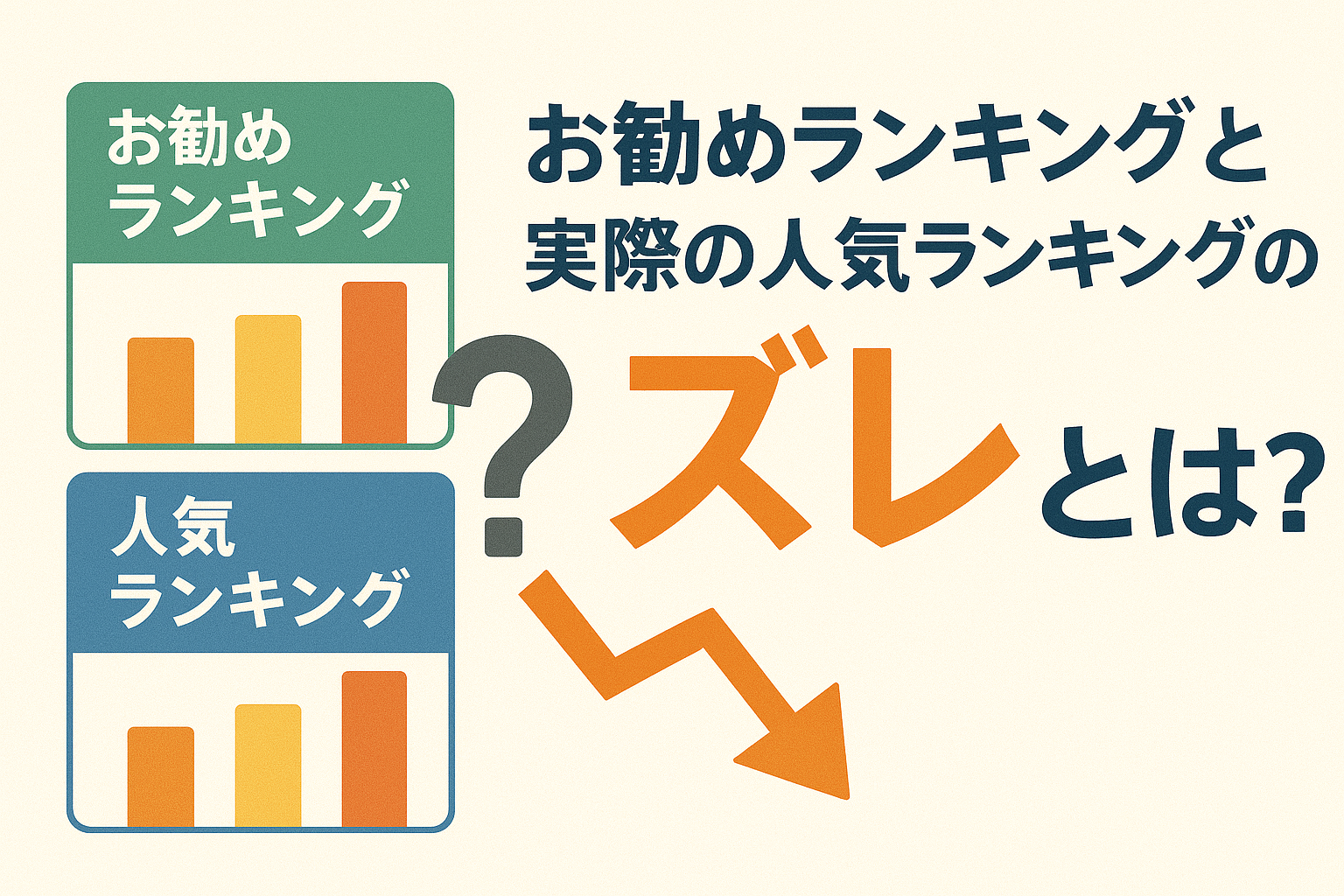
コメント