はじめに
グループディスカッション(GD)では、自然と役割分担が生まれます。
リーダー、書記、タイムキーパー、発表者といった役割は、議論を進める上で重要な存在です。
でも、「どの役割を選べば評価が高いの?」「役割ごとに何を意識すればいいの?」と迷う学生も多いはず。
今回はそれぞれの役割に求められる行動とNG行動を整理し、オンラインGDでの注意点やAI時代のテーマ例も交えて解説します。
役割の決め方
GDの最初の数分で役割を決めることが多いです。
方法はシンプルで、立候補する/自然に分担される/ジャンケンで決める など。
👉 ポイントは「決め方」そのものではなく、決まった役割をどう遂行するか です。
役割がかぶったときは、
- 「では私はサポートに回ります」
- 「最後のまとめを担当します」
と譲る姿勢が評価につながります。
リーダー
評価される行動
- 論点を提示し、議論の方向性を示す
- 意見を拾い、全員に発言の機会をつくる
- 時間を意識して「まとめ」に導く
NG行動
- 自分の意見を押し通す(独裁型)
- 逆に何もしない(名ばかりリーダー)
👉 良いリーダーは「まとめ役+促し役」。
強さより調整力 が評価されます。
書記
評価される行動
- 出た意見を簡潔に板書(ホワイトボードやメモ)
- 類似の意見をまとめて見やすくする
- 「ここはこういう意見が多いですね」と要約して流れを整理
NG行動
- 黙々と書くだけで発言ゼロ
- メモが乱雑で誰も読めない
👉 書記は「見える化」の貢献が大きい役割。
発言しながら書けると評価が上がります。
タイムキーパー
評価される行動
- 「あと10分です」「残り5分なので結論に入りましょう」と時間を区切る
- 議論の進行に応じて柔軟にアラートを出す
NG行動
- ただ時計を見ているだけ
- 「もう時間です」と急かすだけで、議論の流れを壊す
👉 タイムキーパーは「議論を着地させる影のリーダー」。
残り時間を共有する一言で評価が変わります。
発表者
評価される行動
- 結論 → 理由3点 → 実行案 → 一言まとめ、の流れで端的に話す
- 30秒版/60秒版を意識する
- 他のメンバーの意見を反映していることを示す
NG行動
- 自分の意見だけを強調する
- 結論が伝わらない(だらだら話す)
👉 発表者は「顔」として見られるため、聞き手に伝わる話し方 が重要です。
オンラインGDの注意点
- 発言がかぶりやすい → 「〇〇さんどうぞ」と順番を回す
- 書記は共有ホワイトボードやチャットを活用
- タイムキーパーは「残り時間+次のステップ」をセットで伝える
👉 オンラインでは「気配り」が特に評価されます。
AI時代のテーマ例
最近のGDテーマでは「AI」が話題になるケースも増えています。
例:
- 「大学教育に生成AIを導入すべきか?」
- 「AI時代の働き方改革をどう進めるか?」
👉 こうしたテーマでは「AIにできること/できないこと」を意識できると、議論に深みが出ます。
筆者の一言
講師の立場としてGDをどう評価するかというと、「リーダーをやったから評価される」という単純なものではありません。 むしろ、与えられた役割をどう遂行するか がすべてです。
書記でも、タイムキーパーでも、周囲に配慮して役割を果たしている学生は評価が高いです。
「自分は裏方だから…」と引いてしまうのではなく、自分の役割でできることを全力でやる。
これが最も評価に繋がります。
まとめ
- GDの役割はリーダー/書記/タイムキーパー/発表者
- どの役割でも「責任を果たす姿勢」が評価される
- オンラインGDでは特に気配りが重要
- AIテーマでは「人とAIの役割分担」を意識すると深みが出る
👉 大切なのは「どの役割をやるか」ではなく、「その役割をどう果たすか」。
次回予告
次回(第4回)は、「実戦ドリル:頻出テーマ20題+ミニ台本」 を紹介します。
実際に出題されやすいテーマを例に、練習に使える台本やプレゼン雛形を解説します。


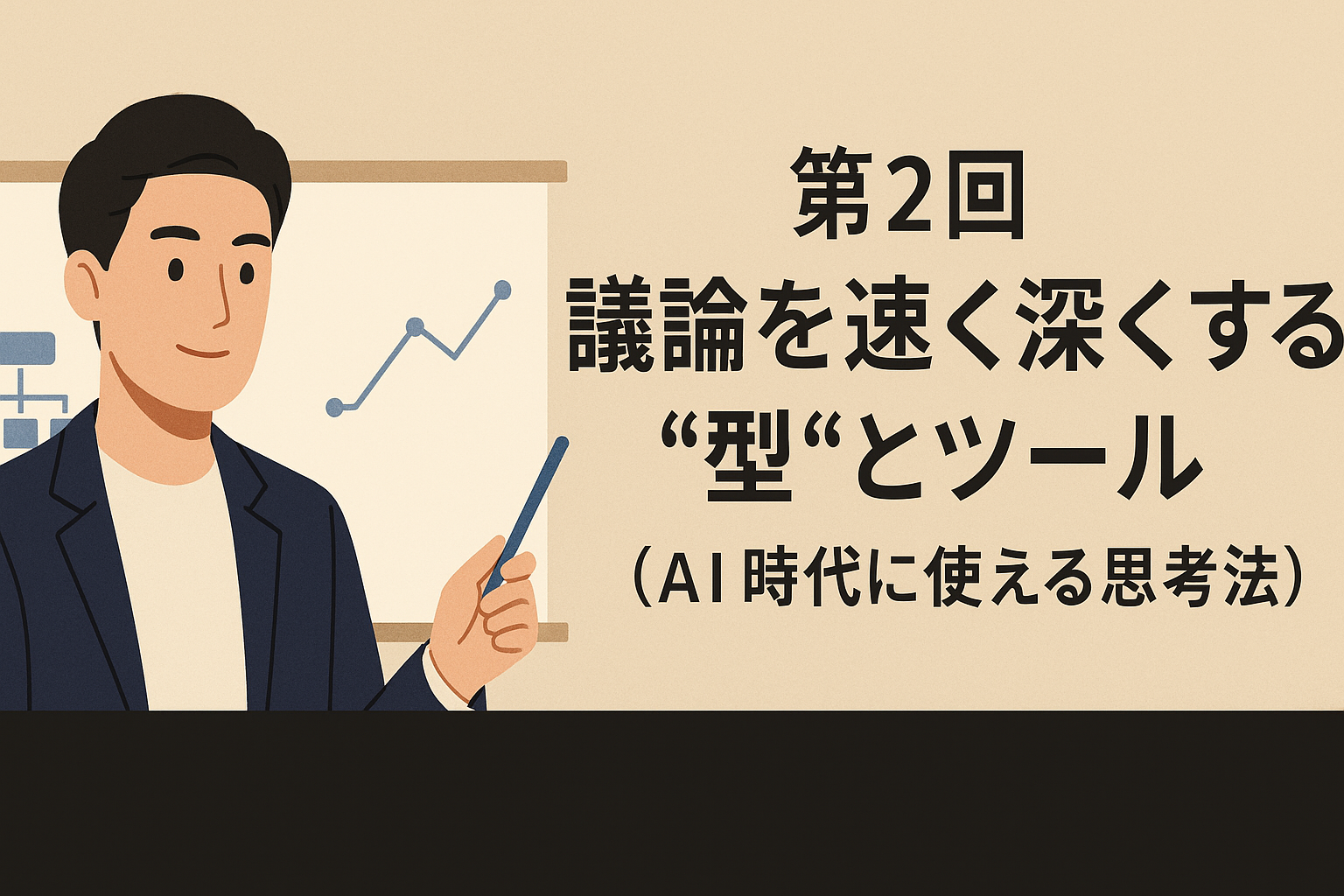
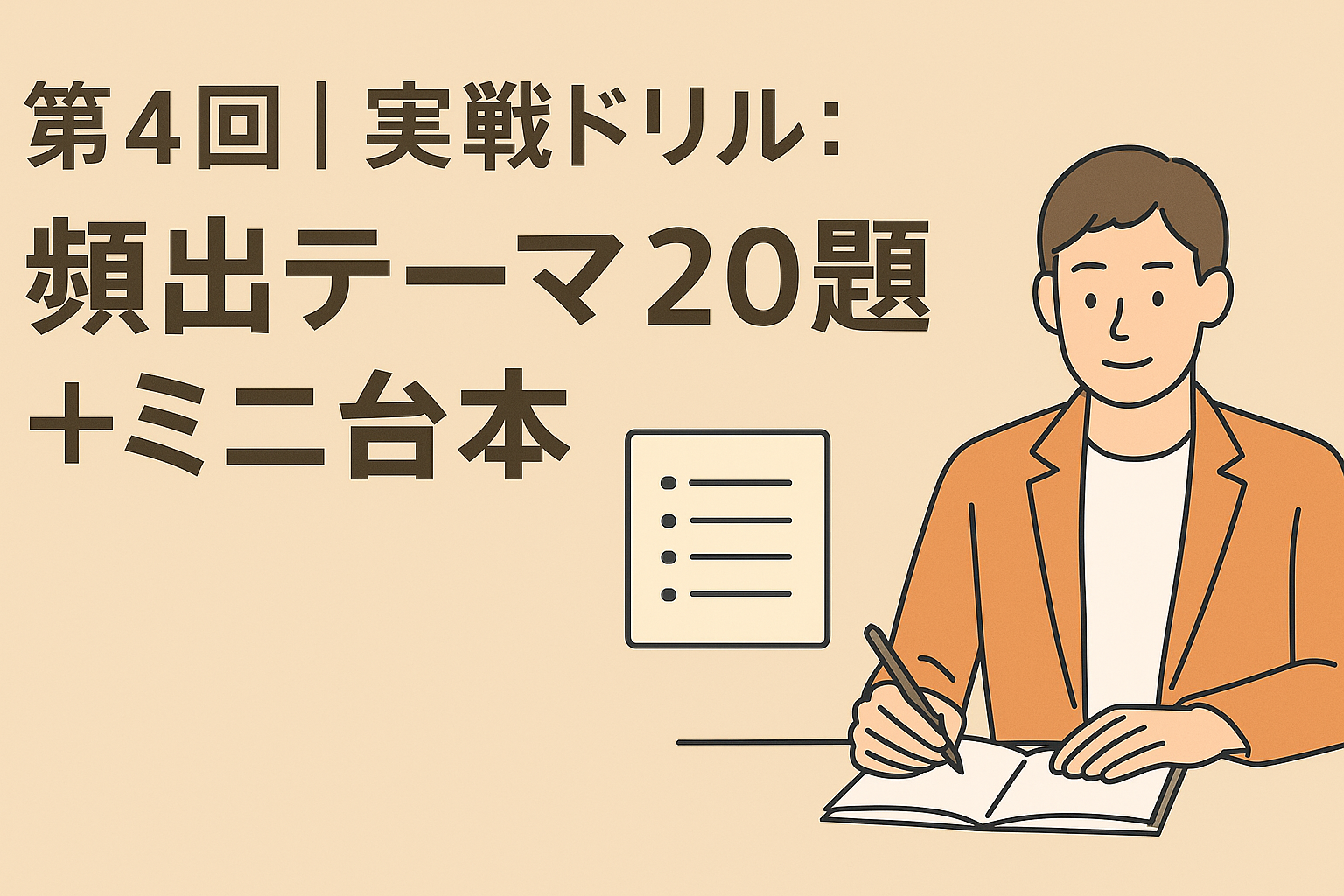
コメント