はじめに
グループディスカッション(GD)は、知識よりも「議論の進め方」と「協調性」が重視されます。
その力を伸ばすには、実際のテーマで練習すること が一番効果的です。
今回は、就活でよく出題されるテーマ20題をタイプ別に紹介し、実際の流れをイメージできる「ミニ台本」や「発表の雛形」も用意しました。
頻出テーマ20題(タイプ別)
課題解決型
- 少子化を解決するには?
- 地方創生を進めるには?
- 働き方改革をさらに浸透させるには?
- 学生の就職ミスマッチを減らすには?
- 災害時の避難所の課題を改善するには?
新規企画型
- 若者に読書を広めるには?
- 外国人観光客を増やす新しい施策は?
- 大学祭を地域に開かれたイベントにするには?
- 学生向け新SNSを普及させるには?
- 健康志向を取り入れた新サービスを考える
賛否討論型
- 大学の授業に出席確認は必要か?
- 学生にアルバイト経験は必須か?
- 日本は移民をもっと受け入れるべきか?
- 東京一極集中は是正すべきか?
- AIによる自動化は雇用を奪うか?
AI・最新テーマ型
- 生成AIを教育に導入すべきか?
- AIと人間の役割分担はどうあるべきか?
- SNSでの発言にAIによる規制は必要か?
- AIが書いた記事や論文は信用できるか?
- AI面接は公平な採用方法といえるか?
👉 これらのテーマは「正解がない」ものばかり。
大切なのは論理的に意見を出すことと、グループで結論をまとめることです。
ミニ台本(例:課題解決型「少子化を解決するには?」)
- リーダー:「まず、少子化の原因を整理しませんか?」
- 書記:「教育費・働き方・結婚観の変化、と大きく3つ出ていますね」
- メンバーA:「教育費が高いのが一番の課題だと思います」
- メンバーB:「働き方の改善も必要だと思います。育休や時短勤務など」
- タイムキーパー:「残り10分なので、そろそろ解決策に絞りましょう」
- リーダー:「では、教育費支援と働き方改革を柱にまとめますか?」
- 発表者:「私たちの結論は『教育費の支援強化と柔軟な働き方制度の推進』です」
👉 実際のGDも、このように「意見出し→整理→結論」で進みます。
プレゼン雛形(30秒/60秒)
30秒版
「私たちの結論は〇〇です。理由は3点あります。第一に△△、第二に□□、第三に◇◇です。以上です。」
60秒版
「私たちの結論は〇〇です。その理由は3点あります。第一に△△、第二に□□、第三に◇◇です。さらに、この結論を実行するために、××という方法が有効だと考えます。以上です。」
👉 「結論→理由→まとめ」の型を覚えておけば、どんなテーマでも対応できます。
コラム:アイデアを広げる「ブレインストーミング」
GDの「意見出しフェーズ」では、ブレインストーミング の考え方を使うと効果的です。
4原則
- 批判禁止(相手の意見を否定しない)
- 自由奔放(大胆な発想も歓迎)
- 質より量(まずはたくさん出す)
- 結合改善(意見を組み合わせて発展させる)
授業で見ていても、このルールを守った班は意見が活発に出て、結論も説得力を増していました。
筆者の一言
学生がGDを練習するとき、最初は「何を言えばいいかわからない」と戸惑いがちです。
でも、テーマ例や台本を使って練習していくうちに、発言の型が身について自信が出てくるのを感じます。
GDは知識テストではありません。
むしろ「意見を出して、相手の意見を受け止めて、まとめる練習」を繰り返すことが最大の対策です。
まとめ
- GDは実際のテーマで練習するのが一番効果的
- 課題解決型・新規企画型・賛否討論型・AI関連など多彩なテーマが出題される
- ミニ台本を使うと議論の流れがイメージしやすい
- 発表は「結論→理由→まとめ」の型で端的に
- 意見出しでは「ブレインストーミング」のルールが有効
次回予告
次回(第5回)は、「企業実例と就活生へのメッセージ」 を紹介します。
実際にGDを導入している企業例や本番直前チェックリストを取り上げ、AI時代を生き抜く就活のヒントをお伝えします。

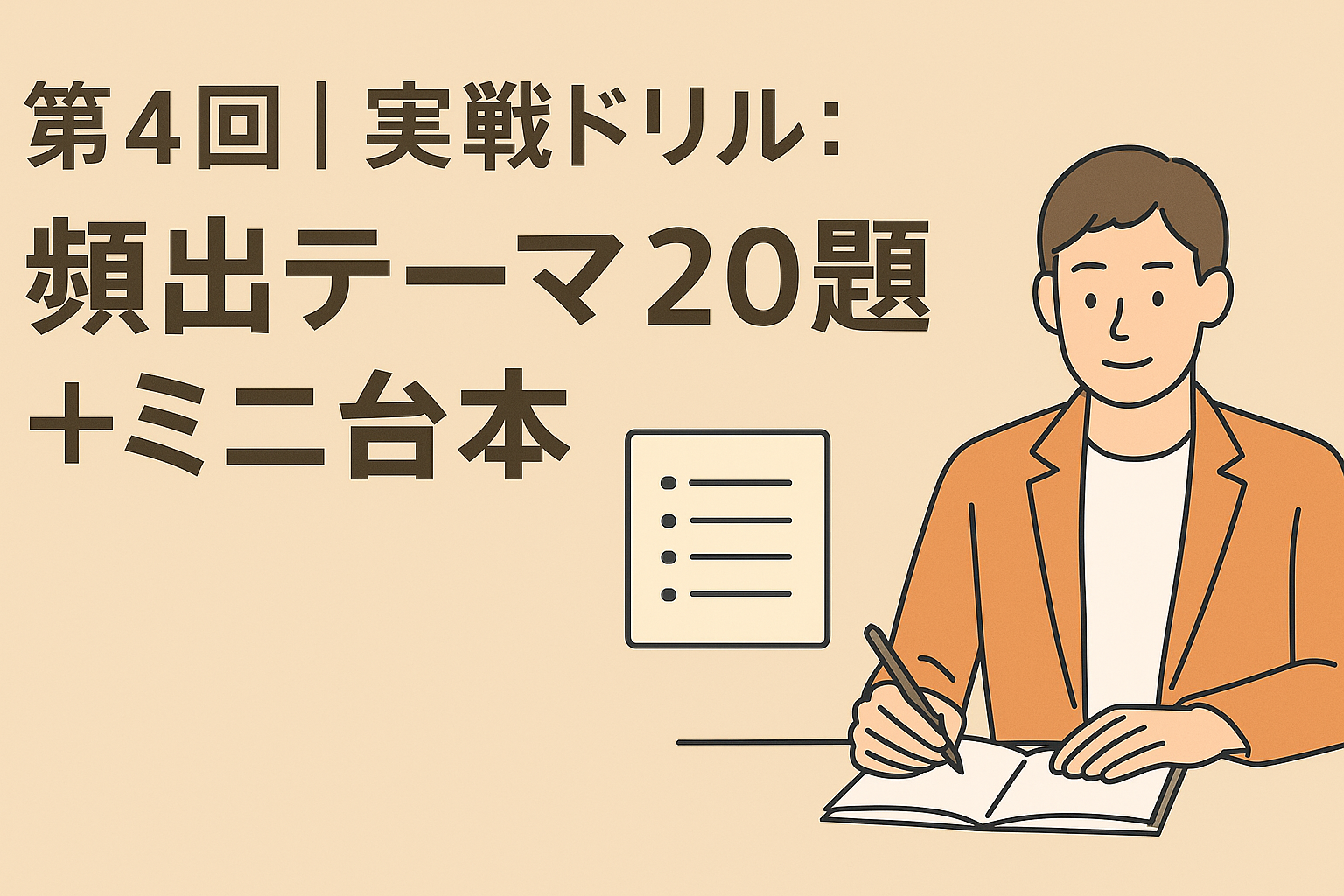

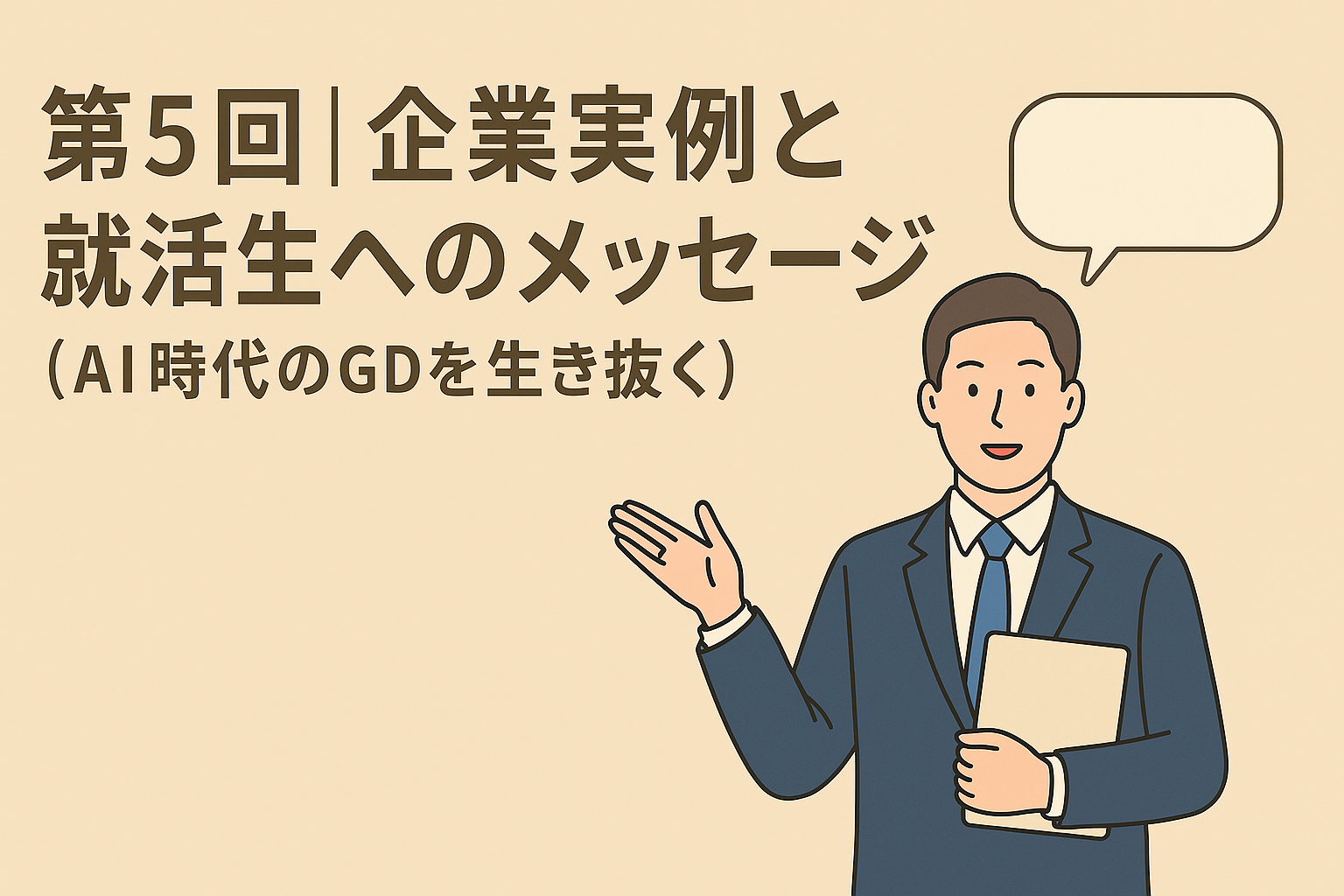
コメント