未来を切り拓くα世代|親が知っておきたい5つの視点|第3回
「これからの子どもたちの未来って、どうなるんだろう?」
保護者の皆さんも、一度はそう考えたことがあると思います。
AIによって仕事や社会の姿が大きく変わる時代。
今の小学生=α世代は、先の見えない未来に立ち向かわなければならない最初の世代です。
そんな彼らをどう表現するかで、世の中の見方は大きく変わります。
“迷走世代”と見られてしまうかもしれない理由
※ここでいう“迷走世代”という言葉は、実際に存在する呼称ではありません。
ただ、将来が見えにくい現状を考えると、そう感じられてしまう可能性があるのです。
- 将来、どんな仕事が残るのか誰にも分からない
- 進学や就職の道筋が、これまでのように一本ではなくなっている
- 大人自身がAIの変化に戸惑っているため、不安をそのまま子どもに投影してしまう
こうした背景から、α世代は「夢を持ちにくい」「方向性が見えにくい」世代として、“迷走しているように見える”と言われても不思議ではありません。
実際は“開拓世代”と呼ぶべきでは?
しかし一方で、こう考えることもできます。
- AIを当たり前のように使いこなし、新しい価値をつくる最初の世代
- 正解のない課題に取り組み、自分なりの答えを探し出す力を身につける世代
- 多様な選択肢を前に、自分で未来を切り拓く経験を積む世代
つまり、迷走どころか“開拓”に挑むフロンティア世代とも言えるのです。
筆者の視点 ― 不安を投影するより可能性を信じたい
私自身、教育の現場で子どもたちと向き合っていて感じるのは、彼らは“迷っている”のではなく“探している”ということです。
AI時代の変化は確かに不安です。
でもその不安を「迷走」とラベルづけしてしまうのは、大人の側の気持ちにすぎません。
保護者にできるのは、道を示すことよりも「一緒に歩きながら考えること」。
そうすれば子どもたちは、“迷走世代”ではなく“開拓世代”として自分の未来を切り拓いていけるはずです。
次回予告
次回は、α世代にとって本当に必要な力とは何かを考えます。
キーワードは「正解探し」ではなく「道を切り拓く力」。
学校や習い事、そして家庭でどのように伸ばしていけるのかを具体的に見ていきます。
未来を切り拓くα世代|親が知っておきたい5つの視点(第4回) どうぞお楽しみに。

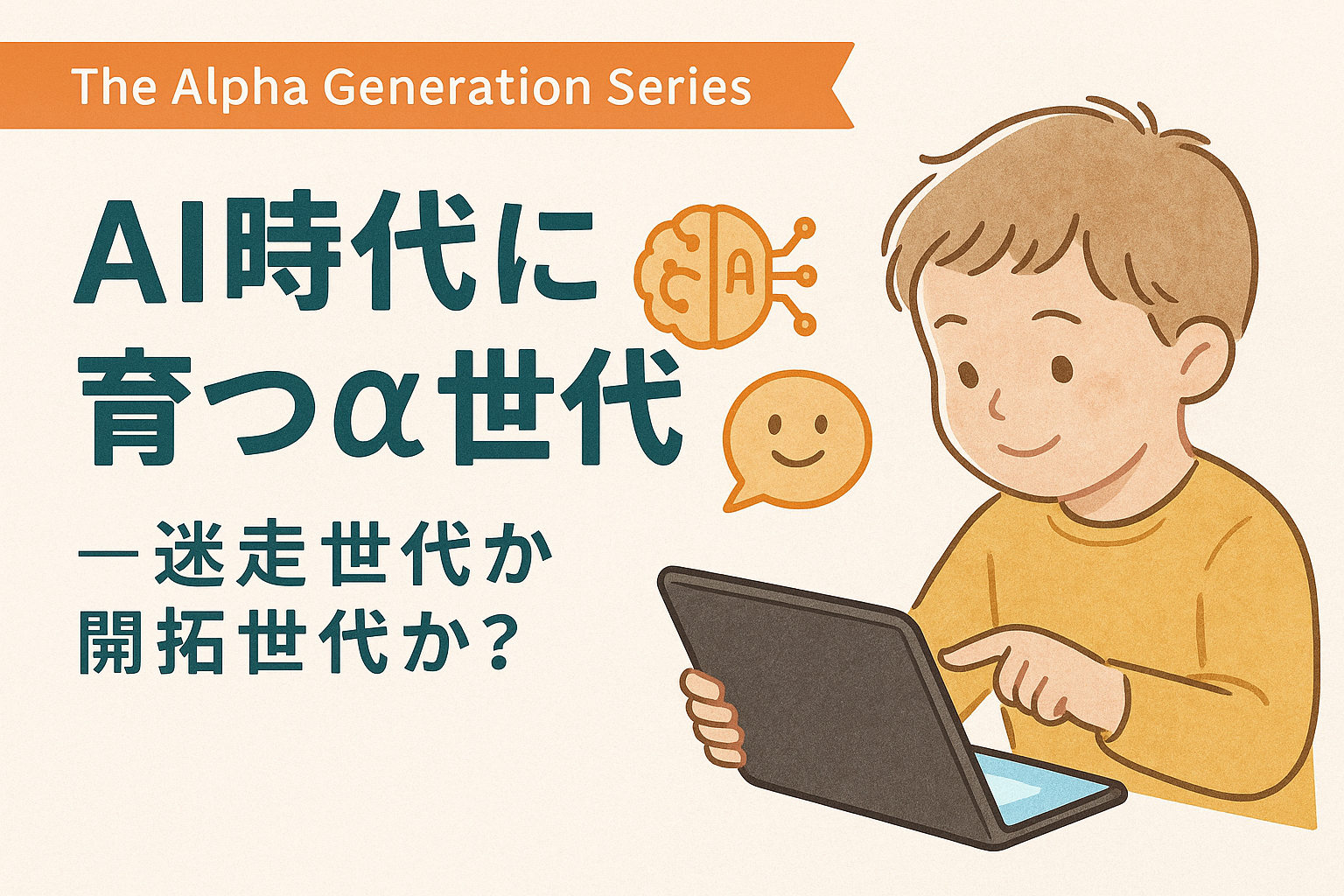
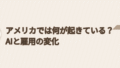
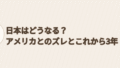
コメント