― 夏休みの家庭実践ガイド ―
はじめに
小学3・4年生は「なぜ?どうして?」という疑問が増え、考える力・表現する力が育つ時期です。
このタイミングで、家庭でのサポートを工夫すれば、子どもの「探究心」をグンと引き出すことができます。
このページでは、自由研究・作文・Scratch作品づくりなど、親子で楽しめる具体的な進め方をご紹介します。
🔬 実践①:自由研究「おにぎりが固くなる理由」
🎯 目的
- 身近なテーマから調べる力・まとめる力を育てる
- 興味を深める“探究型学習”の入門にぴったり
🧭 進め方ステップ
- おにぎりをラップで包んで、冷蔵庫に入れる(時間:半日〜1日)
- 取り出して「見た目・におい・食感」をメモ
- 「なぜ固くなったのか?」を親子で一緒に予想する
- ネットや図鑑で調べて、「水分」「でんぷん」の変化を調査
- まとめ:実験前後の違い+気づいたこと+自分の意見を書く
💬 保護者の声かけ例
- 「どうして固くなると思う?」
- 「調べる前と後で、考えがどう変わった?」
- 「発表するとしたら、どこを一番伝えたい?」
🧑💼 実践②:家族インタビュー作文「わたし新聞」
🎯 目的
- 相手の話を聞き、まとめて伝える「表現力」や「共感力」を育てる
- 親との対話から新しい気づきを得られる
🧭 進め方ステップ
- 家族(親・祖父母・兄弟など)にインタビューする人を決める
- 「好きな食べ物」「小さいころの夢」など質問を3〜5個考える
- インタビューを実施し、メモを取る(録音でもOK)
- 聞いた内容を“新聞スタイル”でまとめる
例:タイトル/話の内容/感想+似顔絵などを自由に
💬 保護者の声かけ例
- 「話してみて、意外だったことあった?」
- 「伝えたいことを1つだけに絞るとしたら?」
- 「“へぇ〜!”と思ったところを強調してみよう!」
💻 実践③:Scratchで「迷路」や「クイズ」をつくる
🎯 目的
- 自分のアイデアを“形にする”経験で創造力と論理力を育てる
- うまくいかない→直す→試す、の“試行錯誤”を体験
🧭 進め方ステップ
- Scratch(https://scratch.mit.edu)にアクセスし、アカウント作成(保護者が管理)
- 「迷路を作る」「3問クイズを出す」など、テーマを一緒に決める
- 背景・キャラ(スプライト)を配置し、矢印キー操作やif文で動かす
- 動いたらOK!完成度にこだわりすぎず「動く楽しさ」を一緒に喜ぶ
💬 保護者の声かけ例
- 「どんな動きにしたい?」
- 「間違って動いたらどう直せばよさそう?」
- 「完成したら誰に見せたい?」
まとめ|「問い」から始まる学びが、子どもを伸ばす
この時期の子どもは、「正解を当てる」より「考えるプロセス」にワクワクします。
自由研究、作文、プログラミングはすべて、「自分の思いを形にする」手段です。
大人の手助けは最小限にして、**「子ども自身が気づく」「自分で考える」**を引き出せる関わりを意識してみましょう。
🔜 次回:小学5年〜中学2年生編|“習慣化”と“振り返り力”を育てるコツ

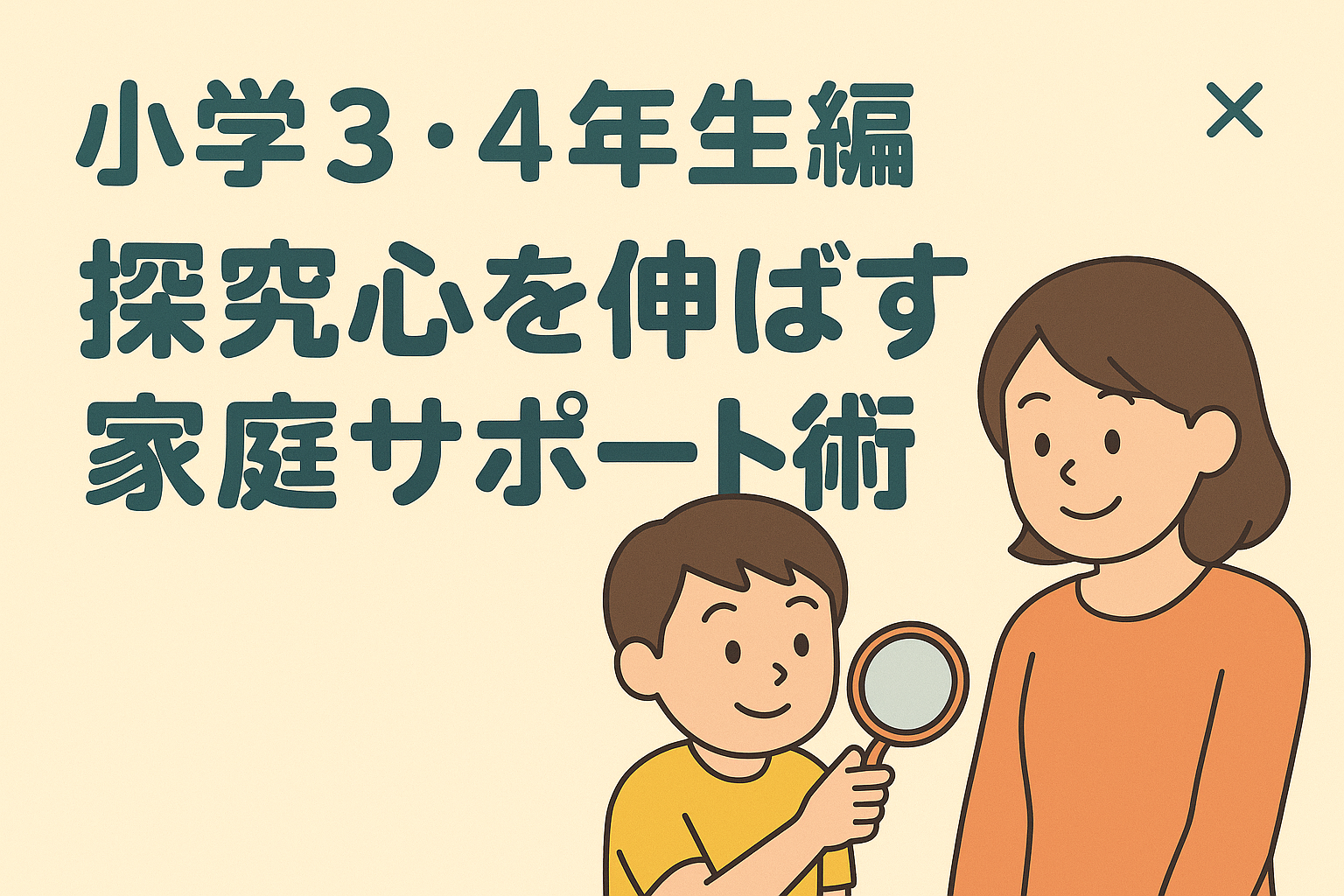
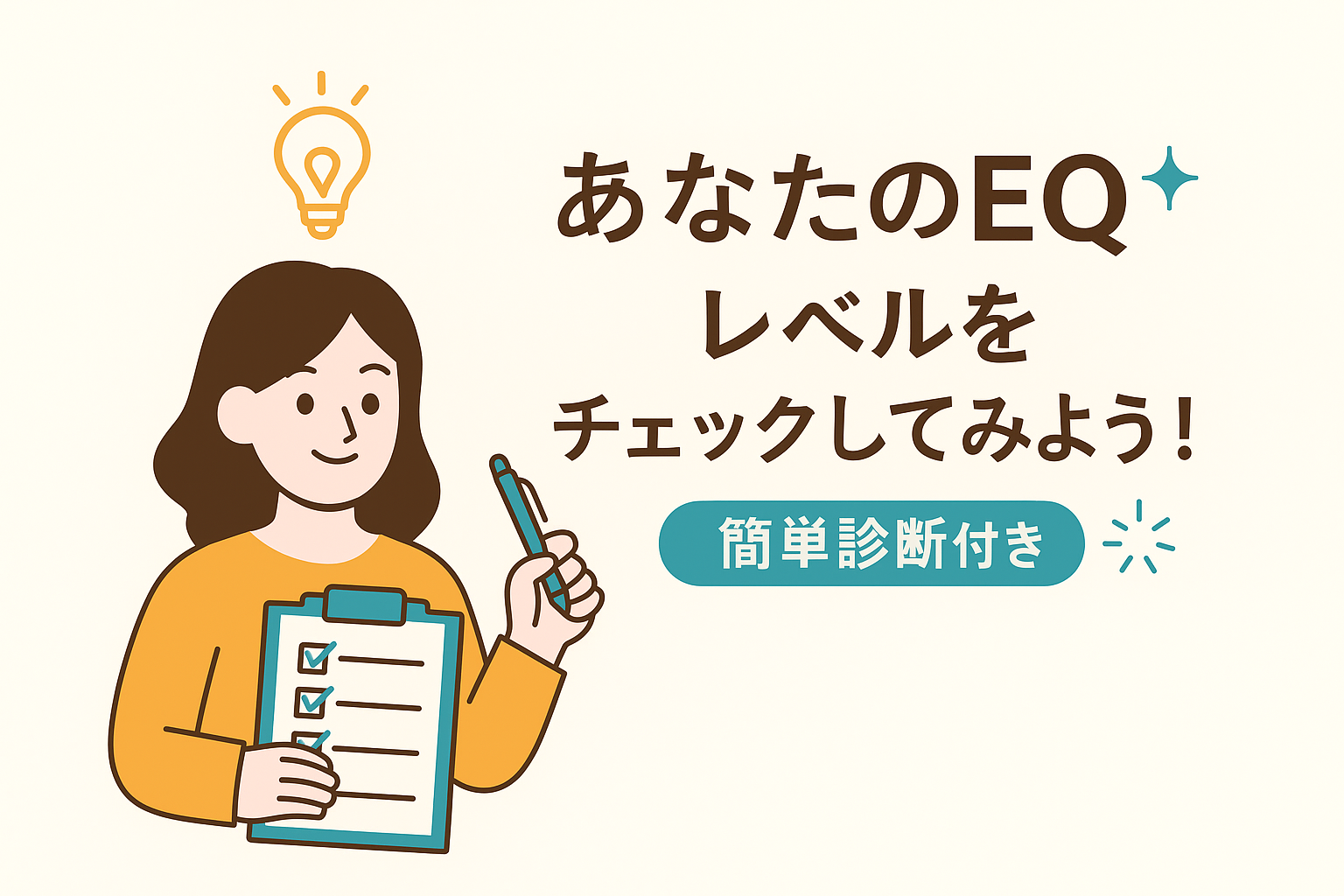
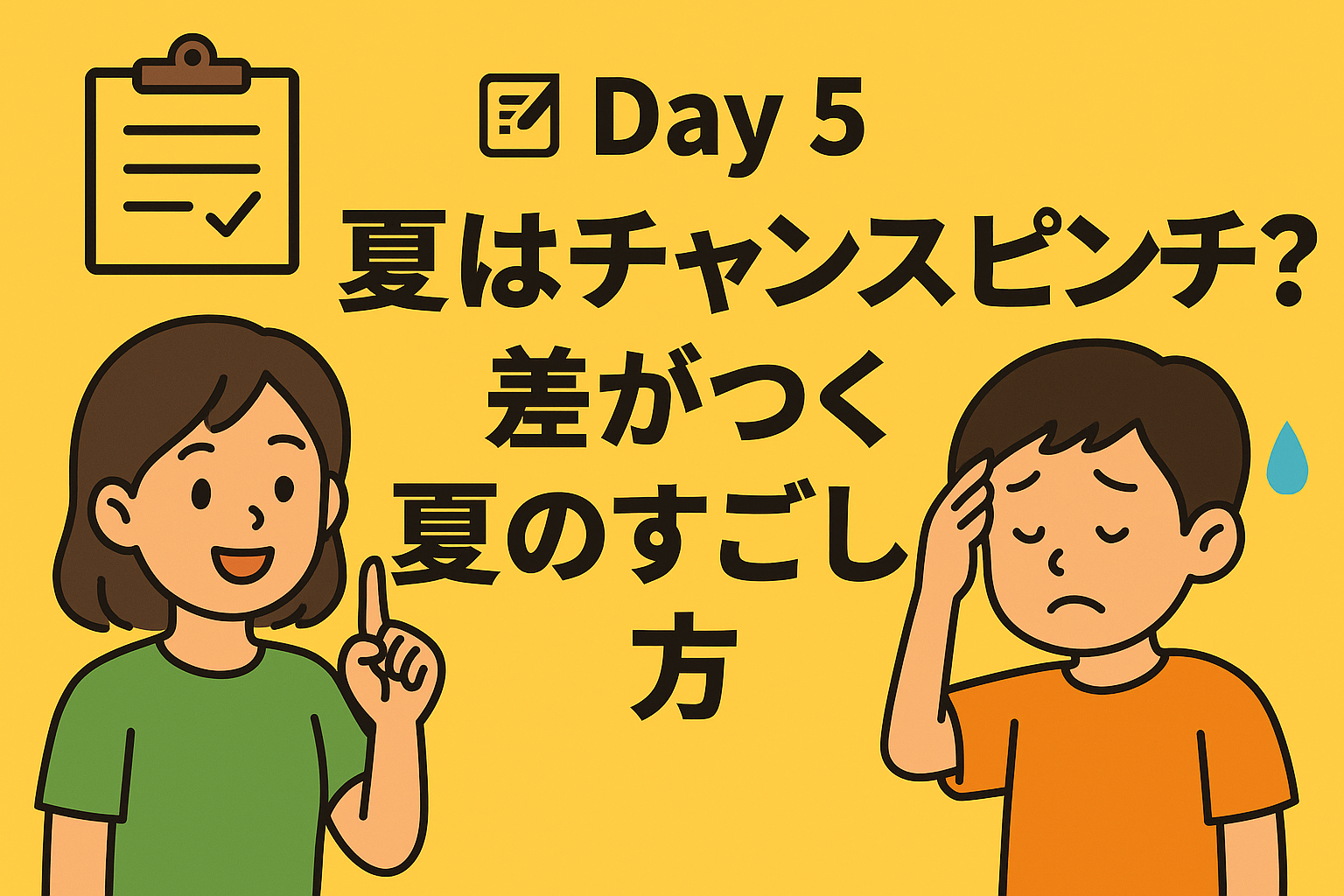
コメント