はじめに:止まったサービスと、止まらなかったサービス
2025年10月20日、Amazonのクラウド「AWS」で大規模障害が発生し、
SNSやゲーム、Webアプリが世界中でアクセス不能になりました。
しかしその中で、X(旧Twitter) や YouTube、Google系サービス は
ほとんど影響を受けずに動き続けていました。
実は、XもAWSをまったく使っていないわけではありません。
ただし、AWS“だけ”に依存していなかった のです。
Xは自社サーバーや他社クラウドも組み合わせることで、
障害が起きてもサービスが止まらないようにしていました。
ここから見えてくるのが、現代のITに欠かせないキーワード――
「リスク分散」です。
☁️ AWSを使っている=止まるとは限らない
AWS(Amazon Web Services)は、
世界中の企業が使うクラウドの代表格。
多くのアプリやサービスがAWSの上で動いています。
ただし、今回の障害は アメリカ東部のUS-EAST-1リージョン という
一部の地域サーバーで発生したものでした。
つまり、同じAWSを使っていても、
- 利用している「地域(リージョン)」
- 仕組みの作り方(分散・冗長化の有無)
によって、影響の度合いは大きく変わるのです。
🧩 X(旧Twitter)が強かった理由
XもAWSのサービスを一部で利用しています。
しかし、全システムをAWSに置いているわけではありません。
- 🌐 自社のデータセンター(オンプレミス)
- ☁️ 他のクラウドサービス(Google Cloudや独自サーバーなど)
- 🔁 複数リージョンに分散したAWS構成
これらを組み合わせた「ハイブリッド構成」を採用しています。
そのため、仮にAWSの一部で障害が起きても、
他の拠点やクラウドが動いていれば、サービス全体は止まりません。
これが、Xが「AWSを使っているのに影響を受けなかった」理由です。
🔄 リスク分散とは何か?
リスク分散(リダンダンシー)とは、
「どこか1つが止まっても、他が動いてサービスを維持できる仕組み」のこと。
ITシステムでは、次のような分散方法が一般的です。
① マルチクラウド構成
AWS・Google Cloud・Microsoft Azureなど、複数のクラウドを組み合わせて使う。
→ どれか1つが障害を起こしても、残りが動く。
② 複数リージョン(地域)への分散
同じAWS内でも、東京・大阪・海外など複数地域にデータを配置。
→ 地域的な障害でもサービス全体は止まらない。
③ キャッシュ・バックアップ・フェイルオーバー
データを一時保存(キャッシュ)したり、
自動的に他サーバーへ切り替える仕組みを用意しておく。
こうした“もしも”への備えが、
大きなサービスを止めないための鍵になります。
🎓 学生にとっての学び:「依存しすぎない設計」
IT業界を目指す学生にとって、
今回のAWS障害とXの対応は、とても実践的な教訓です。
「止まらない仕組み」を考えることもエンジニアの仕事。
どんなに良いプログラムを書いても、
サーバーが止まればサービスは動きません。
リスク分散の考え方は、
ITだけでなく、仕事や人生の考え方 にも通じます。
ひとつに頼りすぎない。
いつでも“別の選択肢”を持っておく。
この考え方が、どんな時代でも強いシステムを生みます。
🧠 まとめ:Xの強さは「分散」と「備え」にあった
- XもAWSを使っているが、「一部だけ」で依存を分散していた
- 自社データセンターや他クラウドとのハイブリッド構成が強み
- 一方、AWSの1リージョンに集中していた企業は影響を受けた
- 便利さの裏にはリスクがある。“分散と備え”が安定の鍵



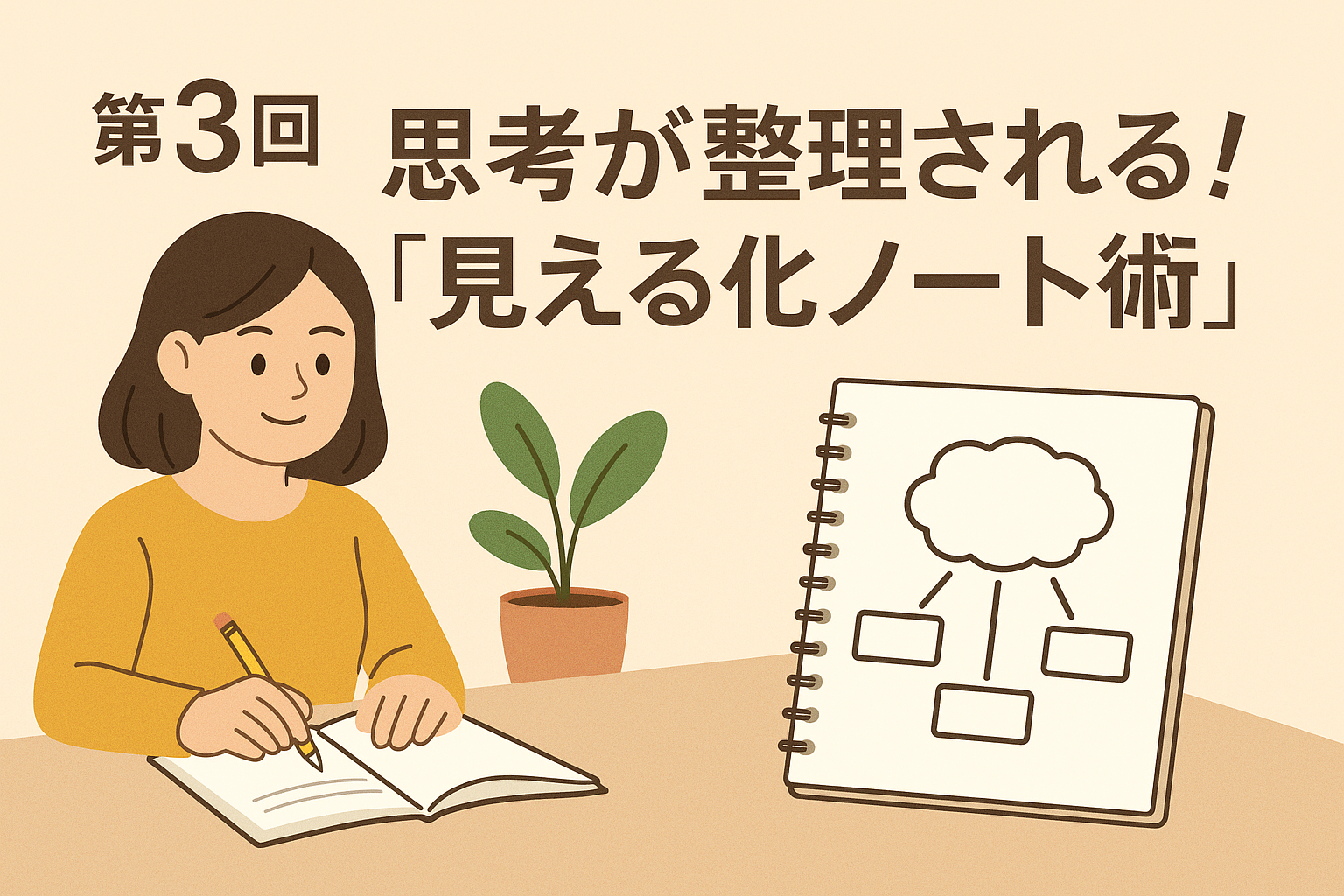
コメント