未来を切り拓くα世代|親が知っておきたい5つの視点|第2回
「世代」という言葉、よく耳にしますよね。
実は日本でつけられてきた世代の呼び方には、ある共通点があるんです。
それは、なぜか“ちょっとネガティブ”な響きを持つこと。
この傾向は長い間続いていて、子どもや若者のイメージに大きな影響を与えてきました。
今回は「なぜ日本の世代呼称がネガティブになりがちなのか?」について考えていきます。
日本の世代呼称が生まれる背景
日本独自の世代の呼び方は、多くの場合「社会の大人世代が若者をどう見ているか」から作られてきました。
その背景には、教育制度の変更や景気の変動など、社会全体の事情があります。
ところが、そうした社会的な要因よりも「今の若者はこう見える」という印象が優先されてしまい、
結果として「ちょっと残念」「期待外れ」というニュアンスを持つ呼び方が広まってきたのです。
海外の呼称との違い
一方で海外では「X世代」「Z世代」「α世代」といったアルファベットによる呼称がよく使われます。
こちらは基本的に「技術の変化」「社会の大きな出来事」といった客観的な出来事をもとにしていて、
呼び方そのものに良い悪いのニュアンスはあまり含まれていません。
つまり、日本の呼称は「大人の感覚や不安」が強く反映されやすいのに対し、
海外の呼称は「社会の変化を区切るラベル」として中立的に使われているのです。
その影響とは?
ネガティブな呼称が広まると、若者自身が「自分たちはそういう世代なんだ」と思い込んでしまうことがあります。
本来は社会が作った背景なのに、あたかもその世代の性格そのもののように受け取られる。
これが一番の問題だといえます。
世代名は「ラベル」でしかないのに、ラベルが子どもたちや若者の可能性を制限してしまう危険性があるのです。
筆者の視点 ― 子どもをラベルで縛らない
私は教育の現場で多くの子どもや学生と関わってきました。
その中で強く感じるのは「同じ世代でも一人ひとりの個性は全く違う」ということです。
ネガティブな呼称は、大人側の不安や不満を投影したものでしかありません。
だからこそ、保護者が子どもを見るときは「世代ラベル」よりも「今この子が何に夢中になっているか」に目を向けることが大切だと思います。
子どもたちは社会が決めたイメージに縛られる必要はありません。
むしろ、その枠を超えていく力を持っているはずです。
次回予告
次回は、今の小学生=α世代にスポットを当てます。
「AI時代に育つ子どもたちは、先の見えない社会の中で“迷走しているように見える”のか?
それとも“未来を切り拓く開拓世代”と捉えるべきなのか?」
保護者の不安と希望を両面から考えていきます。
未来を切り拓くα世代|親が知っておきたい5つの視点(第3回) どうぞお楽しみに。

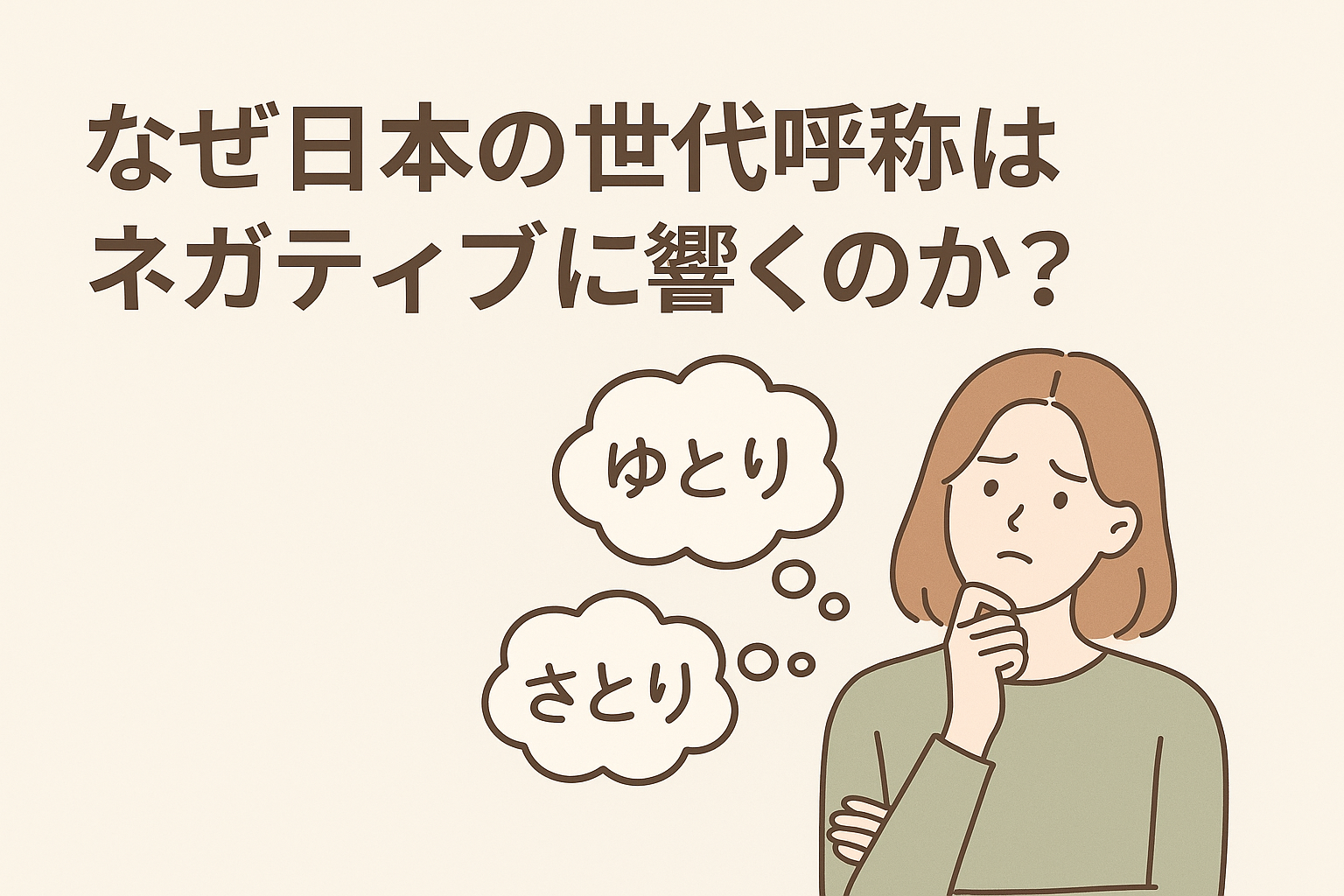
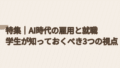
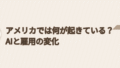
コメント