2026年4月から始まる自転車の青切符制度。違反すれば反則金を科される仕組みですが、「免許も教習もないのにルールを守れと言われても理不尽では?」という声もあります。本記事では、この“理不尽さ”の背景を整理し、なぜ教育より罰則が先に導入されることになったのかを解説します。
🤔 そもそも「理不尽」に感じる理由
- 自転車には自動車のような免許制度や教習システムがない
- ルールは113種類以上あり、一般の人は全てを知らない
- それなのに「守れなければ反則金」という構造
このため「知らないうちに違反してしまう」「教わってないのに罰金を取られる」という不満が生まれやすいのです。
🛠️ なぜ免許制度がないのか?
- 利用者が幅広すぎる
小学生から高齢者までが生活手段として使うため、免許必須にすると社会的コストが大きすぎる。 - 日常の移動手段であること
通学・買い物・通勤など「生活必需品」として扱われるため、免許制にすると不便さが目立つ。 - 免許制導入には膨大な費用がかかる
全国民規模の講習・試験制度を整えるのは現実的ではない。
⚖️ なぜ教育より罰則が先なのか?
- これまで「安全講習」「学校での交通安全教育」「指導警告」が中心だったが、事故抑止効果は限定的だった。
- 特に信号無視やスマホ操作などの重大違反が減らず、死傷事故も多い。
- そこで「教育だけでは事故は防げない → 強制力として罰則を導入」という流れに。
🏫 教育は軽視されているのか?
実際には教育が軽視されているわけではなく、以下のような取り組みが進められています。
- 学校や地域での交通安全教室の拡充
- 自治体や警察による啓発動画や教材の配布
- オンライン教材(○×クイズ形式など)の活用事例も登場
つまり「教育だけ」では限界があるため、教育+罰則の二本立てで安全を確保する方向に進んでいるのです。
📌 まとめ
- 自転車青切符が「理不尽」と言われるのは、免許や教習がないのに罰則だけがあるため
- 免許制度がないのは社会的コストや利便性の問題が大きい
- 教育はすでに行われているが効果は限定的だったため、罰則が導入された
- 今後は「教育+罰則」の両輪で事故防止を目指す
🔜 次回の記事では、**「親子でできる自転車教育|子どもにどう伝える?」**をテーマに、家庭での声かけや工夫をまとめます。


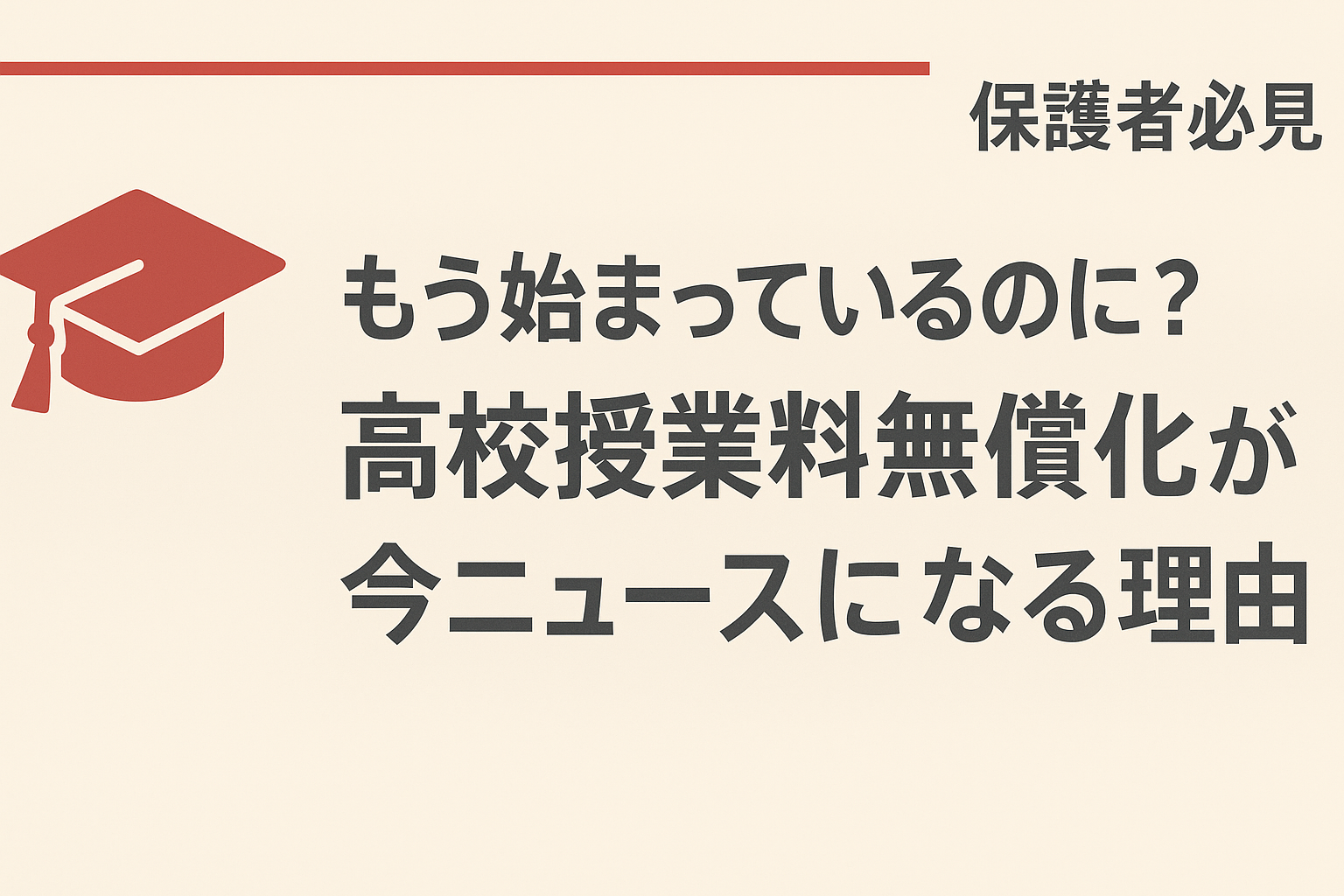
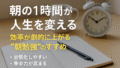
コメント