❓「とりあえず禁止」が子どもを守る?本当にそうでしょうか
最近、学校や家庭で「ChatGPTなどの生成AIは使わせない方がいい」というルールや声を聞くことが増えてきました。
子どもを守るため、学力を保つため、ズルを防ぐため……その理由はさまざまです。
でも、“禁止すること=安心”という考え方には、落とし穴もあります。
この記事では、「AI禁止ルール」の本当の意味と、保護者ができるサポートについて考えてみましょう。
✅よくある「AI禁止ルール」が生まれる背景
学校や家庭で「ChatGPT禁止」と言われる場面は、主に以下のような場面です:
- 宿題で丸写しされてしまうのでは?という心配
- AIが出した答えが正しいかわからず混乱する
- 考える力が育たなくなるという不安
つまり、「禁止ルール」は、AIの活用方法がまだ十分に理解されていないことから生まれているケースが多いのです。
⚠️禁止がもたらす3つのリスク
①「こっそり使う子」を生む
禁止されても、スマホやパソコンを使える環境があれば、子どもは隠れて使う可能性があります。
すると、
- 正直に使うことを学べない
- AIと自分の区別をつけずに混ぜてしまう
- わからないことを放置する
といった“ズルではないけれど危うい使い方”が増えてしまいます。
②「使い方を学ぶ機会」を失う
AIを使うには、「この情報は正しい?」「これは自分の考え?」といった判断力が必要です。
完全に使わせないと、その判断力を身につけるチャンスがなくなります。
子どもたちは、“使いながら学ぶ”ことで力をつけていくものです。
③「正しい使い方の対話」ができなくなる
親や先生がAIを“よく知らないまま禁止”してしまうと、子どもとの間に「知識の壁」が生まれます。
本当は大人も一緒に学びながら、「使うとき、どんなことに気をつければいい?」という会話をしていくことが大切です。
🧭保護者として考えたいこと
💡1. ルールよりも「目的」を話す
「使っちゃダメ」ではなく、「なぜ使わない方がいいのか」を共有すること。
その目的が明確であれば、子どもも納得しやすく、ルールの意味も伝わります。
💡2. 「今はどういう使い方をしている?」と聞いてみる
AIを使っている子どもに対して、頭ごなしに禁止するのではなく、現状を聞くことが第一歩です。
- 「どんなことに使ってる?」
- 「わかりにくいところはあった?」
こうした会話から、一緒にルールを考える姿勢が育ちます。
💡3. 保護者自身も“少し使ってみる”
ChatGPTなどを1度でも使ってみると、「こんなに正確?」「意外と大雑把?」など気づきがあります。
使うことで、禁止か解禁かではなく“どう向き合うか”の視点に変わっていきます。
📝まとめ|安心を求めるなら、「禁止」より「理解」を
AI時代の学びにおいて、子どもを守る一番の方法は、正しい知識と使い方を共有することです。
禁止が必要な場面もありますが、それは一時的なもの。
大切なのは、「いつか使うときのために、今なにを教えておくか」です。
安心=禁止、ではありません。
安心=対話と理解の積み重ねです。
📢次回予告
👉 「世界ではこうしている!家庭でもできるAIとの付き合い方ガイド」
次回は、海外の事例をもとに、家庭でAIとどのように向き合えばよいかを紹介します。

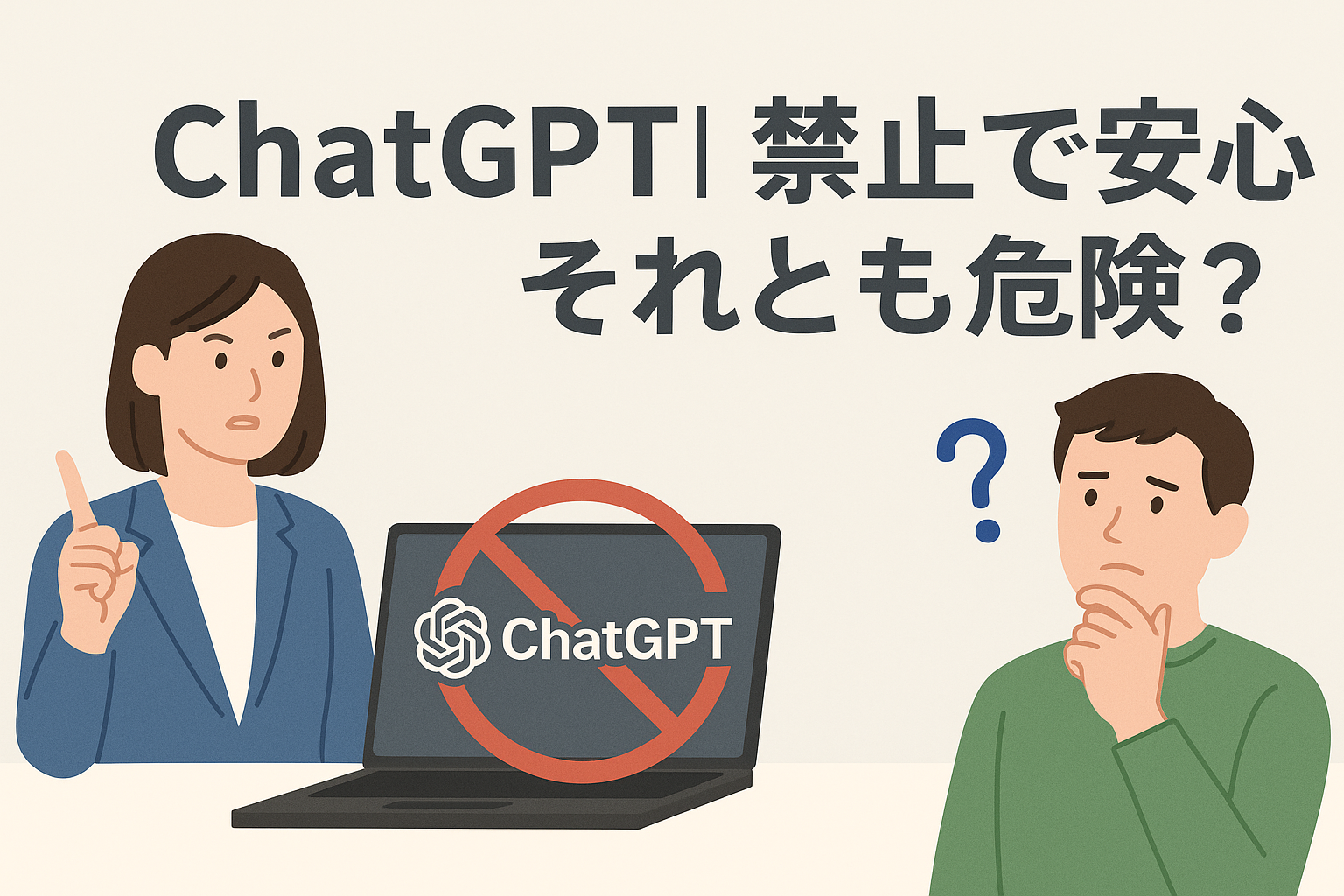


コメント