「プログラミング=勉強」と思わせないのがコツ!
プログラミングって、実は遊びと学びの中間にあるもの。
でも、親が「さあ勉強よ!」と声をかけると、子どものやる気はガクッと下がります。
特にこんな場面、ありませんか?
- 「ほら、プログラミングの宿題やりなさい」
- 「あの教材、ちゃんと最後までやったの?」
- 「ゲーム作るんでしょ?パソコン開いたら?」
ちょっと待って。その言い方、子どもの心を遠ざけているかもしれません。
🎮 プログラミング=“学習”ではなく“遊び+好奇心”
ScratchやPlayCode、ロボット教材など、今のプログラミングは遊び感覚で始められるものが多いです。
実際に子どもたちは…
- 「動いた!」が嬉しい
- 「自分で作れた!」が誇らしい
- 「もっと面白くしたい!」と試行錯誤する
これはまさに、自発的な学びの理想形。
でも、“親のひと言”がそれを止めてしまうこともあるのです。
✅ NGになりがちな声かけ3つ
| NGパターン | 理由 |
|---|---|
| 「勉強しなさい!」 | 勉強=苦しいもの、というイメージを連想させてしまう |
| 「早くやって終わらせなさい」 | プログラミングは“正解のない試行錯誤”が魅力。急かすと創造性が止まる |
| 「これで成績上がるの?」 | 楽しさや興味より“成果”が優先されてしまい、意欲が下がる |
✅ やる気が伸びる声かけ3つ(具体例つき)
| 声かけ | 効果 |
|---|---|
| 「それ、どうやって動いてるの?見せて!」 | 子どもが自分の作ったものを説明=理解が深まる |
| 「前よりスムーズになってない?」 | 成長のプロセスに気づいてあげると、自信につながる |
| 「それ、他の人に見せたらびっくりするね!」 | 作ったものを“認められる”と次への意欲が湧く |
🧠 親が意識しておきたい3つのポイント
- 「正解がないこと」に慣れさせるチャンス
→ 試行錯誤やトライ&エラーがプログラミングの醍醐味! - 一緒に“遊ぶ”感覚で接する
→ 最初は親も一緒にプレイ感覚で画面を見るのが効果的 - 目的は「自分で動かす体験を通じて考える力を育てる」こと
→ 成績や検定より、まずは“考える力”に価値を置く
👨👩👧 実際にあった事例
💬 小5男子の保護者:「最初は遊び感覚でやっていたのに、『いつやるの?』と毎回聞いていたら、だんだんパソコンを開かなくなって…。でも『見せて』に変えたら、また自分からやるようになりました!」
💬 中1女子の保護者:「“宿題としてのプログラミング”を毎回声かけしていたら、やる気が下がってしまった。でも、自由研究としてScratch作品を褒めたら、次の作品を自分から作り始めました!」
📎 関連記事もチェック!
まとめ|「ほめる・見せてもらう・待つ」が伸ばすカギ
子どもにとってプログラミングは、「わかる楽しさ」と「動く嬉しさ」が詰まった体験です。
だからこそ、“勉強っぽくしない”親の声かけが習慣づけのカギになります。
「させる」のではなく、「一緒に見守る」。
そんなスタンスが、未来のITスキルを育てる最初の一歩になります。


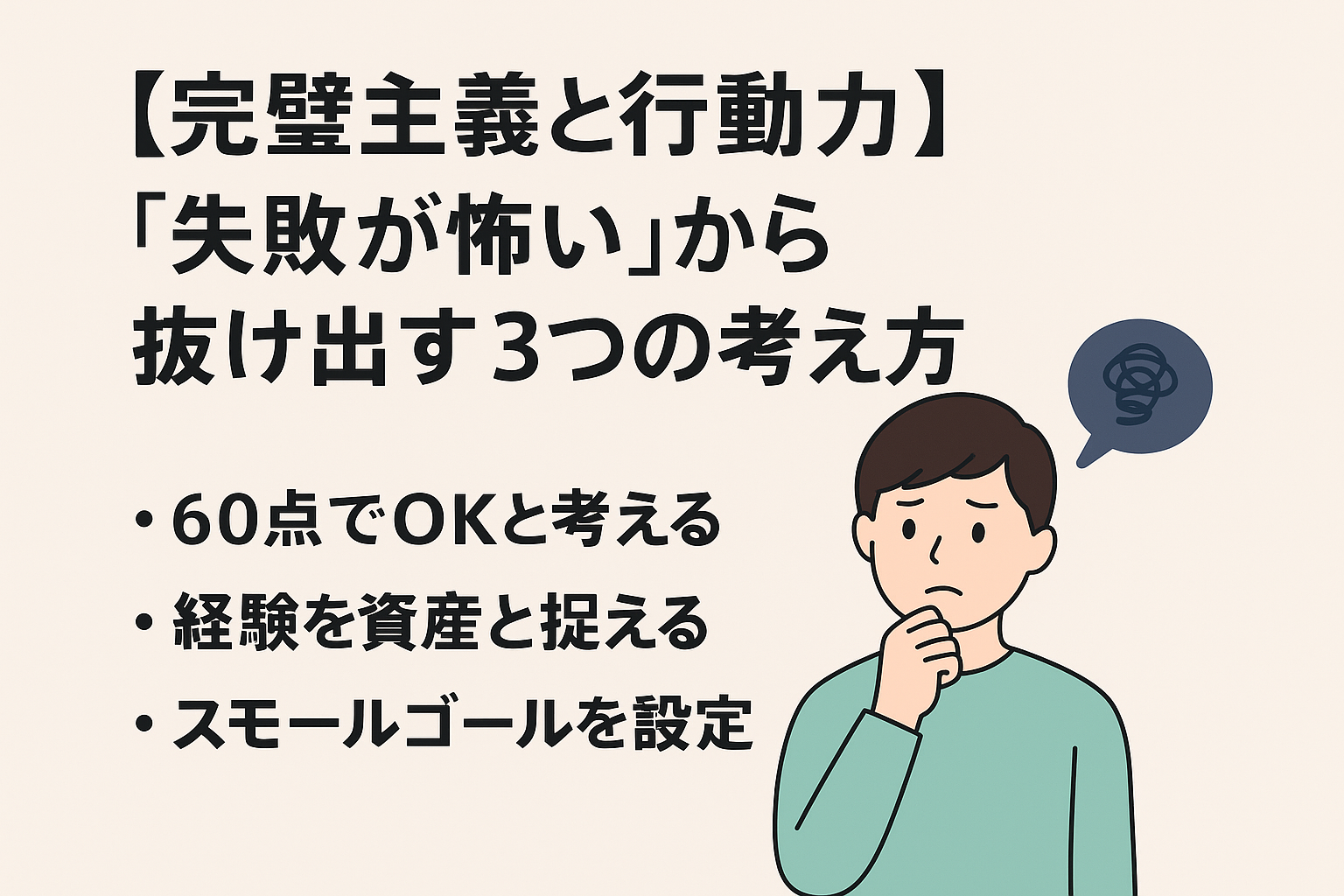
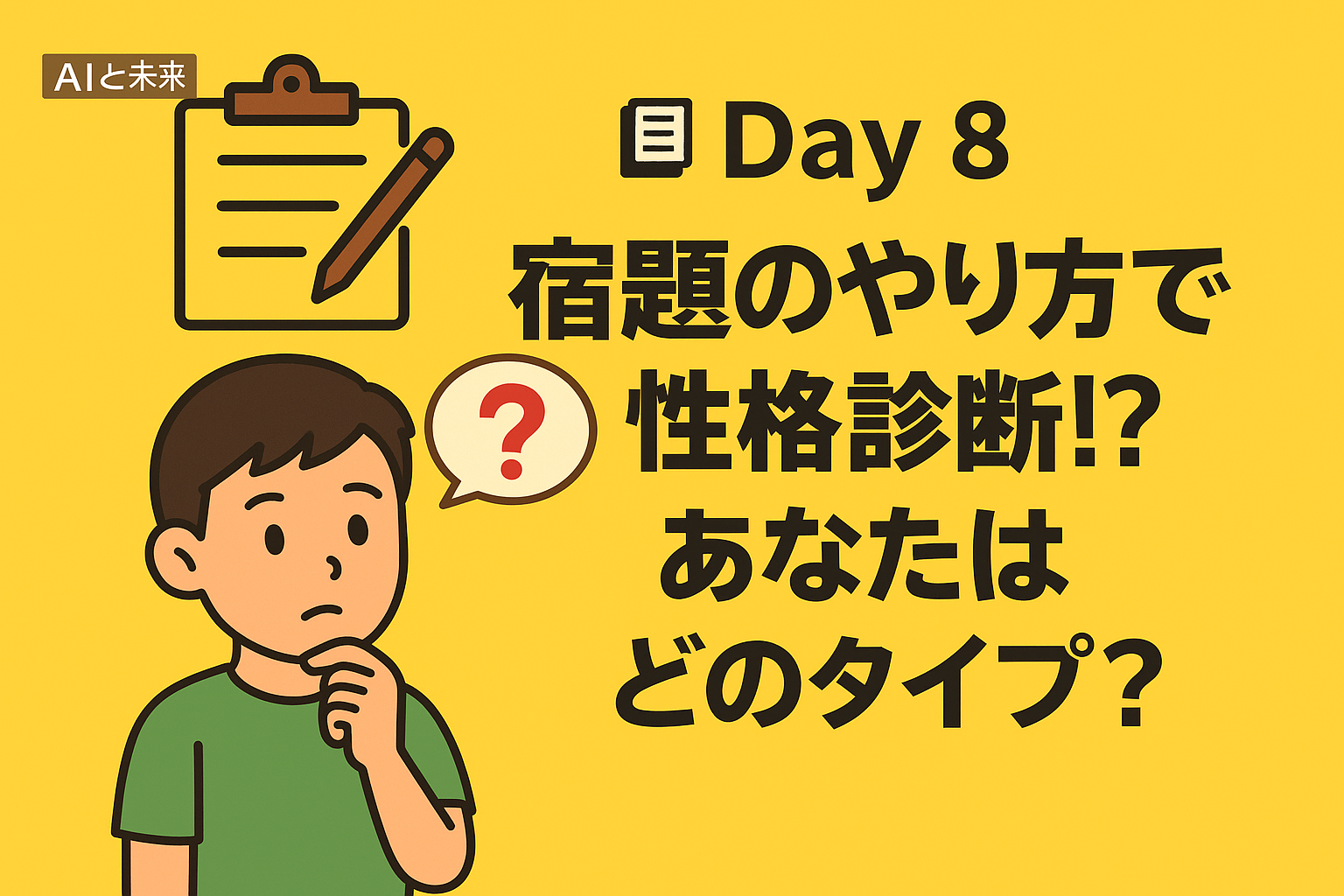
コメント