AI時代の必須スキル|言語化力 実践編 第1回
はじめに
「AI時代の必須スキル|言語化力」シリーズの基礎編(全5回)では、言語化力の大切さやAIとの関わりを解説してきました。
この“実践編”では、家庭で子どもの言語化力を育てるための具体的な方法を、保護者の方に向けて紹介していきます。
「うちの子、気持ちをうまく言葉にできない」
「ゲームやスマホばかりで、会話が減ってきている気がする」
そんな悩みを持つ方にこそ役立つ、日常で実践できる工夫をまとめました。
言語化力は家庭で育つ
言語化力は、特別な教材ではなく 日々のやりとり の中で自然に育ちます。
たとえば「今日どうだった?」と聞く場面で、
- 「何が一番楽しかった?」
- 「どうしてそう思った?」
- 「やってみてどんな気持ちになった?」
と一歩踏み込んだ問いかけをすれば、子どもは「考えを整理して言葉にする」練習ができます。
日常会話を“学び”に変える
- 買い物帰りに:「今日のお買い物で一番面白かったものは?」
- テレビや動画を見たあとに:「どうしてそのキャラが好きなの?」
- 食卓で:「今日一番うれしかったことは?」
正解を求める必要はなく、子どもが自分の言葉で表現すること自体が大切です。家庭のちょっとした会話が、言語化力の練習場になります。
遊びを通じて育てる
- 絵本の読み聞かせ:「このあとどうなると思う?」と予想させる
- しりとりや連想ゲーム:言葉を使った遊びで想像力を広げる
- お絵かき説明ゲーム:描いた絵を自分の言葉で説明する
「考える → 言葉にする」の流れを遊びに組み込むと、楽しみながら自然に力が伸びます。
デジタルを味方にする
AIやアプリを使うときは、
- “答えを写す”のではなく“自分の言葉に直す”
- 保護者が一緒に利用して安全を確かめる
- AIを「会話の相手」として活用する
といったルールを意識しましょう。
最近ではChatGPTに保護者管理機能が導入予定(2025年10月)と発表され、子どもも安心して活用できる環境が整いつつあります。
感情を言葉にする習慣
言語化力は、勉強だけでなく 感情の整理 にもつながります。
- 怒ったとき:「何が嫌だったの?」
- 喜んだとき:「どんな気持ちになった?」
- 一行日記でその日の感情を書く
感情を言葉にできる子は、自己理解が深まり、人間関係でも円滑に気持ちを伝えられるようになります。
まとめ
子どもの言語化力を育てる場は、家庭のあちこちにあります。
大切なのは「親が正しい答えを引き出すこと」ではなく、安心して言葉にできる環境をつくること。
親の聞く姿勢とちょっとした問いかけが、子どもの未来につながる力を育てます。
次回予告
👉 「子どもが話したくなる!親の聞き方・問いかけのコツ」
子どもが自然に話したくなるのは、親の聞き方しだい。次回は「開かれた質問」と「寄り添うリアクション」の具体例を紹介します。


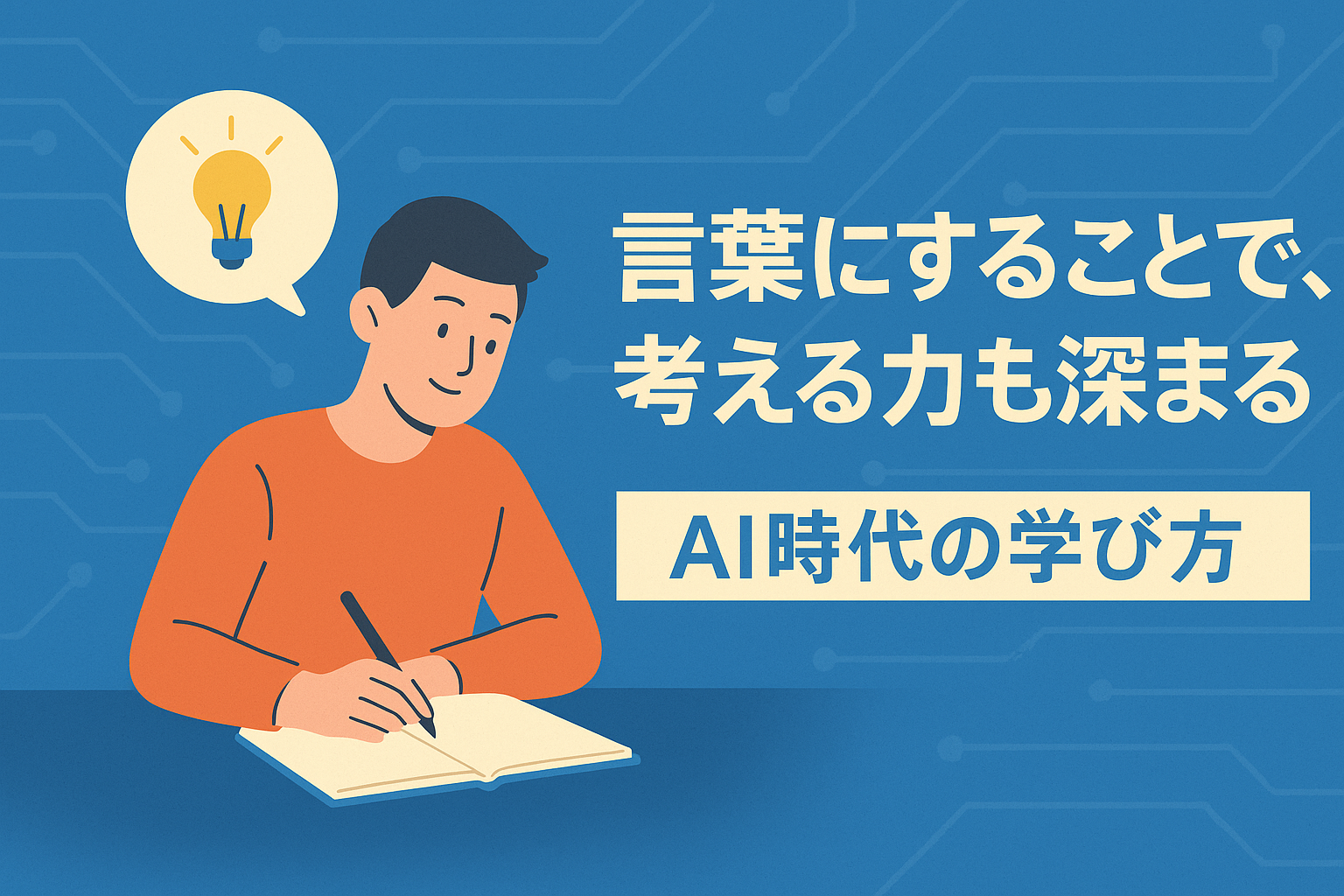

コメント