1. はじめに
高校授業料の無償化は、2025年4月からすでに始まっています。
中学生の家庭にとっては“直撃世代”でしたが、**小学生の家庭にとっては「これから受ける世代」**にあたります。
制度の恩恵は受けられる見込みですが、タイミング的に「制度が定着・修正された後」に進学することになるため、考え方は少し異なります。
本記事では、小学生の保護者が今から意識しておくべき教育費戦略について整理します。
2. 制度は「変化の途中」であることを理解する
中学生世代は“制度が始まった直後”に進学します。
一方、小学生世代は 制度が定着し、必要に応じて修正された後 に高校進学する層です。
- 無償化の対象範囲が広がる可能性
- 逆に、財源問題で条件が見直されるリスク
- 公立・私立の人気バランスの変化
👉 つまり、小学生世代の保護者は「いまの制度がそのまま10年後も続く」とは限らないと理解しておく必要があります。
3. 大学・専門学校への備えを優先
高校授業料はゼロになる可能性が高いとしても、その後に控える大学・専門学校の費用は依然として大きな負担です。
- 国立大学:年間約82万円
- 私立大学(文系):年間約120〜130万円
- 私立大学(理系):年間150〜180万円
- 専門学校:年間約100万円
👉 小学生の家庭は「高校無償化で浮いた分を大学資金に回す」という発想を持つことが重要です。
4. 小学生から始まる“外部教育費”の格差
すでに小学生の段階から、習い事や塾によって教育費格差は広がっています。
- 公立小学校+習い事なし → 最低限の費用で済む
- 習い事(英語・ピアノ・スポーツ)→ 月1〜3万円
- 中学受験を視野に入れる家庭 → 年間100万円以上
無償化は「授業料」という一部の負担を減らすだけで、実際には 習い事や塾代が家計に占める割合が大きくなる のです。
5. 制度に依存しない資金計画を
小学生の家庭にとって大切なのは、制度に安心して教育費の備えを怠ることではありません。
- もし制度が縮小・廃止されたら?
- 想定外の支出(私立進学や留学など)が必要になったら?
そんな“もしも”に備え、制度がなくてもやっていける教育費計画を立てておくことが安心につながります。
6. 保護者が今からできること
- 教育費シミュレーションを作る
高校・大学・習い事すべてを含めた長期的な見積もりを立てる。 - 積立・学資保険・NISAの活用
浮いた分を“貯蓄や投資”に回す発想を持つ。 - 学校外教育の選択を見直す
習い事や塾にかける費用が将来の進学にどうつながるかを見極める。 - 情報リテラシーを養う
制度の変化や教育政策に敏感になり、将来の変動に備える。
7. まとめ
- 小学生の家庭は「制度が定着・修正された後」に進学する世代。
- 高校無償化で安心するより、大学・専門学校資金の備えが重要。
- 習い事や塾代など“外部教育費”は小学生からすでに始まっている。
- 制度に依存せず、長期的な教育費戦略を持つことが大切。
8. 保護者へのメッセージ
無償化は心強い制度ですが、将来の教育費をゼロにしてくれるわけではありません。
小学生の家庭こそ、**「制度があるから安心」ではなく「制度がなくても大丈夫」**という備えを持つことが必要です。
✍️ 次回(第7記事・最終回)では、**「平等は実現できても公平は遠い? 高校授業料無償化と教育格差の行方」**をテーマに、制度が社会全体にどんな影響を与えるのかを解説します。

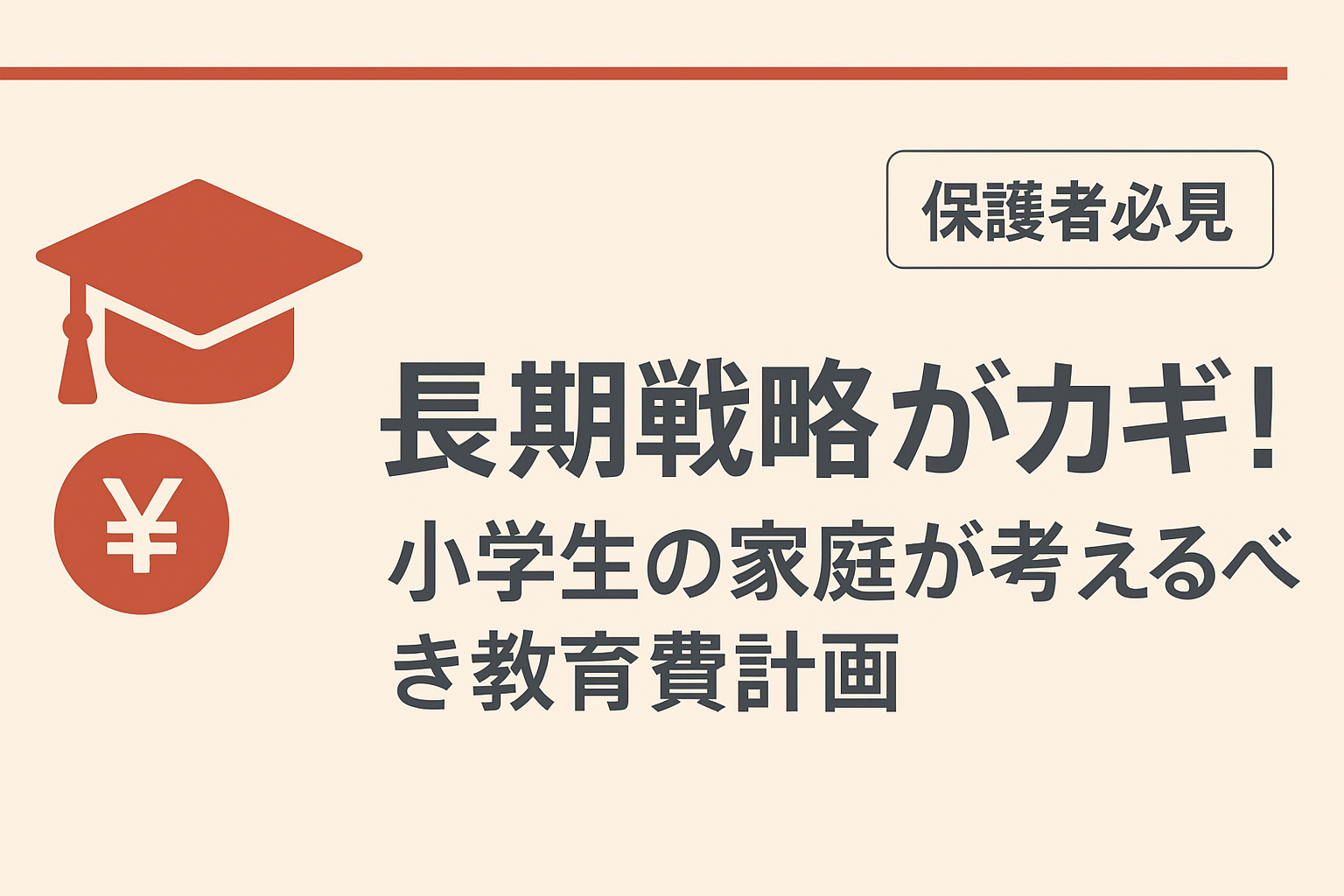

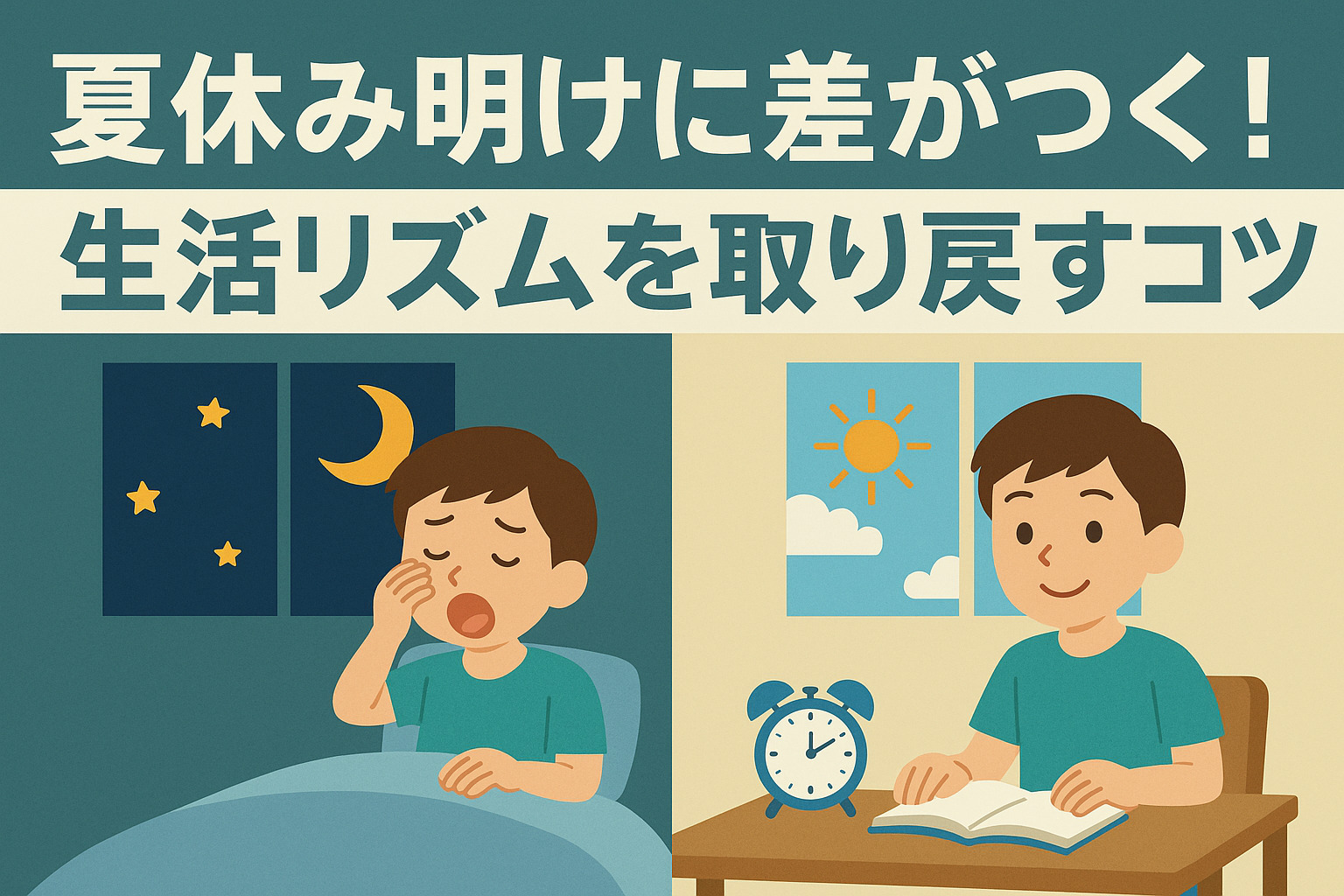
コメント