はじめに
「ノートを書いているのに、復習するときに役立っていない」
「きれいにまとめることが目的になってしまって、結局頭に残らない」
そんな悩みを抱えている人は少なくありません。
ノートは「きれいに写すため」ではなく、思考を整理して理解を深めるためのツールです。
今回は、勉強内容を“見える化”することで考えが整理されるノート術を紹介します。
なぜ「見える化」が大切なのか
人間の脳は、言葉だけで処理するよりも、図や表に整理された情報の方が理解しやすい性質があります。
また、「何がわかっていて、何がわかっていないか」を目で確認できると、効率的に復習することができます。
つまり、ノートを「見える化」することで、ただのメモが 思考を整理する地図 になるのです。
二分割ノート法 ― 予測と答え合わせを整理する
先読み読書や授業前の予習で立てた「予測」と、実際に学んだ「答え」を整理する方法です。
- 左ページ:予測・疑問
「この範囲では〇〇が出そう」「この公式はどう使うのだろう?」と事前に書く。 - 右ページ:答え・学び
授業や読書の後に「実際に出たのは△△」「公式はこう使う」とまとめる。
こうすることで、予測と答え合わせの関係が一目でわかり、理解の進み方が“見える化”されます。
図解ノート術 ― 情報をつなげて整理する
文字をびっしり書くよりも、図解することで理解は加速します。
- 矢印でつなぐ
歴史の因果関係(例:産業革命 → 都市化 → 社会問題) - マインドマップ風に広げる
生物の分類や英単語の派生などを枝分かれ形式で整理 - 表で比較する
似ている概念(例:民主主義と独裁主義)を左右に並べて違いを強調
図や表は復習時に「流れ」や「関連性」を一瞬で思い出せるメリットがあります。
色分けノート術 ― 重要度を一目で把握
ノートに色をつけると「何が重要か」がすぐにわかります。
- 赤:テストに直結する重要事項
- 青:理解を深めるための補足
- 緑:自分の疑問や感想
自分なりのルールを決めると、後で見返したときに「ここをまず覚えればいい」という優先順位が明確になります。
実践例:英語長文での“見える化”
英語の長文問題を解くときに、次のようにノートを作ると効果的です。
- 左に「この段落は〇〇についてだろう」と予測を書く
- 右に「実際は△△が書かれていた」と答えを書く
- わからなかった単語を色で囲み、下に意味を書く
- 段落ごとに矢印で流れをつなぐ
こうすれば、文章全体の構造や自分の理解の弱点が一目でわかるようになります。
「きれいなノート」と「使えるノート」の違い
- きれいなノート
黒板をそのまま写しただけで、見直しても頭に残らない。 - 使えるノート
自分の疑問や考えを残し、理解のプロセスが見える。
勉強の目的は「ノートを仕上げること」ではなく、「理解して覚えること」です。
多少汚くても、自分にとって役立つノートこそが“使えるノート”です。
ノートを習慣化するコツ
- 授業前に「予測欄」を準備しておく
- 授業中は完璧に書こうとせず、キーワードだけ残す
- 授業後に整理しながら“見える化”する
「予測 → 学び → 整理」という流れを繰り返すことで、ノートが勉強の核になります。
まとめ
- ノートは「きれいにまとめる」のではなく「思考を整理する」道具。
- 二分割ノート、図解、色分けで情報を“見える化”できる。
- 復習時に「何が重要で、どこが弱点か」が一目でわかるようになる。
- 使えるノートは、自分の学びのプロセスが残るノート。
次回予告
第4回「忘れる前に思い出す ― 記憶を強化する反復トレーニング」では、エビングハウスの忘却曲線をベースにした復習法を紹介します。
効率的に記憶を定着させる“タイミング”と“方法”を具体的に解説します。

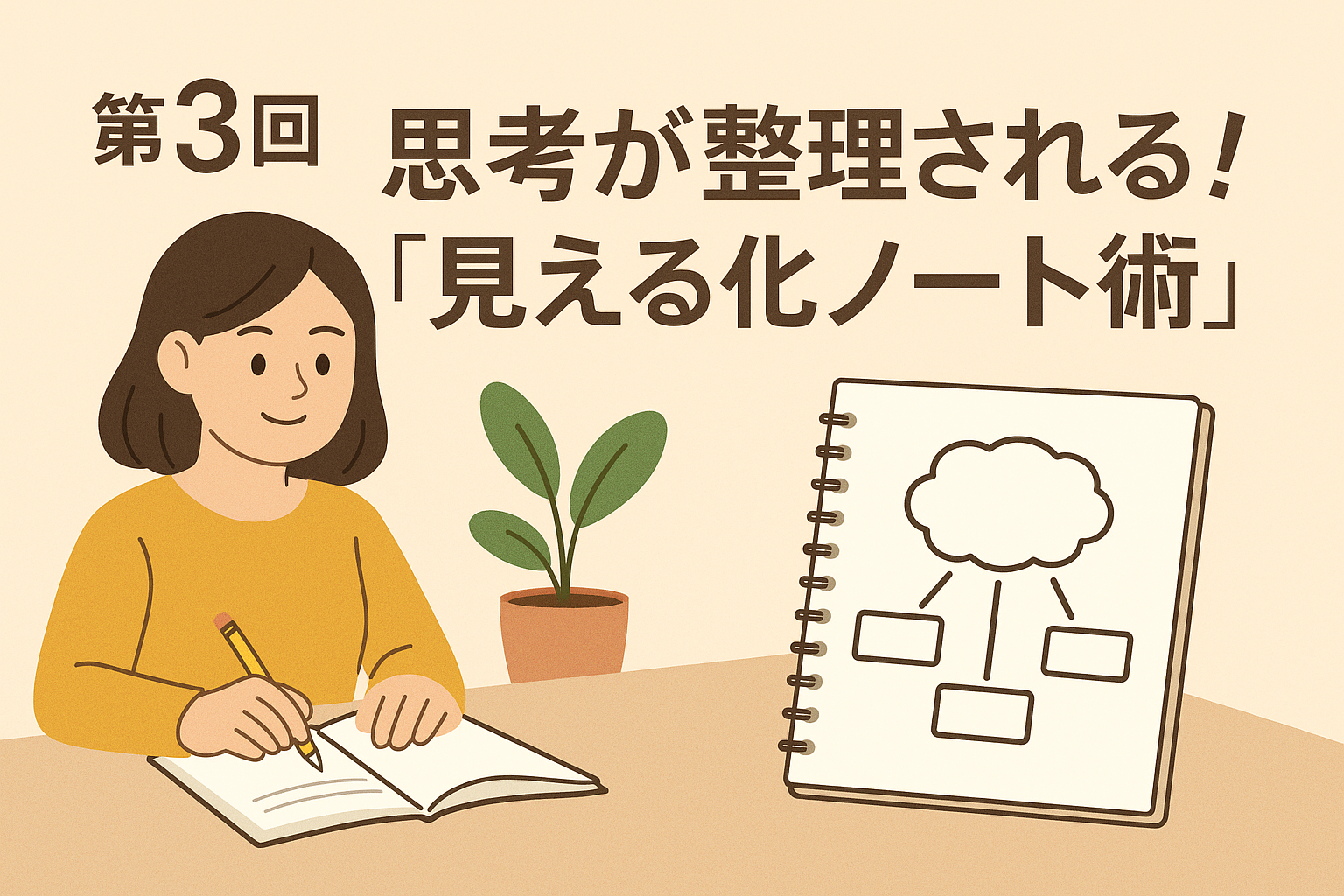

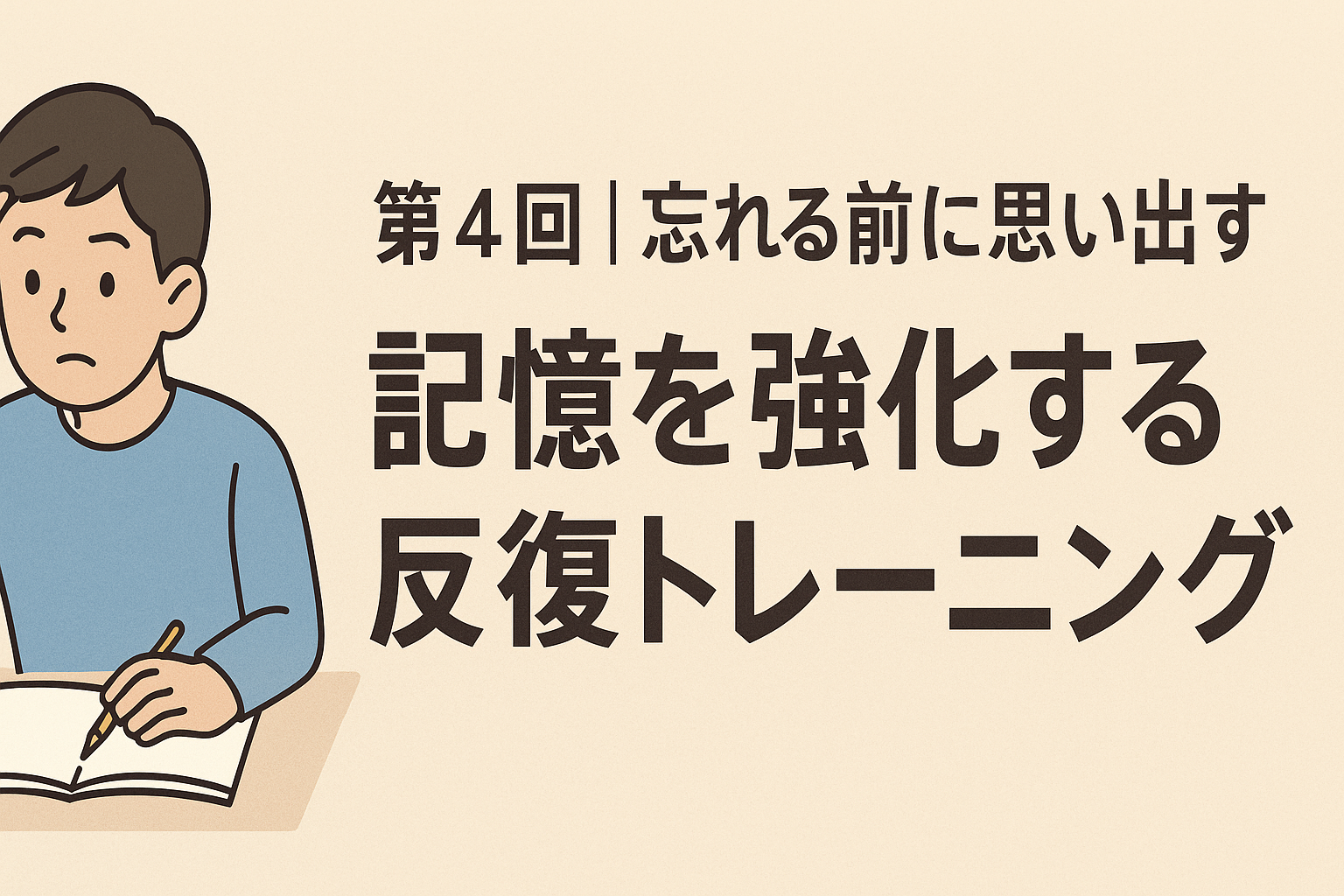
コメント