はじめに
前回の記事では、教科書を「ただ読む」だけでは頭に残らない理由を解説しました。
今回は、その解決策として 「先読み読書」を勉強に応用する方法 を紹介します。
読む前に「この範囲はテストでどんな問題が出そうか?」と予測してから読むことで、理解度と記憶の定着が大きく変わります。
試験に出ると意識すると脳が動く
「テストに出るかもしれない」と思いながら読むと、脳は自然にアンテナを立てます。
結果として、重要な定義や説明に目が向きやすくなり、ただ読むよりも能動的に情報を処理できるのです。
予測と答え合わせの流れ
先読み読書を勉強に取り入れるときは、次の流れを意識してください。
- 目次や小見出しを確認する
例:「この章は光合成についてだから、“植物がエネルギーを作る仕組み”が出そう」 - 試験に出そうな内容を予測する
「定義」「公式」「歴史の年号」など、出題されやすい部分を想像します。 - 本文を読みながら答え合わせをする
「やっぱり定義が強調されている」「ここは思ったより詳しく書かれている」と確認します。 - 理解を整理する
「予測通りだった部分」「意外だった部分」をノートにまとめることで、記憶がさらに強化されます。
勉強効率が上がる理由
- 覚える優先順位がつく:全部を均等に覚えようとせず、重要度の高い部分に集中できる
- 能動的に読む習慣がつく:ただ眺めるのではなく「考えながら読む」読書に変わる
- 記憶が強化される:予測と答え合わせのプロセス自体が、頭に残る学習体験になる
実践の工夫
- 定期テスト対策なら、過去問や先生が強調した部分と照らし合わせて予測する
- 資格試験や大学の専門科目なら、「この単元は実際の問題形式でどう問われるか」をイメージしてから読む
自分なりの「出題予想」を立てることで、学習は受け身ではなく能動的なトレーニングに変わります。
まとめ
- 先読み読書を勉強に応用するには「試験に出そうな部分を予測する」ことが大切。
- 予測と答え合わせの流れを繰り返すことで、理解と記憶が深まる。
- 予測によって勉強の優先順位がつき、効率が大きく上がる。
次回予告
第3回「先読み読書×問題演習 ― 記憶を定着させる最強の組み合わせ」では、予測して読む学習法と、実際の問題演習を組み合わせる方法を紹介します。
読むだけで終わらせず、解くことで知識を確実に身につけるステップを解説します。

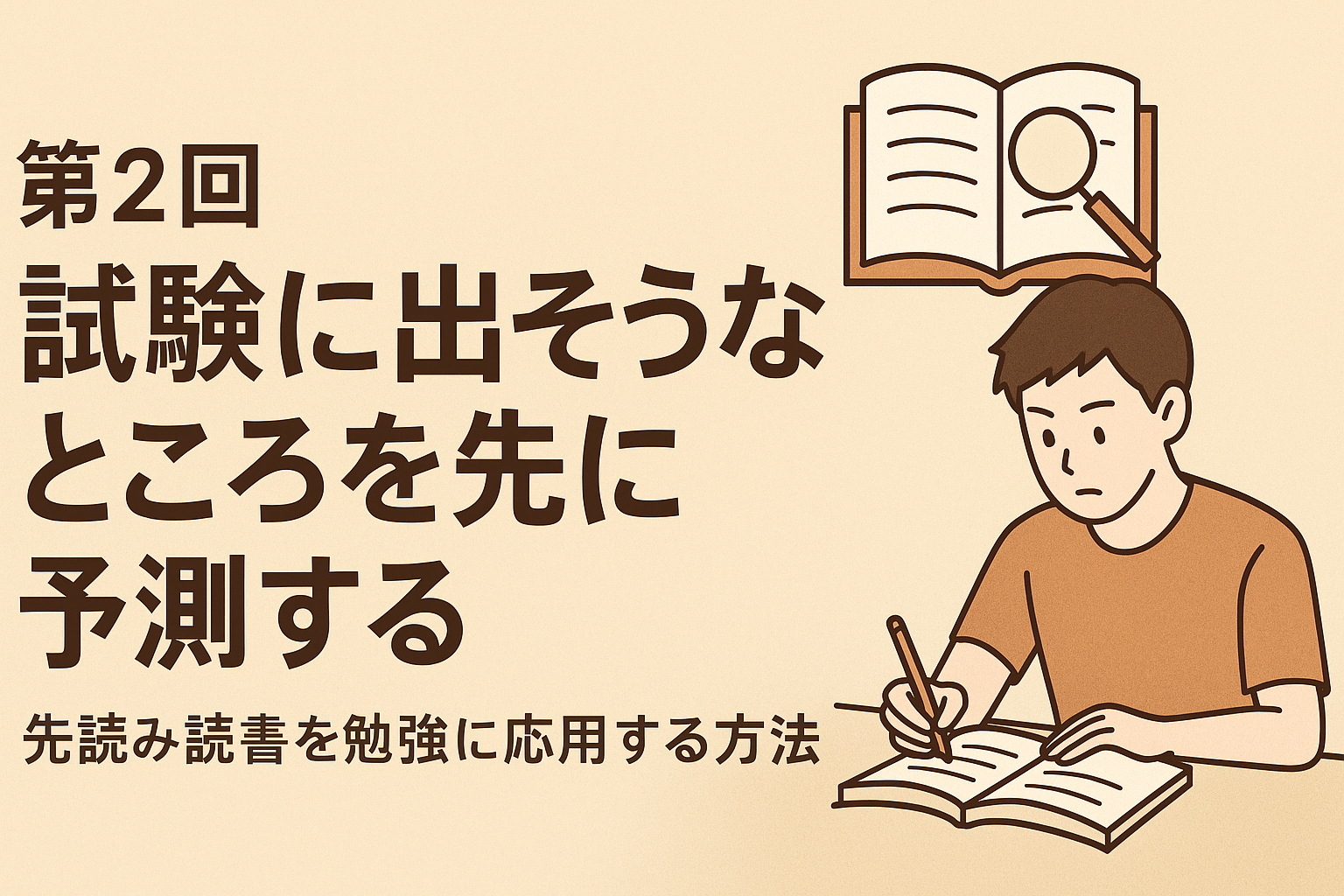
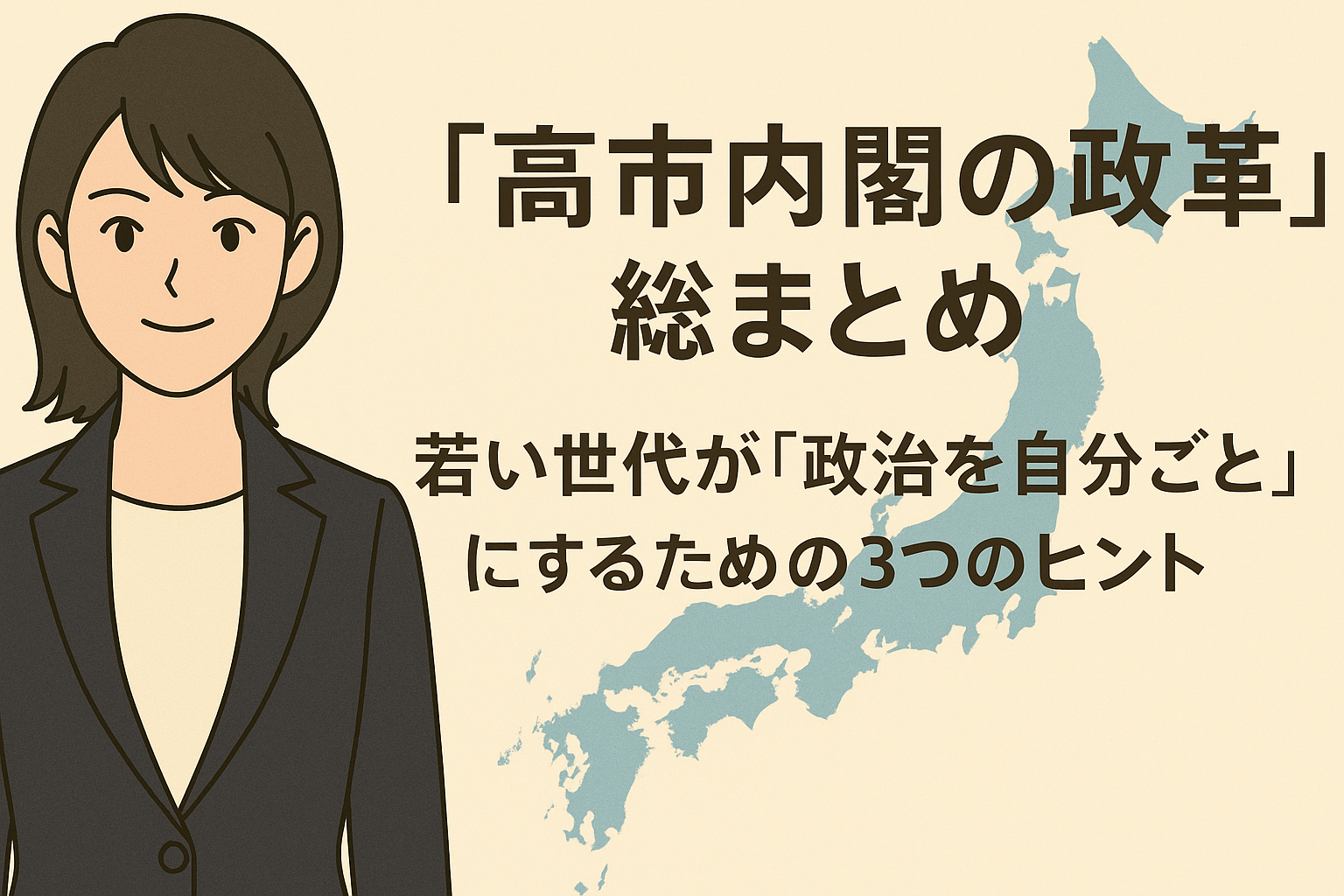
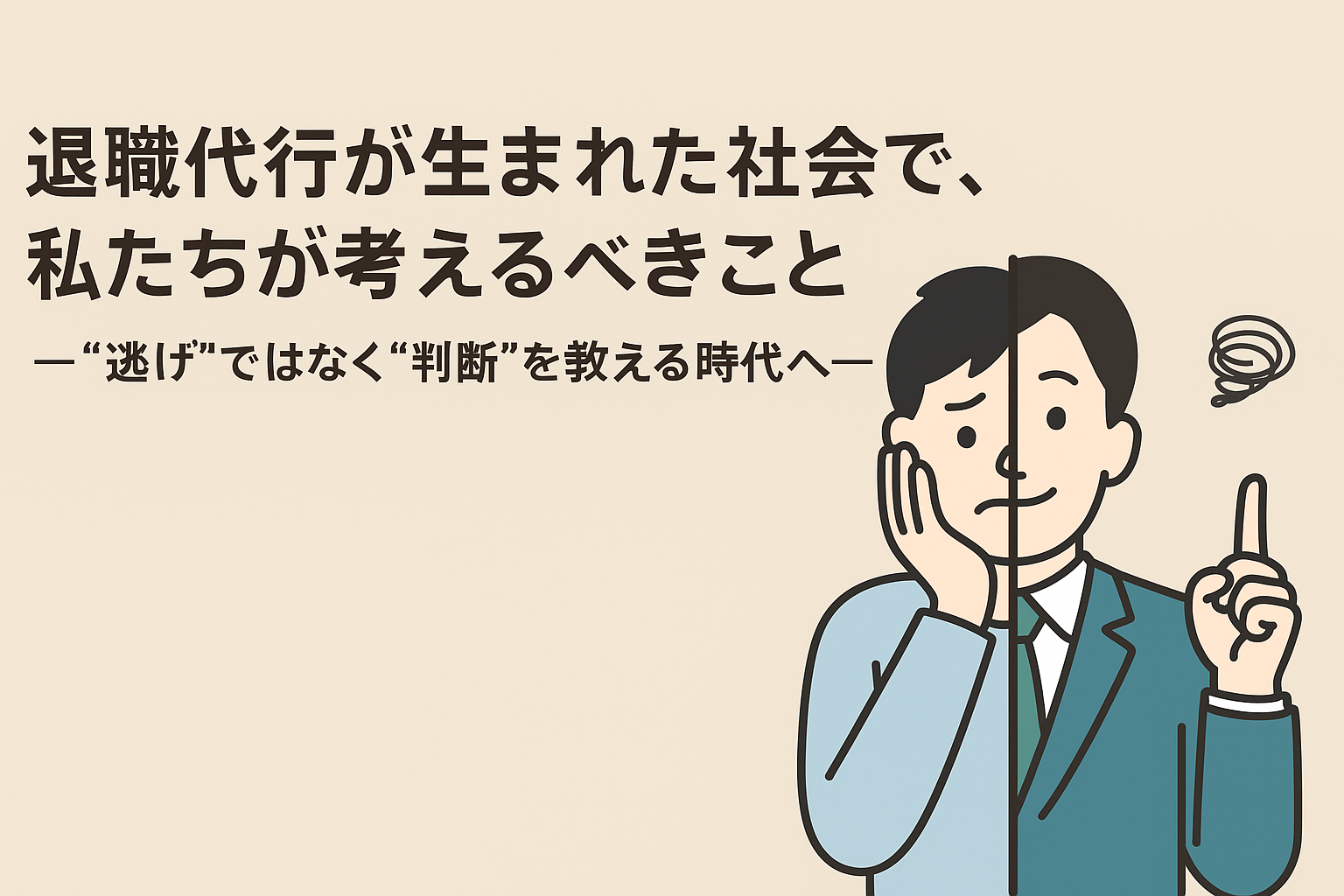
コメント