はじめに
前回の記事では、「ただ読むだけ」では内容が頭に残りにくいことを解説しました。
では、どうすれば理解度と記憶を高められるのでしょうか。
その答えのひとつが、**「先読み読書」**です。
これは、読む前に「この章にはこういうことが書かれているだろう」と 内容を予測する読み方 です。
予測するとアンテナが立つ
予測を立ててから読むと、脳が「その答えを探そう」と働きます。
結果として、重要な情報に自然と目が向くようになり、受け身の読書から 能動的な読書 に変わります。
答え合わせのように理解が深まる
予測と実際の内容を比べることで、
- 「思った通りだった」→ 自信がつく
- 「違っていた」→ 新しい発見として記憶に残る
という流れが生まれます。
これはまさに「答え合わせ」のような学習効果で、理解も記憶も強化されるのです。
関連知識を呼び起こす
予測の段階で「たぶん〇〇についてだろう」と考えると、頭の中に既存の知識が引き出されます。
その状態で読むと、新しい情報が過去の知識と結びつきやすくなり、理解がスムーズに進むのです。
実践のステップ
先読み読書を試すときは、次の流れを意識してください。
- 目次や見出しを確認する
- 「この章は〇〇について書かれていそう」と予測を立てる
- 本文を読みながら「合っていた/違った」を答え合わせする
- 違っていた場合は「なぜ違ったのか?」を考える
このサイクルを回すだけで、読むスピードは変わらなくても 理解度と記憶の定着率が大きく変わります。
まとめ
- 先読み読書は「読む前に予測する」読み方。
- 予測することでアンテナが立ち、重要な情報を捉えやすくなる。
- 答え合わせ感覚で理解が深まり、記憶にも残りやすい。
次回予告
次回、第3回「理解を深める“答え合わせ読書” ― 予測と照らし合わせて学ぶ」では、事前に立てた予測を実際の本文と比べながら読む“答え合わせ読書”を紹介します。
予測が当たった場合と外れた場合、それぞれがどのように学びを深めるのかを具体例を交えて解説します。

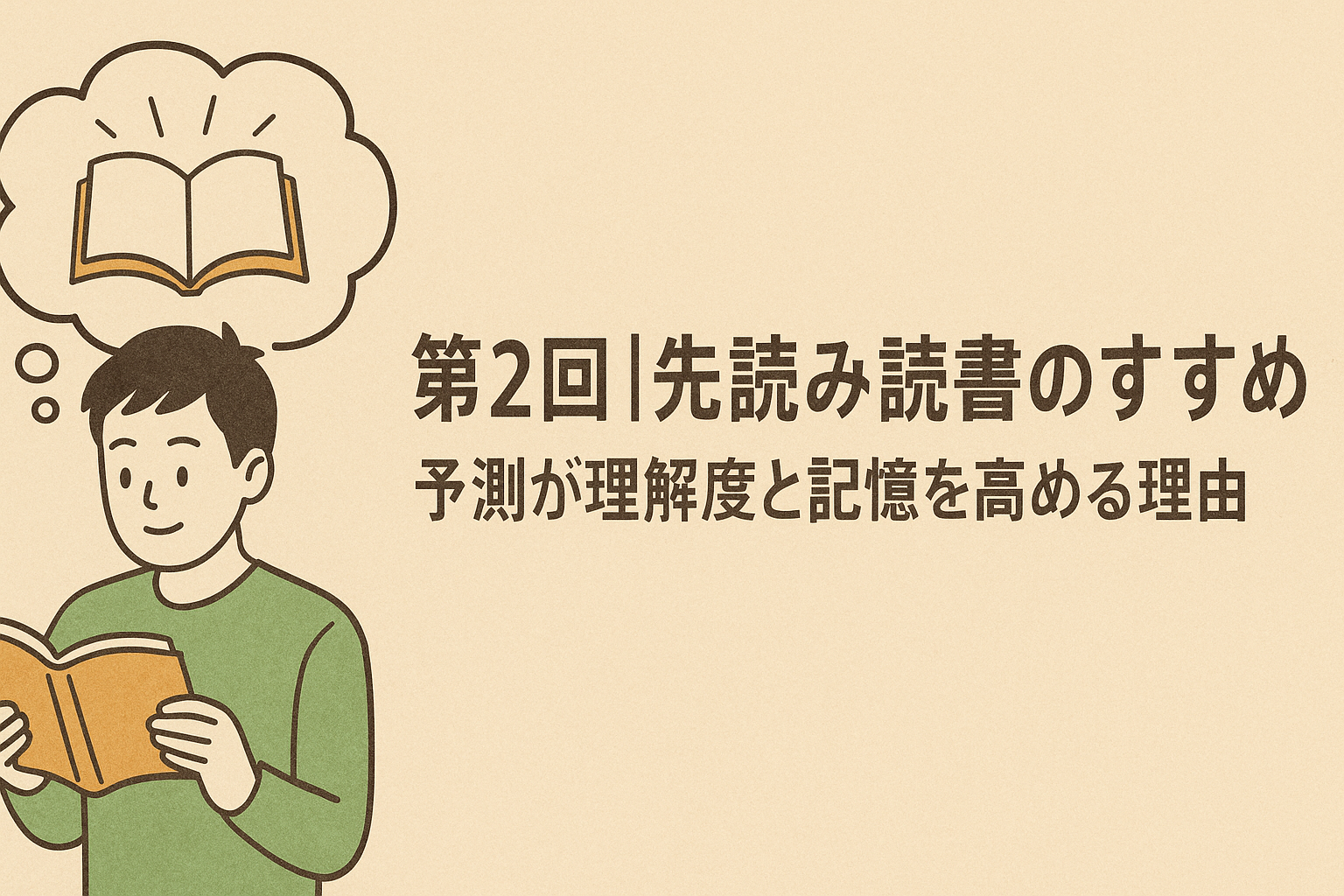
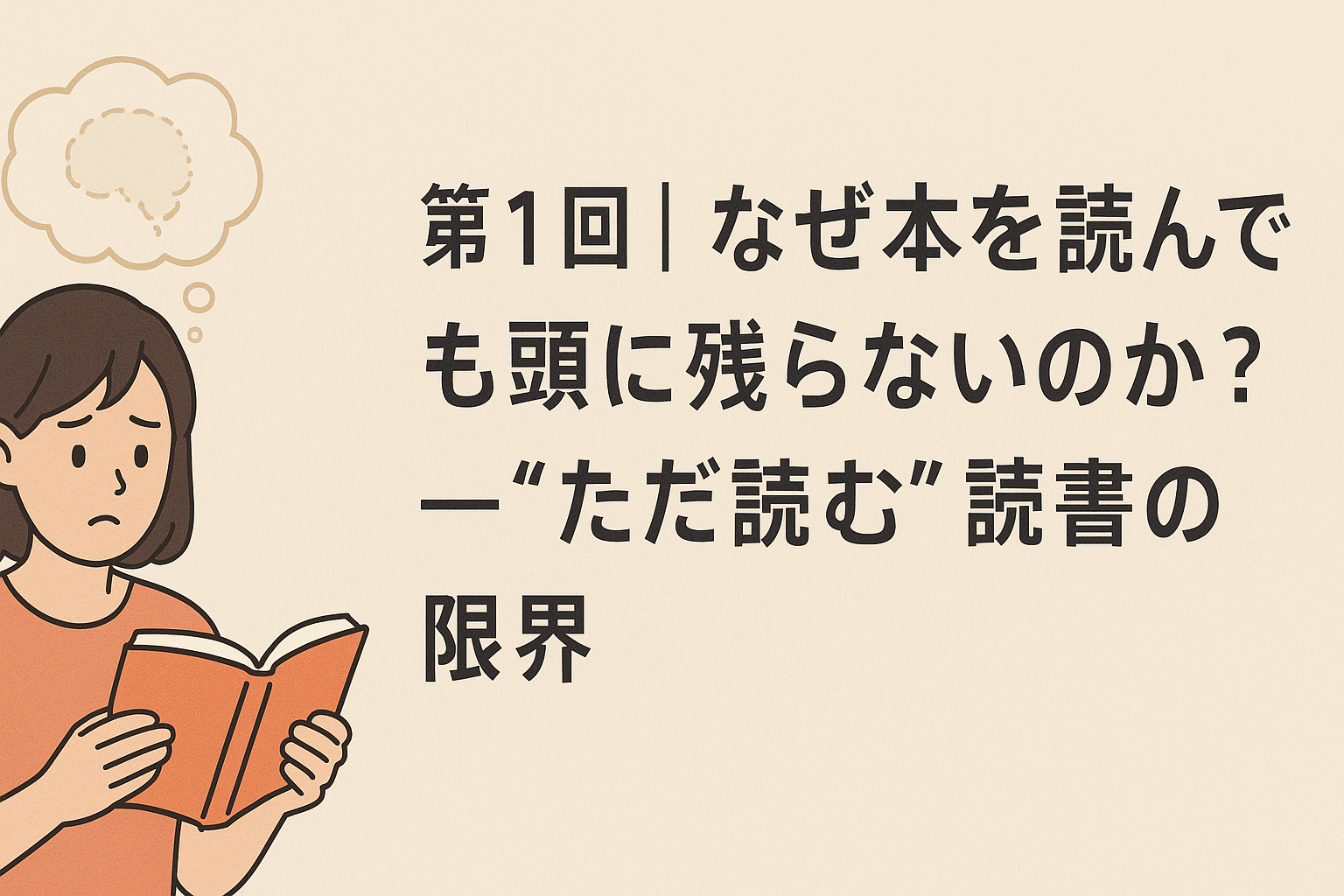
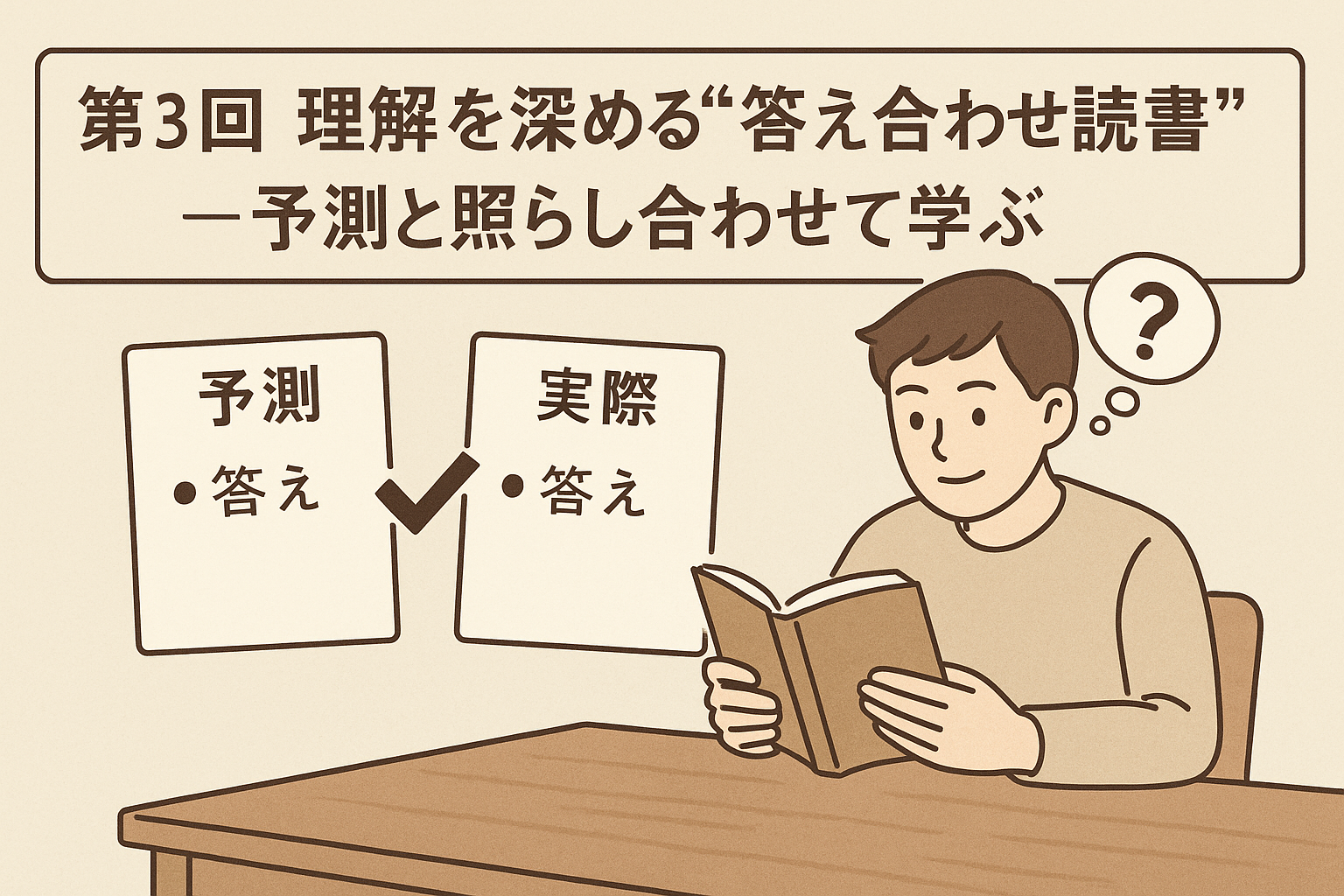
コメント