1. はじめに
2025年4月から高校授業料の無償化が始まりました。
「ありがたい制度」と感じる保護者は多いでしょう。
しかし、この制度の“直撃世代”はまさに 今の中学1〜3年生です。
制度の恩恵を最も強く受ける一方で、制度がもたらす副作用や変化の影響を最も大きく受ける世代でもあります。
本記事では、なぜ中学生の家庭こそ一番考える必要があるのか、その理由を具体的に整理します。
2. 制度のタイミングが重なる世代
- 中学3年生 → 2026年春に高校入学
→ 私立支援が大幅拡充される“本格無償化”を最初に体験する学年。 - 中学2年生 → 2027年春に入学
→ 制度が定着し、人気校集中や倍率変化がより鮮明になる時期。 - 中学1年生 → 2028年春に入学
→ 制度のメリット・デメリットが顕在化した中での進学世代。
つまり「制度が始まったばかり」「定着」「副作用のピーク」という3つの段階を、この3学年が連続して経験することになります。
3. 高校選びにどう影響するのか
制度によって、私立高校の人気が急上昇しています。
「授業料が同じなら、教育環境の良い私立を」という選択がしやすくなったからです。
結果として、
- 公立高校の倍率低下 → 定員割れが増える
- 私立高校の競争激化 → 受験倍率アップ
という二極化が進んでいます。
👉 中学生世代の保護者は「公立か私立か」の選択を、これまで以上にシビアに考える必要があります。
4. “隠れ教育費”の増大
授業料が無償化されても、受験対策や塾代は別問題です。
- 中3〜高1の塾代は月3〜5万円が相場
- 特に私立受験コースは費用がさらに高騰
- 模試や検定、参考書代も積み重なる
「授業料がタダだから安心」と思っていると、むしろ塾代や受験準備費用が家計を圧迫するケースが増えます。
5. 教育格差が広がるリスク
制度は「平等」を実現しても、「公平」までは保証しません。
- 塾や予備校に通わせられる家庭 → 受験に有利
- 通わせられない家庭 → 選択肢が狭まる
結果として、家庭の教育リソースによる格差が広がる可能性が高いのです。
これはまさに中学生世代で最初に顕在化する問題です。
6. 保護者が今からできること
では、中学生の保護者は何を考えるべきでしょうか。
- 学校選びを“総費用”で考える
授業料だけでなく、入学金・施設費・教材費・通学費まで含めて比較する。 - 塾代の見通しを立てる
受験期にどのくらいかかるのかを把握し、家計に組み込む。 - 制度に振り回されない視点を持つ
「無償化だから安心」ではなく、「子どもに合う教育環境はどこか」で判断する。 - 情報収集を怠らない
地域ごとの倍率変動や学校改革の動きをチェック。数年単位で流れが変わる可能性があります。
7. まとめ
高校授業料無償化の恩恵を最も大きく受けるのは、今の中学生世代です。
しかし同時に、制度の副作用(私立人気・公立衰退・塾代増大・格差拡大)を一番強く受けるのもこの世代です。
保護者として大切なのは、
- 制度を「家計が助かる」という視点だけで見ないこと
- 子どもに合った進路と教育環境を見極めること
- 外部教育費や長期的な資金計画を準備すること
「直撃世代」だからこそ、冷静な判断と準備が求められます。
✍️ 次回(第6記事)では、「小学生の保護者編|長期戦略がカギ! 無償化時代を見据えた教育費計画」 を解説します。

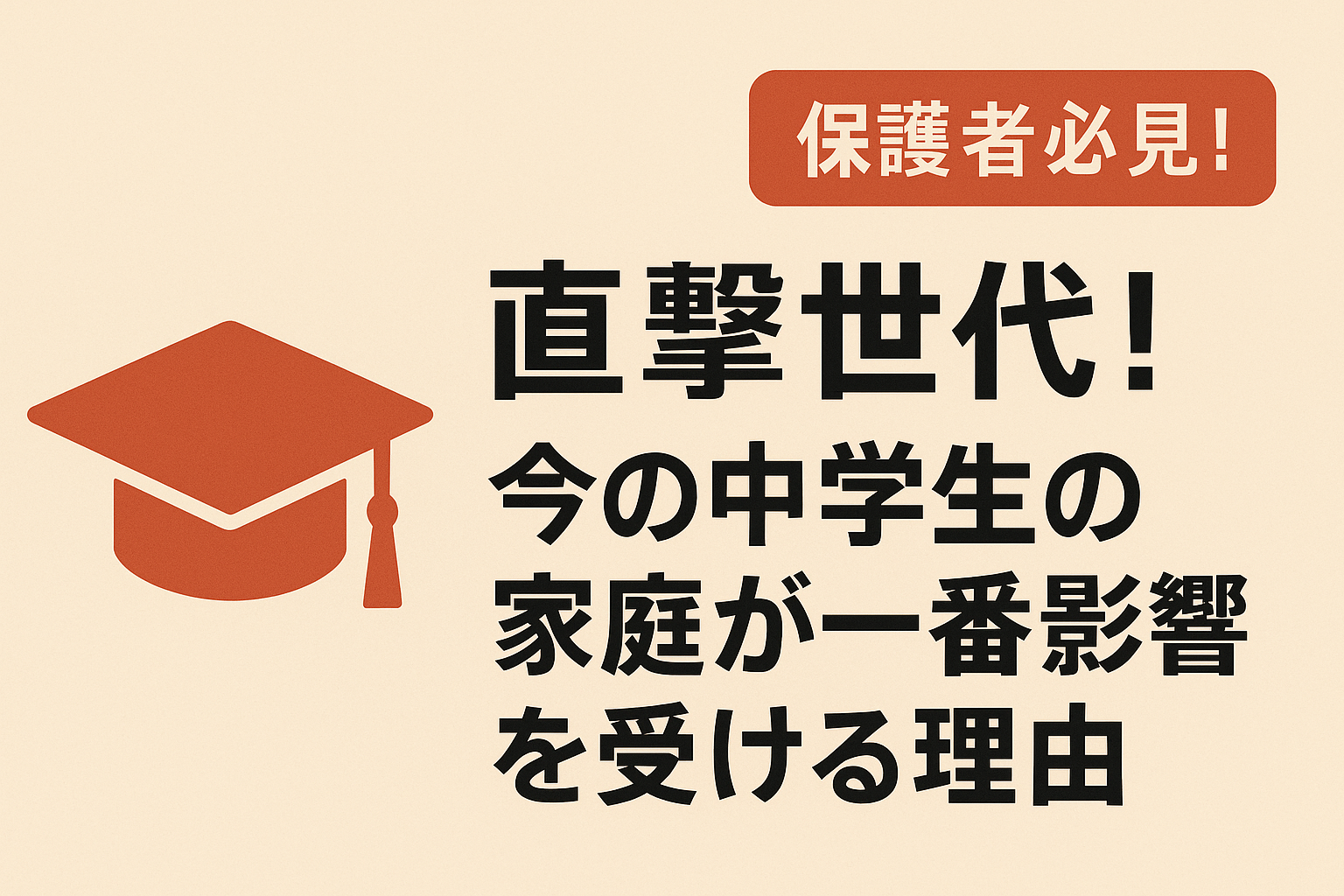
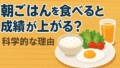

コメント