子どもの未来を育てる習い事選び|第2回
はじめに ― 習い事の選び方に迷われる保護者の皆さまへ
小中学生の保護者の方とお話をしていると、「英会話や水泳はよく聞くけれど、プログラミングは本当に必要なの?」とよく質問されます。
教育現場で子どもたちを指導していると、保護者の方が**「自分の経験の範囲でしか習い事を選べていない」**と感じることが少なくありません。
大人世代が受けてきた教育と、これからの子どもたちに必要とされるスキルの間には、大きなギャップがあるのです。
📊 「お勧め」と「人気」ランキングの比較
まずは前回の 未来社会に役立つ習い事おすすめランキング(教育者視点) と、実際に調査で出ている**人気ランキング(保護者・子ども調査)**を並べてみましょう。
お勧めランキング(AI社会で役立つスキル)
- プログラミング(論理的思考・AIリテラシー、OECDや文科省も必須スキルと明示)
- 英会話・ディベート(グローバル発信力、論理的思考、他者理解)
- 読書・文章・スピーチ(情報整理力、表現力、批判的思考)
- ロボット・STEAM教育(ものづくり・創造力・試行錯誤力)
- 思考系ボードゲーム(戦略性・論理力・集中力)
実際の人気ランキング(日本の小中学生・保護者調査)
(出典:ベネッセ教育情報サイト「【最新版】子どもに人気の習い事ランキング」2024年、学研「子どもの習いごとに関する意識調査」など)
- 水泳(体力づくり・健康・安心感)
- 学習塾(勉強や受験に直結する安心感)
- 英会話(小学校で必修化・将来役立つイメージ)
- ピアノ・音楽(情操教育・根気を養える)
- 通信教育(自宅で取り組みやすく費用も比較的安価)
- ダンス(楽しく体を動かせる、表現力やリズム感を育てる)
- サッカー(仲間との協調性、体力強化)
- 習字・書道(字の美しさ、集中力、礼儀作法)
- プログラミング(興味はあるが通える環境や情報が限られる)
- そろばん・その他の習い事(基礎学力強化、集中力を養う)
🎯 ズレが生まれる理由
お勧めランキングでは「未来社会に役立つスキル」を重視してプログラミングが1位に挙がりました。
しかし実際の人気ランキングを見ると、プログラミングは9位。なぜこのようなギャップが生まれるのでしょうか?
- 親世代が習った経験の有無
英会話やピアノは、多くの保護者が自身の子ども時代に経験しています。そのため「習わせておけば安心」という実感があり、自然と選びやすくなる傾向があります。
一方でプログラミングは新しい分野で、親自身が習った経験がほとんどないため、何が身につくのかイメージしづらいのです。 - “目に見える成果”の分かりにくさ
水泳なら進級バッジ、書道なら段位や作品展示など、成果がすぐに形になります。
対してプログラミングは、コードを書いて画面に小さな変化が起きるだけ。大人から見ると「何を学んでいるの?」と分かりにくいのかもしれません。
👉 私の教室では、最初に「キャラクターをジャンプさせる」という小さな成功を体験してもらいます。子ども自身が「自分で考えた命令で動いた!」と感じた瞬間に、ぐっと自信が生まれます。この変化を保護者の方に見てもらうと、プログラミングが単なる“パソコン遊び”ではなく、思考を言葉にする力を育てる学びだと理解していただけます。
- 将来とのつながりが伝わっていない
OECDや文科省はプログラミング的思考を重視していますが、保護者の方の多くはまだその価値を実感できていません。
「プログラムが書けて何になるの?」という疑問が先に立ち、結果として選択の優先度が下がってしまうのです。
これからの選び方のヒント
- 「すぐ役立つか」だけでなく「未来で活きるか」を考える
- 子どもが“楽しい”と感じるかどうかを大切にする
- 保護者が知らない分野でも、子どもの興味を尊重する
おわりに ― ギャップをどう埋めるか
調査データと現場の実感を照らし合わせると、プログラミングは未来において重要なスキルでありながら、まだまだ「選ばれにくい」習い事であることが分かります。
私自身、保護者の方と話す中で「自分が知らないから不安」「勉強に直結しないのでは」という声を聞きます。その一方で、子どもが自分のアイデアを形にし、目を輝かせる瞬間を何度も見てきました。
親が知らないことを理由に、子どもの可能性を狭めてしまうのはもったいない。
だからこそ「プログラミングがなぜ大事なのか」を正しく知り、習い事選びの視野を広げることが大切だと思います。
次回予告
お勧めランキングと実際の人気ランキングを見比べると、プログラミングは未来に必要とされているのに、まだまだ選ばれにくい現状が浮かび上がりました。
次回は、「保護者が知っておきたいプログラミングの選び方 ― リアルとオンラインの違い」という記事の中でプログラミング教室の学習スタイルの種類についても触れていきます。

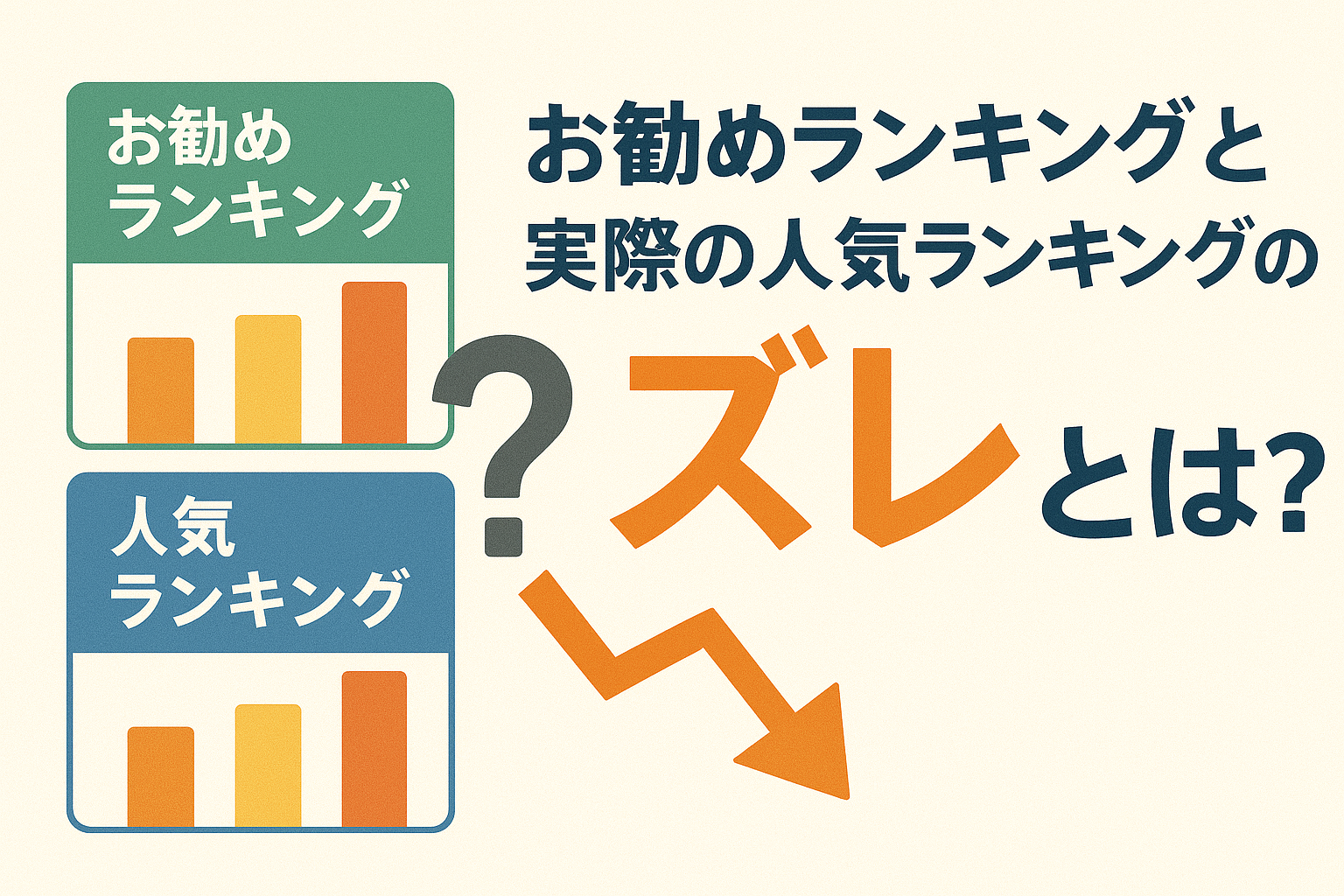
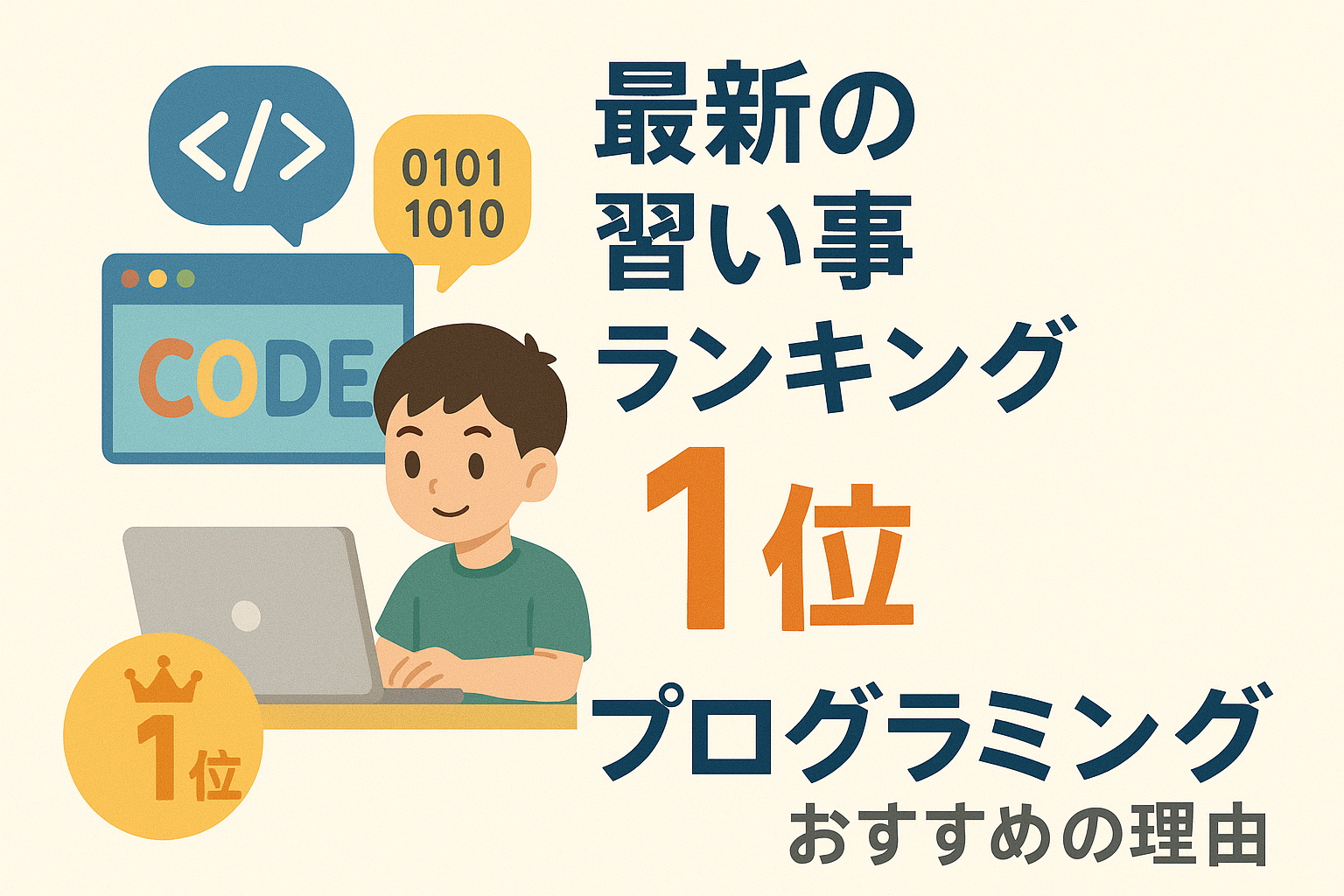
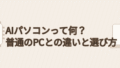
コメント