「子どものスマホやゲーム利用を制限する」──そんな条例を巡って、再び議論が活発になっています。
2020年に施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(いわゆる“ゲーム条例”)、そして2025年に愛知県豊明市で提案されたスマホ利用「1日2時間まで」条例案。
どちらも「行政(自治体)が家庭のルールに踏み込んだ」として、全国的に注目を集めました。
香川県のゲーム条例は施行から4年半が経過し、現在は「見直しフェーズ」に入り、効果や問題点を再検討する段階にあります。この記事では、香川県のケースが今どう評価されているのか、そして豊明市の新しい条例案との共通点・違いを整理しながら、行政が家庭に関わる是非を考えます。
香川県ゲーム条例(2020年施行)の概要と背景
香川県は2020年4月に「ネット・ゲーム依存症対策条例」を施行しました。
内容は以下のようなものでした。
- 利用時間制限:平日は1日60分、休日は90分まで
- 夜間利用の制限:中学生以下は21時まで、高校生は22時まで
- 対象:ゲームやスマートフォンなどインターネットを使う娯楽
特徴は「努力義務」であり、守らなくても罰則はありません。
目的は「ゲーム依存症の予防」と「子どもの健全育成」でした。
当時は「子どもの健康を守るために必要」という賛成意見がある一方で、
- 「家庭の自由に行政が介入するのはやりすぎ」
- 「科学的根拠が薄い」
- 「時間で縛るのではなく、どう使うかが大事」
といった批判も強く、全国的に物議を醸しました。
4年半後の評価と見直し議論(2024年)
2024年秋、施行から4年半を経た香川県議会では、条例の成果や課題を議論する見直しフェーズに入りました。
- 効果検証が難しい
「条例のおかげで依存が減った」と断定できるデータは乏しい。 - 名称の問題
「依存症」という言葉が偏見を生むのではないか、として名称変更の検討も。 - 実効性への疑問
結局は家庭ごとの自主性に委ねられており、強い効果は出ていない。
つまり、「大きな効果は確認できないが、話題になったことで家庭や学校で考えるきっかけになった」というのが現状の評価です。
豊明市スマホ利用制限条例案(2025年)の特徴
愛知県豊明市が提案したのは、**「学校外でのスマホ利用は1日2時間まで」**という条例案。
- 時間制限:利用は2時間を目安
- 夜間利用の制限:小学生は21時まで、中高生は22時まで
- 罰則:なし
内容を見ると、香川県ゲーム条例と非常によく似ています。
賛成派の声:
- 子どもの健康や学力を守るために有効
- 家庭でルールを話し合うきっかけになる
反対派の声:
- 家庭の自由に行政が介入すべきではない
- 守っているかどうか確認できず、実効性に乏しい
まさに香川県のときと同じ構図で、賛否が二分しています。
共通点と違い
共通点
- どちらも「努力義務」で罰則なし
- 子どもの健康や学習環境を守る目的
- 家庭のルール作りを後押しする意図
- 「行政が踏み込みすぎでは?」という批判が多い
違い
- 香川県:県レベルで全域に適用
- 豊明市:市レベルで、影響範囲は小さい
- 香川県:ゲーム依存症という病理的視点を強調
- 豊明市:スマホ利用の生活習慣・睡眠不足への配慮を強調
行政が家庭に関与する意味
では、なぜ行政はこのような「家庭に関わるルール」をあえて条例で示すのでしょうか?
- 市民に対して強いメッセージを出すため
「ただのキャンペーン」より条例の方が重みがある。 - 家庭や学校で話し合いを促すため
「市が決めた」という大義名分があると、親子で向き合いやすい。 - 社会問題として注目を集めるため
条例にすることでニュースに取り上げられ、意識が広がる。
一方で、「本当に条例にする必要があったのか」「啓発や教育活動では不十分だったのか」という疑問は残ります。
筆者の視点:形式より実効性を
筆者自身は、香川・豊明どちらのケースも「家庭の問題に行政が入り込みすぎ」と感じます。
確かにスマホやゲームの依存問題は深刻ですが、数字で一律に制限しても根本的な解決にはなりません。
しかし一方で、条例がニュースになることで、家庭や学校で「スマホとの付き合い方を話し合うきっかけ」が生まれたのも事実です。
つまり「条例の強制力」ではなく「条例の話題性」に意義があったのだと思います。
まとめ
- 香川県ゲーム条例は2020年施行、2024年に見直しフェーズに入り「効果は限定的だが話題になった意義はあった」と評価されている。
- 豊明市スマホ条例案(2025年)も同様に「罰則なし」で、家庭に踏み込む姿勢に賛否が分かれている。
- 共通して言えるのは、行政の本当の狙いは「市民に考えてもらうきっかけ作り」であり、強制的に取り締まることではない。
結局のところ、スマホやゲームとの向き合い方は、行政ではなく家庭や子ども自身が考えるべき課題です。条例はあくまで「きっかけ」であり、実効性ある教育や家庭での対話こそが重要だと言えるでしょう。

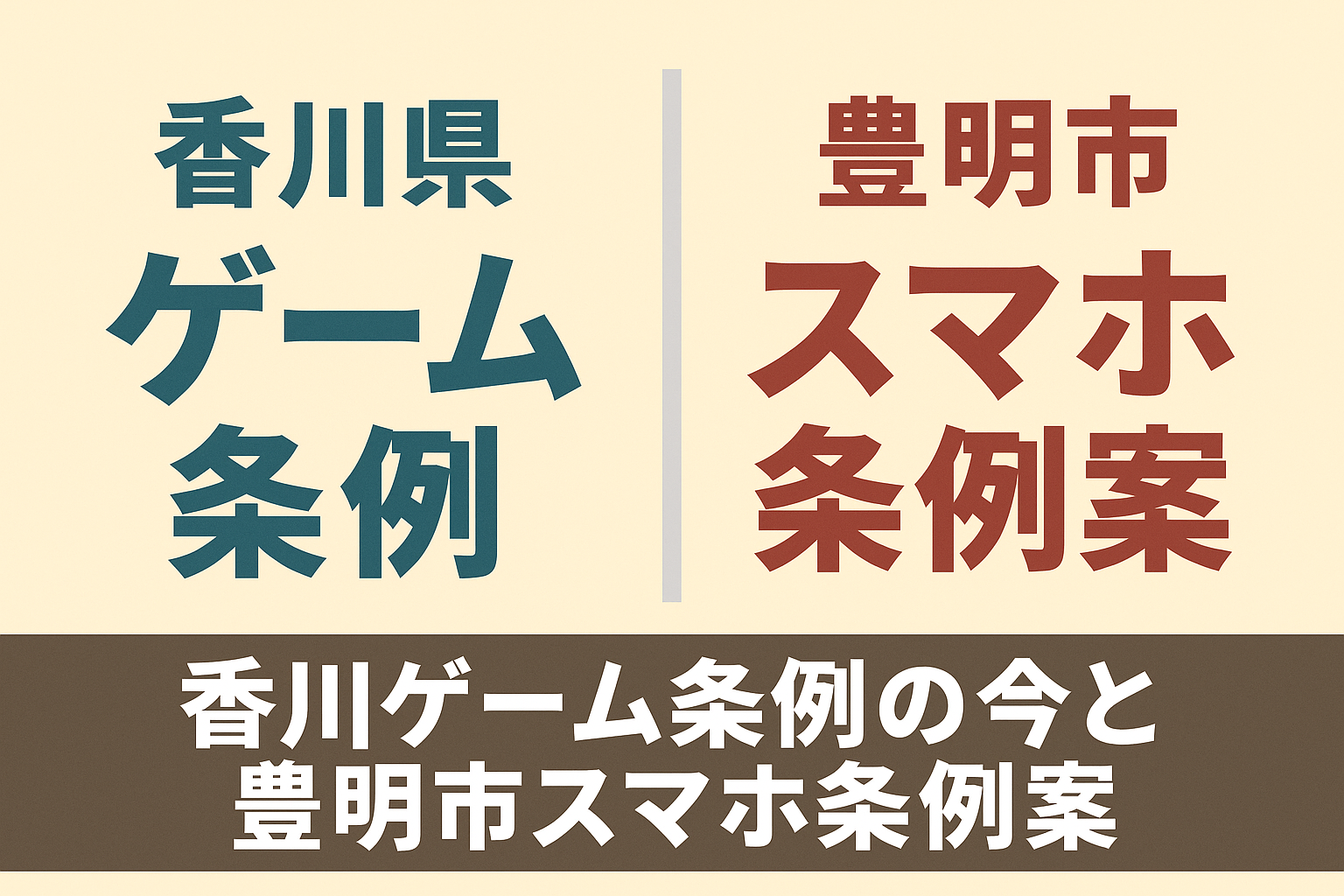
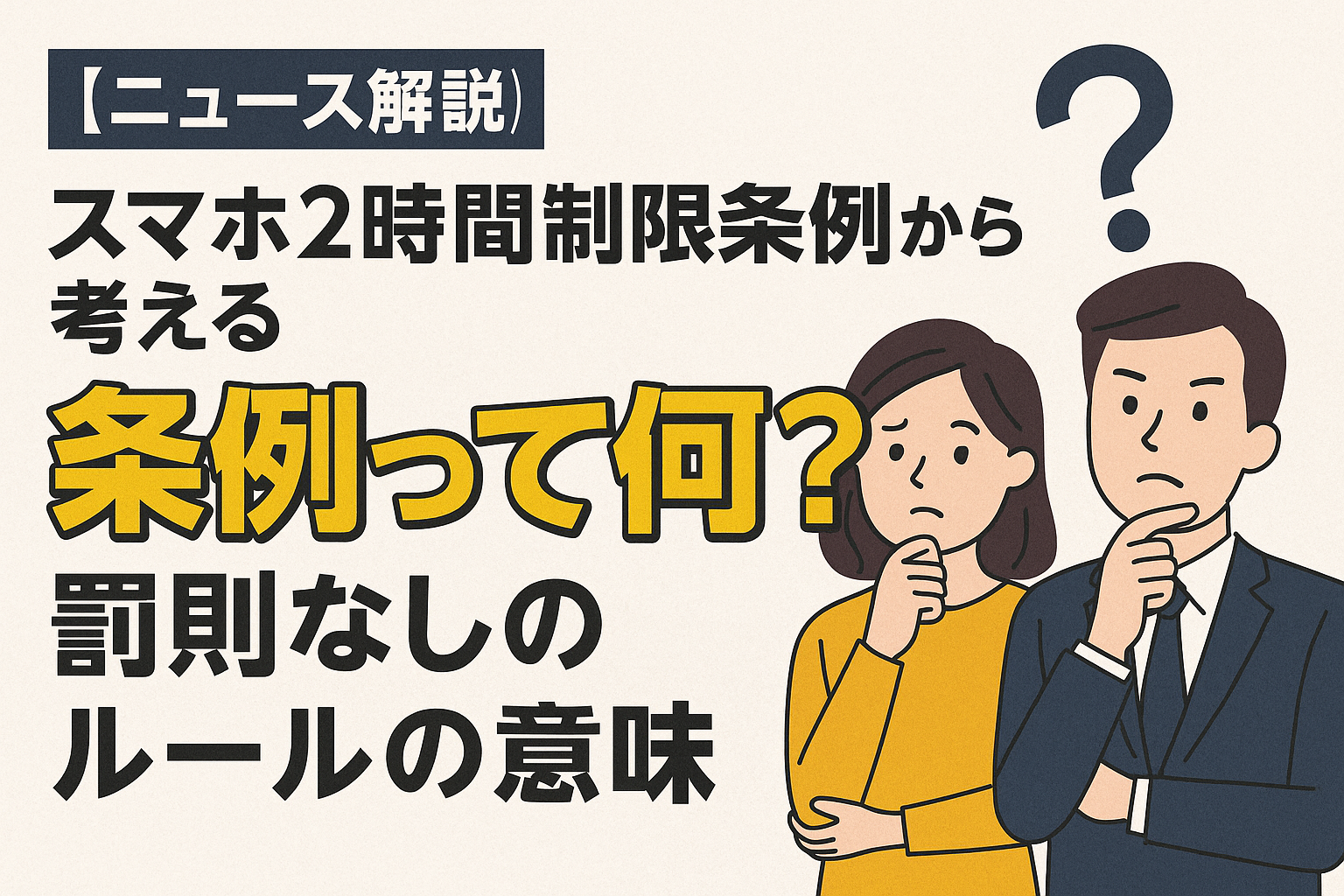
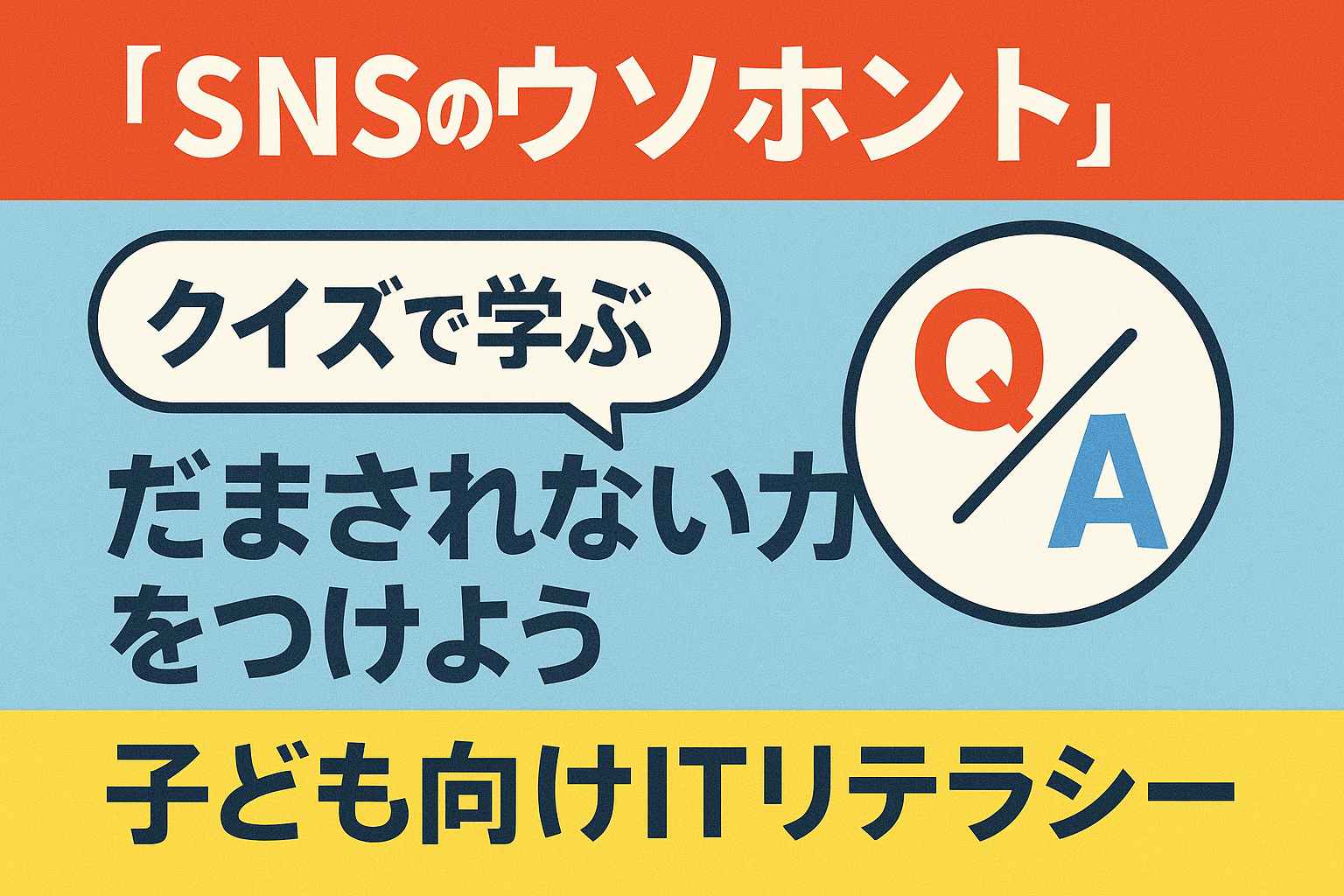
コメント