― “逃げ”ではなく“判断”を教える時代へ ―
はじめに:退職代行が当たり前になった社会
近年、「退職代行」という言葉をよく耳にするようになりました。
電話一本、あるいはLINEひとつで退職を代わりに伝えてくれる――
そんなサービスが次々と登場し、SNSでも「助かった」「心が救われた」という声が目立ちます。
確かに、上司に直接言えないほど精神的に追い詰められている人にとって、
このサービスは“命綱”のような存在です。
辞める自由は誰にでもあり、命より大切な仕事などありません。
そう考えれば、退職代行の存在には一定の意味があります。
なぜここまで追い込まれる前に「判断」できないのか
ただ一方で、私はどうしてもこう思ってしまいます。
「そこまで追い詰められる前に、退職という判断をできなかったのか」と。
人は、つらいときほど「もう少し頑張れば」「自分が弱いだけだ」と自分を責めてしまいます。
その結果、気づけば心が限界を超え、身動きが取れなくなってしまう。
本当に必要なのは、「頑張る力」ではなく、壊れる前に立ち止まる判断力ではないでしょうか。
逃げ道があることで生まれる「低いほうへ流れる」心理
もうひとつ、私が懸念しているのはここです。
退職代行のような“逃げ道”があることで、
人は無意識のうちに「楽なほうへ流れる」心理状態になります。
「最悪、頼めば辞められる」と思うことで、
本来ならあと一歩踏み出せば乗り越えられた人たちまで退職を選んでしまう。
便利さが人を助ける一方で、“自分で向き合う力”を静かに奪っていく。
これこそ、私たちが今いちばん注意すべき現象だと思います。
社会が目指すべきは「逃げない社会」ではなく「逃げなくて済む社会」
ここで誤解してほしくないのは、
私は「逃げるな」と言いたいわけではありません。
逃げることでしか守れない命も、心もあります。
ただ、私たちが本当に目指すべきは、
「逃げなくても済む社会」を作ることです。
そのために会社側として必要な対応は次の3つです。
- 早めに相談できる環境を整えること
- 意見を言いやすい職場や組織をつくること
- 「我慢より判断」を教える教育を広げること
これらが実現すれば、退職代行が「最後の手段」ではなく「不要な選択肢」になっていくはずです。
まとめ:逃げる勇気よりも、壊れる前に「ここまで」と言える力を
退職代行を使う人を責めるつもりはありません。
追い詰められた末の選択なら、それは立派な“生きるための行動”です。
ただ、私はこう思います。
逃げる勇気よりも、壊れる前に「ここまで」と言える判断力を持ってほしい。
その力を持つ人は、どんな職場に行っても、きっと自分の人生を自分で選び取れるはずです。
✍️ 著者メモ
この記事は、退職代行「モームリ」報道をきっかけに、
“逃げ”ではなく“判断”の大切さを考える視点からまとめました。
便利なサービスの裏にある「人の心の動き」こそ、
私たちがこれから教育の中で伝えていくべきテーマだと感じています。

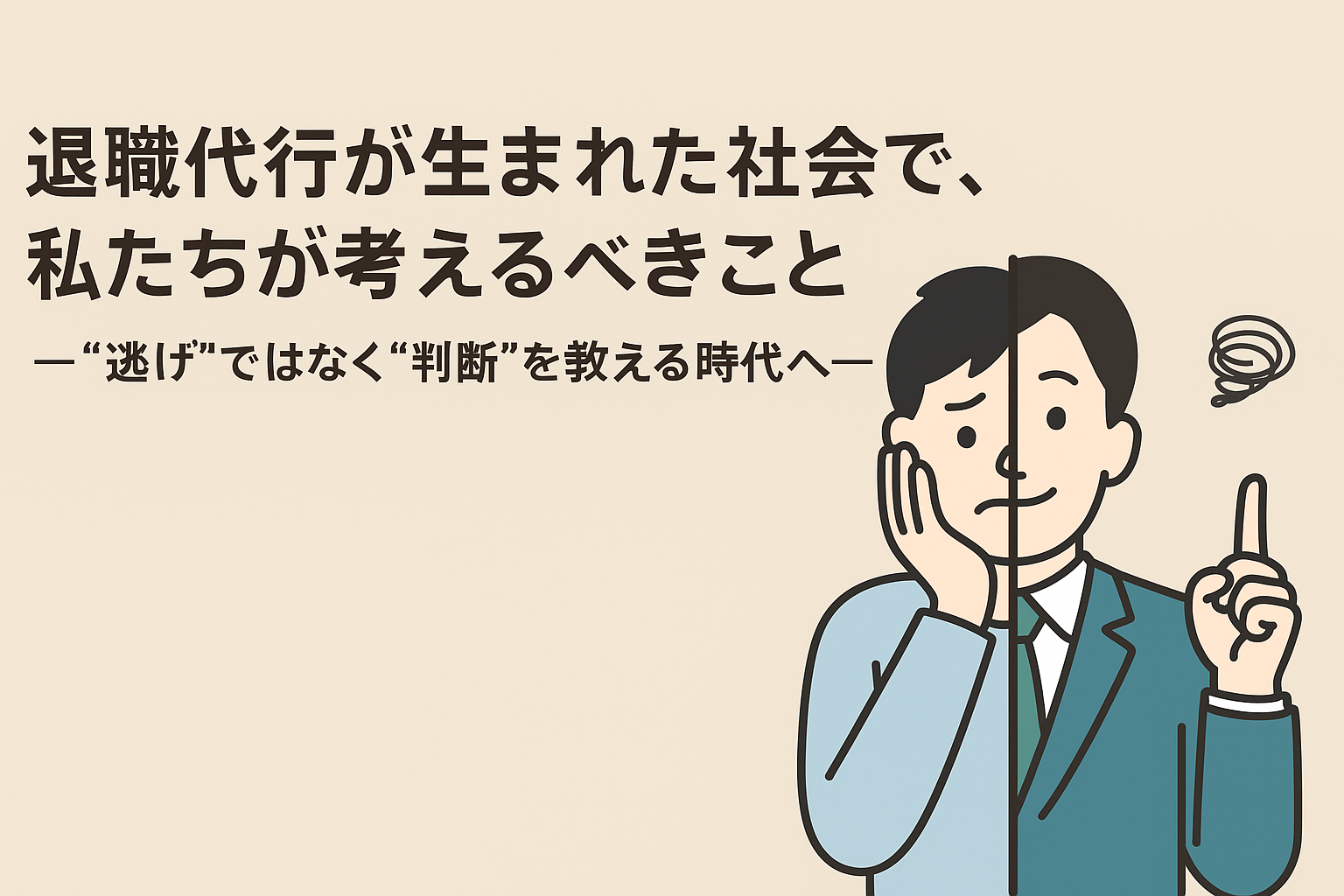
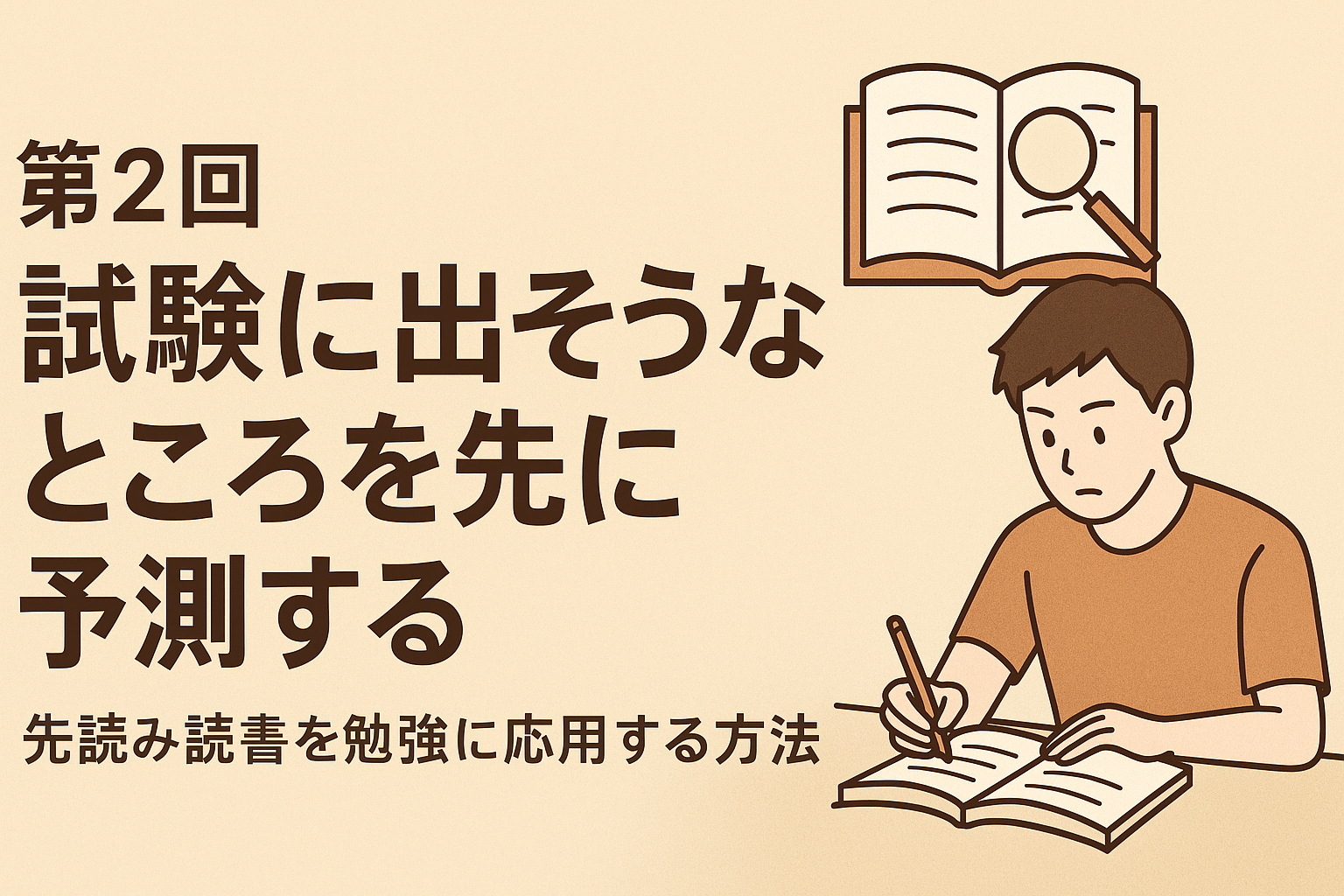
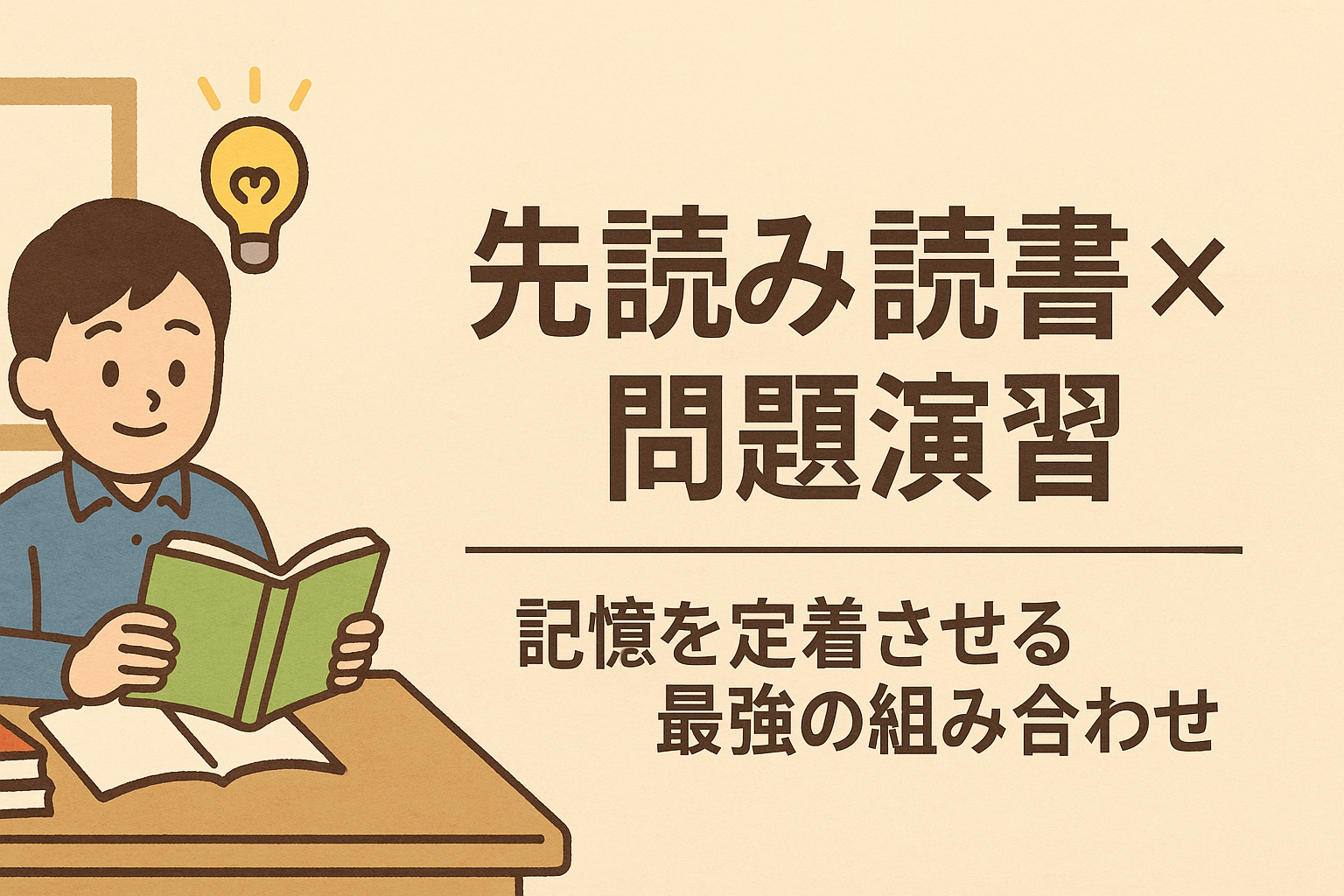
コメント