2025年10月14日——この日はWindows 10の公式サポートが終了する日として、長らくカウントダウンされてきました。しかし最近、マイクロソフトが「延長セキュリティ更新プログラム(ESU)」を提供することを発表し、Windows 10を2028年まで使い続ける道が開かれました。
この記事では、その延長サポートの概要、費用、注意点、そして導入の判断基準をわかりやすく解説します。
🗓 いつまで使える?延長スケジュールまとめ
| 項目 | 日付・期間 |
|---|---|
| 通常サポート終了 | 2025年10月14日 |
| 延長サポート(ESU)開始 | 2025年10月15日 |
| ESUによる最長延長 | 2028年10月まで(最大3年間) |
延長サポートの対象は Windows 10 Enterprise、Education、Pro エディションなど。家庭向けのHome版は原則サポート外ですが、有償アップグレードや特定企業向けの措置が取られる可能性もあります。
💸 延長は「有料」です。費用は?
延長サポート(ESU)は有償となっており、以下のような価格モデルが想定されています(※正式価格は国・法人向け契約により異なります)。
| 年数 | 企業向け想定費用(1台あたり) |
|---|---|
| 1年目(2025-2026) | 約61ドル(9,000円前後) |
| 2年目(2026-2027) | 約122ドル(倍額になる傾向) |
| 3年目(2027-2028) | 約244ドル(さらに倍増) |
※参考:Windows 7のESU価格構成と類似の想定。
つまり、延長を選ぶほどコストが上がる仕組みです。
🤔 使い続ける?それとも移行する?
Windows 10を延長して使い続けるメリット:
- 現行PCを買い替えずに済む
- 特定業務アプリの互換性維持
- IT管理体制を大きく変更しなくて済む
Windows 11などへの移行を検討すべきケース:
- 最新セキュリティ対策が必要な業務
- ハードウェアがWindows 11対応済み
- クラウドやAI機能を本格的に活用したい
特に企業や教育機関では、「2025年までに全PCをWindows 11に移行するのが難しい」ケースも多いため、**ESUは“移行のための猶予期間”**と捉えるのがよいでしょう。
🛠 どうやって延長サポートを利用する?
マイクロソフトはMicrosoft 365管理センター、Azure Arc、Intuneなどを通じて、ESUの購入や配布を支援するとしています。
また、一般消費者向けにも「有償での延長手段」を提供する予定とのこと。個人PCでもWindows 10を継続利用する道が完全に閉ざされたわけではありません。
✅ まとめ:今やるべきこと
| やるべきこと | 解説 |
|---|---|
| 自分のPCがWindows 11対応か確認 | 「PC正常性チェックツール」で確認可能 |
| 延長が必要か、移行かを判断 | ソフト互換、予算、スケジュールを基準に |
| ESU導入に備える | IT管理者はMicrosoftの公式情報を随時チェック |
✍ 編集後記
今回の発表は、Windows 10ユーザーにとって大きな安心材料になりました。ただし、「使い続けられる」ことと「安全で快適に使える」ことは別物です。最終的なゴールは移行であることを忘れず、戦略的な判断が求められます。

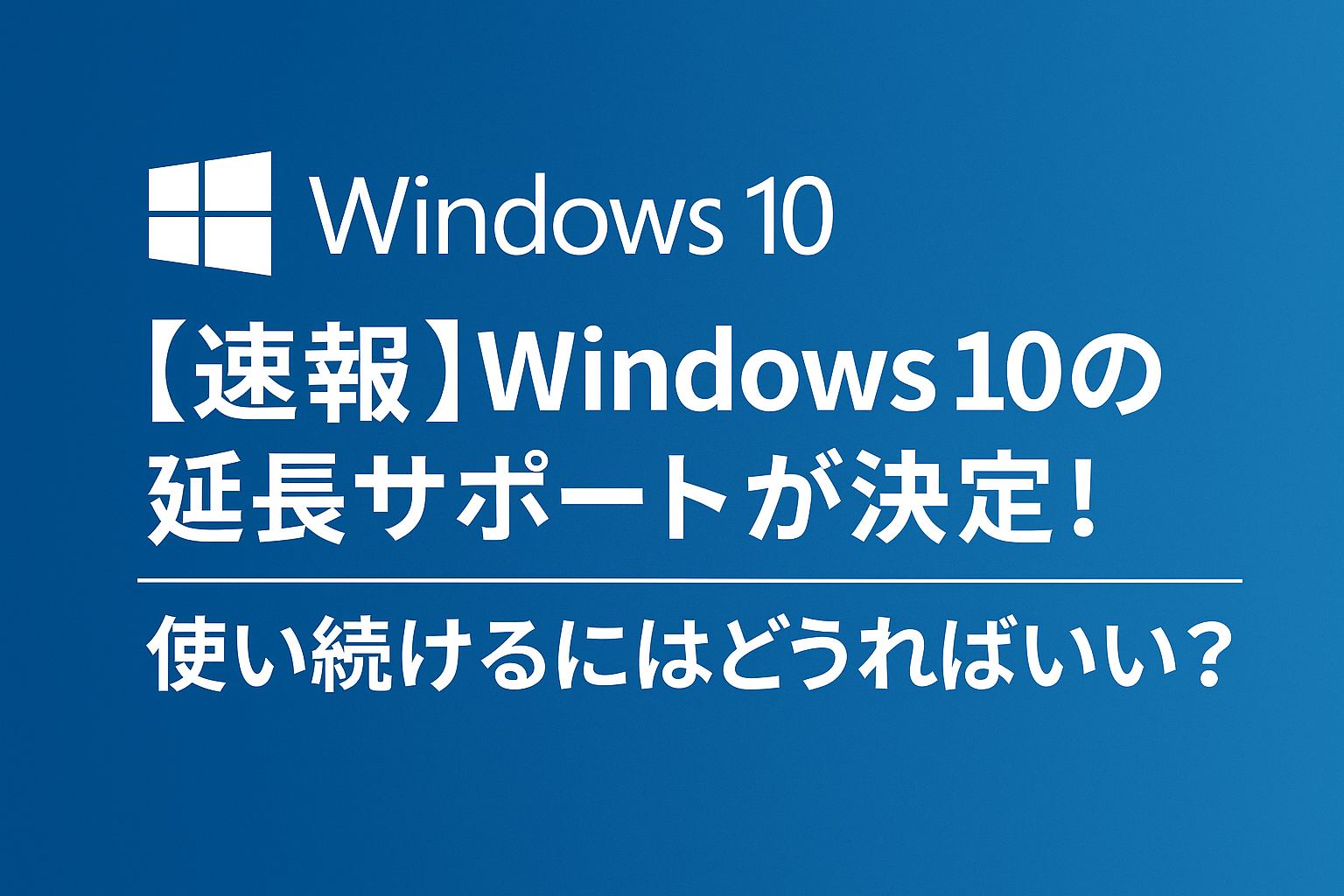
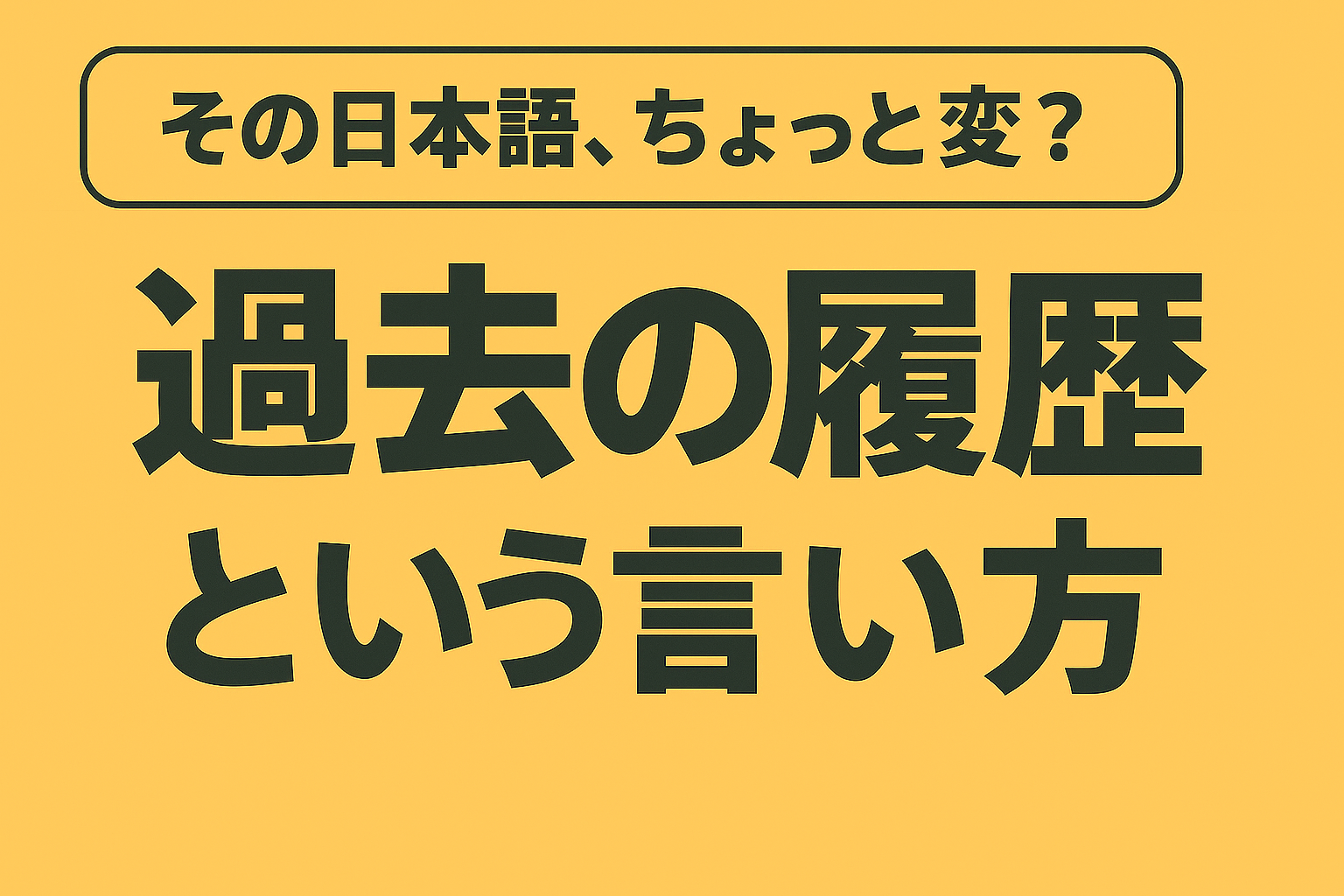

コメント